サステナビリティ経営とは?必要性や具体的な取り組みを解説
経営全般・事業承継
2025年09月30日(火)掲載
近年、さまざまな場面で見聞きする「サステナビリティ」とは、環境、社会、経済の観点で考えられる持続可能性のことです。
この考え方は、経営にも取り入れられます。では、サステナビリティ経営を実現するために、どのようなことを行えばよいのでしょうか。
本記事では、サステナビリティ経営について基礎的な知識を解説します。
環境や社会にやさしい経営を目指し、企業としての価値を高めたい事業者の方は、ぜひご覧ください。
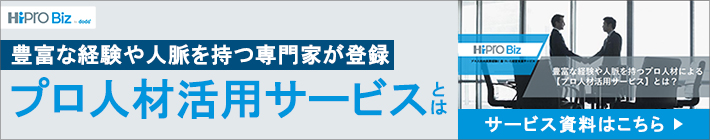
サステナビリティ経営では、環境、社会、経済への長期的な影響を考慮しながら商品の生産やサービスの提供を行います。 例えば、事業活動における廃棄物をゼロにして地球環境への負荷を軽減させることが挙げられます。また、ダイバーシティの実現に向けて雇用にあたりジェンダーの多様性を尊重することも、サステナビリティ経営において大切な取り組みの一つです。
サステナビリティと意味合いの似ている言葉として「SDGs」「ESG」が挙げられます。それぞれ、サステナビリティと異なる点を以下で解説します。
(参照:『総務省:持続可能な開発目標(SDGs)の進捗の測定に用いる指標について』)
サステナビリティとSDGsの具体的な違いについては、以下をご覧ください。
サステナビリティは、あくまでも持続可能性という「考え方」であるのに対し、SDGsはサステナビリティの実現に向けた「目標」である点が大きな違いです。両者は異なるものではありますが無関係ではなく、サステナビリティ経営を目指すにはSDGsを意識することも大切であるといえます。
このように経営にも関係していることから、よりサステナビリティと似た言葉にも見えますが、具体的にはどのように違うのでしょうか。
サステナビリティとESGの違い
サステナビリティとESGはいずれも、環境や社会に対する「考え方」である点は共通していますが、ESGは経済活動に特化しているという特徴があります。
関連記事:諸事例から学ぶESG/SDGs経営の導入と実践
それでは、サステナビリティ経営はなぜ現代社会で必要とされているのでしょうか。主要な3つの理由を以下で解説します。
環境問題の深刻化が進めば、人間社会全体への悪影響につながり、そのような事態となれば企業活動をこれまでのように行えなくなってしまいます。現状の問題を少しでも改善し、多くの人々が健全に社会活動を続けるためにも、企業単位でサステナビリティに取り組む必要があるのです。
多くのステークホルダーは、環境や社会に対して責任のある行動を示している企業を高く評価します。企業が競争力を高めるには、ステークホルダーからの支持を得る必要があるため、サステナビリティ経営を取り入れることが求められます。
とはいえ、各種法規制を理解した上で企業が適応していくことは、そう簡単ではありません。そのため、サステナビリティ経営の一環として法規制に順応するには、専門知識に秀でたプロ人材のアドバイスを求めることをお勧めします。
「HiPro Biz」では、法務やガバナンスの領域に精通したプロ人材が、サステナビリティ経営を実現するための支援をいたします。
経営支援サービス「HiPro Biz」
サステナビリティ経営を実現することで、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。以下で、5つのメリットを解説します。
例えば、特定の地域の自然保護に直結する活動を企業が実施し、地域住民の生活の品質が向上すれば、その地域からの評価が向上するでしょう。また、活動が広く知れ渡れば、地域外のステークホルダーからも「環境問題に向き合っている企業だ」という評価を得られます。
さらに、ブランドイメージが向上すれば、環境問題を重視する顧客からの信頼がより得やすくなるというメリットもあります。
さらに、その結果、新たなアイデアやビジネスチャンスの創出につながる機会もあるかもしれません。サステナビリティ経営は、地球環境だけでなく企業の未来にまでつながる可能性を秘めています。
まず、法的リスクに関しては、各法令を順守することがサステナビリティ経営と直結しているため、サステナビリティ経営の実施により法令順守を徹底した企業を目指すことが可能です。
また、評判リスクの観点は、先に挙げた「ブランドイメージの向上」と関連しています。ステークホルダーに評価される活動を推進することで、結果的に自社の評判を損なうリスクの軽減につながるということです。
「サステナビリティを意識したい」と考えている消費者は多く存在します。例えば、エコラベルのある製品や地球環境に配慮したサービスを提供することで、そのような消費者に選ばれ、競争優位性を築くことも可能でしょう。
なぜなら、サステナビリティ経営の指標の一つである「GRIスタンダード」という基準には、「社会」という項目の中に「雇用」や「労働安全性」など、従業員の雇用に関連する内容も定められているためです。つまり、GRIスタンダードを基準にサステナビリティ経営を目指すことで、従業員にとっても過ごしやすい企業になるということです。
また、サステナビリティ経営を適切に行い、自社が地球環境や社会に貢献している企業である事実が認識されれば、従業員が誇りに感じることも考えられます。「印象の良い企業ではたらいている」という事実も、エンゲージメント向上に寄与するということです。
GRIスタンダードは、あくまでもガイドラインであり、法律ではないため必ずしも沿う必要はありません。しかし、世界的に用いられている指標であり、報告内容の透明性を担保できるというメリットがあるため、適切に活用することで自社の取り組みをより明確に発信できるようになるでしょう。
具体的に、どのようなことに取り組めばサステナビリティ経営を行えるのでしょうか。ここからは、具体的な手順について解説します。
現状を把握できれば、自社がこれから取り組む必要があると思われる課題と、その解決に向けて必要な施策が明確になります。目標の設定にあたっては、漠然としたものを掲げるのではなく「何を解決するために、いつまでに、どのような姿を目指すのか」を明確に定めることが大切です。
SDGsの達成期限とされている2030年や、カーボンニュートラルの目標年である2050年といった、世界で掲げられている目標を取り入れても良いでしょう。
このような取り組みを行い、事業活動が地球環境に与える悪影響を最小限に抑えることが重要です。地球環境に配慮することにより、環境問題への将来的なリスクが軽減され、持続活動な事業活動を実現できます。
なお、JMAホールディングスグループが日本国内の企業を対象に2023年に実施した調査では、「ステークホルダーに対して、開示している項目」(複数回答)という設問で、74.3%の企業が「環境負荷対応状況(製品ライフサイクル、再生可能原料、省エネなど)」と回答しました。このことから、サステナビリティ経営を行っている多くの企業が環境負荷への対応に取り組んでいることがわかります。
(参照:『JMAホールディングスグループ 4社合同調査―『サステナビリティ経営課題実態調査2023』速報-』)
先ほど取り上げたJMAホールディングスグループの調査結果では、ステークホルダーへの報告内容として、「社会への取り組み」に関連する以下の項目が挙がっています。
上記を参考に、社内外と良好な関係を構築し、より良い社会を目指すための取り組みを行いましょう。
(出典:『JMAホールディングスグループ 4社合同調査―『サステナビリティ経営課題実態調査2023』速報-』)
サステナビリティ経営に求められるガバナンスに関する取り組みとしては、以下の例が挙げられます。
ガバナンスの観点でも、JMAホールディングスグループの調査結果を見てみましょう。
上記のように、適切なガバナンス体制を構築するための取り組みを行うことで、健全な経営の推進と維持を実現できます。
(出典:『JMAホールディングスグループ 4社合同調査―『サステナビリティ経営課題実態調査2023』速報-』)
株主総会や顧客向けのリリースはもちろん、ホームページやSNSなども活用して、より多くのステークホルダーに情報を届けることをお勧めします。取り組みを適切に発信することで信頼が高まり、より良い企業活動へとつながることが期待できます。
サステナビリティ経営が具体的にどのような経営であるのか、また実施にあたり何から取り組むべきなのか、イメージいただけたでしょうか。
サステナビリティ経営に必要な取り組みにはさまざまなものがありますが、どれを選ぶ場合でも、ステークホルダーへの報告が必要です。持続可能な地球環境や社会の実現のため、自社が取り組めることを考え、適切に報告を行っていきましょう。
サステナビリティ経営に関してお悩みの管理者や経営者の方は、「HiPro Biz」へのご相談を検討ください。ガバナンスの専門知識を有しているプロ人材が、課題を解決に導きます。
この考え方は、経営にも取り入れられます。では、サステナビリティ経営を実現するために、どのようなことを行えばよいのでしょうか。
本記事では、サステナビリティ経営について基礎的な知識を解説します。
環境や社会にやさしい経営を目指し、企業としての価値を高めたい事業者の方は、ぜひご覧ください。
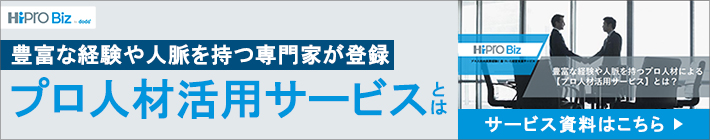
目次
■サステナビリティ経営とは?
■サステナビリティとSDGsやESGとの違い
■サステナビリティ経営が必要とされる理由
■サステナビリティ経営がもたらすメリット
■サステナビリティ経営の具体的な取り組みと手順
■サステナビリティ経営は、ステークホルダーへの報告まで行うことが大切
サステナビリティ経営とは?

サステナビリティ経営では、環境、社会、経済への長期的な影響を考慮しながら商品の生産やサービスの提供を行います。 例えば、事業活動における廃棄物をゼロにして地球環境への負荷を軽減させることが挙げられます。また、ダイバーシティの実現に向けて雇用にあたりジェンダーの多様性を尊重することも、サステナビリティ経営において大切な取り組みの一つです。
サステナビリティとSDGsやESGとの違い
サステナビリティと似ている言葉
- SDGs
- ESG
SDGsとの違い
SDGsは、国連が2015年に採択した「2030年までの持続可能な世界を目指すための17の目標」を指します。さらに、17の目標を達成するための169のターゲットも設定されており、その数は247にも及びます。(参照:『総務省:持続可能な開発目標(SDGs)の進捗の測定に用いる指標について』)
サステナビリティとSDGsの具体的な違いについては、以下をご覧ください。
サステナビリティとSDGsの違い
| 言葉の意味 | 概要 | |
|---|---|---|
| サステナビリティ | 持続可能性 | 環境、社会、経済に配慮する考え方 |
| SDGs | 持続可能な開発目標 | サステナビリティを実現するための具体的な目標 |
ESGとの違い
「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の略語が、ESGです。ESGは、企業が長期的な成長を目指すために必要な観点とされており、近年はESGに配慮した経営である「ESG経営」も重視されつつあります。このように経営にも関係していることから、よりサステナビリティと似た言葉にも見えますが、具体的にはどのように違うのでしょうか。
サステナビリティとESGの違い
| 言葉の意味 | 概要 | |
|---|---|---|
| サステナビリティ | 持続可能性 | 環境、社会、経済に配慮する考え方 |
| ESG | 環境、社会、企業統治の略語 | 上記の中でも特に、経済活動に特化した考え方 |
関連記事:諸事例から学ぶESG/SDGs経営の導入と実践
サステナビリティ経営が必要とされる理由
サステナビリティ経営が必要とされる理由
- 深刻な環境問題への対応
- 企業の社会的責任の高まり
- 環境保護や社会福祉の法律や規制の順守
深刻な環境問題への対応
サステナビリティ経営が重視されるようになった大きな背景として、環境問題の深刻化が挙げられます。産業革命以降、世界中の経済活動により二酸化炭素の排出量は増え続けており、廃棄物も増加しています。これらの問題により、地球環境が悪化していることは紛れもない事実です。環境問題の深刻化が進めば、人間社会全体への悪影響につながり、そのような事態となれば企業活動をこれまでのように行えなくなってしまいます。現状の問題を少しでも改善し、多くの人々が健全に社会活動を続けるためにも、企業単位でサステナビリティに取り組む必要があるのです。
企業の社会的責任の高まり
ステークホルダーから、社会的責任のある企業が求められているという点も、サステナビリティ経営が必要とされる理由の一つです。多くのステークホルダーは、環境や社会に対して責任のある行動を示している企業を高く評価します。企業が競争力を高めるには、ステークホルダーからの支持を得る必要があるため、サステナビリティ経営を取り入れることが求められます。
環境保護や社会福祉の法律や規制の順守
環境問題の深刻化により、さまざまな業界で環境保護のための法規制が進んでおり、企業は遵守が求められています。事業活動を行うには環境問題を無視できない時代に突入しており、地球環境と企業経営を共生させていくために、サステナビリティの観点を経営に反映させることが非常に重要です。とはいえ、各種法規制を理解した上で企業が適応していくことは、そう簡単ではありません。そのため、サステナビリティ経営の一環として法規制に順応するには、専門知識に秀でたプロ人材のアドバイスを求めることをお勧めします。
「HiPro Biz」では、法務やガバナンスの領域に精通したプロ人材が、サステナビリティ経営を実現するための支援をいたします。
経営支援サービス「HiPro Biz」
サステナビリティ経営がもたらすメリット
サステナビリティ経営がもたらすメリット
- 企業価値・ブランドイメージの向上
- 他企業との連携
- リスクマネジメントの強化
- 市場競争力の強化
- 従業員のエンゲージメント向上
企業価値・ブランドイメージの向上
サステナビリティ経営での取り組みによって、企業が地球環境や社会に貢献することで、企業のブランドイメージの向上が期待できます。例えば、特定の地域の自然保護に直結する活動を企業が実施し、地域住民の生活の品質が向上すれば、その地域からの評価が向上するでしょう。また、活動が広く知れ渡れば、地域外のステークホルダーからも「環境問題に向き合っている企業だ」という評価を得られます。
さらに、ブランドイメージが向上すれば、環境問題を重視する顧客からの信頼がより得やすくなるというメリットもあります。
他企業との連携
サステナビリティ経営を実施し、地球環境に配慮した活動を行うことで、地域住民や関連企業との連携が生まれることもあるでしょう。新たな接点をきっかけに、新規取引先やパートナーの獲得も期待できます。さらに、その結果、新たなアイデアやビジネスチャンスの創出につながる機会もあるかもしれません。サステナビリティ経営は、地球環境だけでなく企業の未来にまでつながる可能性を秘めています。
リスクマネジメントの強化
法的リスクと評判が下がるリスク、2つの観点からリスクマネジメントを強化できるというメリットもあります。まず、法的リスクに関しては、各法令を順守することがサステナビリティ経営と直結しているため、サステナビリティ経営の実施により法令順守を徹底した企業を目指すことが可能です。
また、評判リスクの観点は、先に挙げた「ブランドイメージの向上」と関連しています。ステークホルダーに評価される活動を推進することで、結果的に自社の評判を損なうリスクの軽減につながるということです。
市場競争力の強化
地球環境に配慮した製品やサービスを提供することで、競合にない強みを打ち出し、市場競争力を高められるという点も、サステナビリティ経営のメリットの一つです。「サステナビリティを意識したい」と考えている消費者は多く存在します。例えば、エコラベルのある製品や地球環境に配慮したサービスを提供することで、そのような消費者に選ばれ、競争優位性を築くことも可能でしょう。
従業員のエンゲージメント向上
サステナビリティ経営が好印象をもたらす対象は、ステークホルダーだけではありません。社内で従業員のエンゲージメントが向上し、組織への帰属意識が高まる可能性もあります。なぜなら、サステナビリティ経営の指標の一つである「GRIスタンダード」という基準には、「社会」という項目の中に「雇用」や「労働安全性」など、従業員の雇用に関連する内容も定められているためです。つまり、GRIスタンダードを基準にサステナビリティ経営を目指すことで、従業員にとっても過ごしやすい企業になるということです。
また、サステナビリティ経営を適切に行い、自社が地球環境や社会に貢献している企業である事実が認識されれば、従業員が誇りに感じることも考えられます。「印象の良い企業ではたらいている」という事実も、エンゲージメント向上に寄与するということです。
GRIスタンダードとは
ステークホルダーに対しサステナビリティ経営への取り組みを報告するにあたり、多くの企業で用いられている「GRIスタンダード」と呼ばれる指標があります。GRIスタンダードは、国際的な非営利団体であるGRI(Global Reporting Initiative)が定めている、ステークホルダーへの報告を透明かつ比較可能な形で行える基準です。GRIスタンダードは、あくまでもガイドラインであり、法律ではないため必ずしも沿う必要はありません。しかし、世界的に用いられている指標であり、報告内容の透明性を担保できるというメリットがあるため、適切に活用することで自社の取り組みをより明確に発信できるようになるでしょう。
サステナビリティ経営の具体的な取り組みと手順
サステナビリティ経営の具体的な取り組みと手順
- ステップ1:現状分析と目標設定
- ステップ2:具体的な施策の実行
- ステップ3:情報開示とステークホルダーへの共有
ステップ1:現状分析と目標設定
まずは、自社の現状を把握します。「環境、社会、経済の観点で、自社は社会とどのように関わっているのか」を振り返りましょう。現状を把握できれば、自社がこれから取り組む必要があると思われる課題と、その解決に向けて必要な施策が明確になります。目標の設定にあたっては、漠然としたものを掲げるのではなく「何を解決するために、いつまでに、どのような姿を目指すのか」を明確に定めることが大切です。
SDGsの達成期限とされている2030年や、カーボンニュートラルの目標年である2050年といった、世界で掲げられている目標を取り入れても良いでしょう。
ステップ2:具体的な施策の実行
ステップ1で定めた目標に向けて、具体的な施策に取り組みます。ここでは、社会と環境、ガバナンスの3つの観点から、取り組みの具体的な内容を紹介します。サステナビリティ経営で取り組む必要がある施策
- 環境への取り組み
- 社会への取り組み
- ガバナンスへの取り組み
環境への取り組み
サステナビリティ経営を行うにあたり、「環境」の観点では例えば、以下のような取り組みが挙げられます。環境への取り組みの例
- 温室効果ガスの排出量削減
- 再生可能エネルギーの利用
- 資源の有効活用
- 廃棄物の削減
- 環境に配慮した製品の開発や提供
なお、JMAホールディングスグループが日本国内の企業を対象に2023年に実施した調査では、「ステークホルダーに対して、開示している項目」(複数回答)という設問で、74.3%の企業が「環境負荷対応状況(製品ライフサイクル、再生可能原料、省エネなど)」と回答しました。このことから、サステナビリティ経営を行っている多くの企業が環境負荷への対応に取り組んでいることがわかります。
(参照:『JMAホールディングスグループ 4社合同調査―『サステナビリティ経営課題実態調査2023』速報-』)
社会への取り組み
サステナビリティ経営を目指すのであれば、自社の事業活動が社会に与える影響を考慮し、より良い社会を実現するための取り組みも行うことが必要です。具体例は以下をご覧ください。社会への取り組みの例
- 人権の尊重
- 多様性の推進
- 労働環境の改善
- 地域社会への貢献
- 顧客満足度の向上
- 製品・サービスの品質管理
ステークホルダーに対して、開示している項目(複数回答)
- ダイバーシティ推進状況(女性管理職比率など):74.3%
- 社会への貢献・関わり(社会貢献活動の内容、頻度、金額など):64.0%
- 品質への取組み状況(品質への意識、推進活動など):46.3%
- 健康経営の推進状況(高ストレス者割合、生活習慣関連指標など):42.6%
- 労働安全衛生管理の状況(度数率、強度率、年千人率など):36.8%
- 顧客エンゲージメントの状況(顧客満足度指標など):16.9%
(出典:『JMAホールディングスグループ 4社合同調査―『サステナビリティ経営課題実態調査2023』速報-』)
ガバナンスへの取り組み
ガバナンスの観点も、サステナビリティ経営に求められています。これは、ガバナンスを意識することにより企業の意思決定や経営の透明性を確保できるためです。サステナビリティ経営に求められるガバナンスに関する取り組みとしては、以下の例が挙げられます。
ガバナンスへの取り組みの例
- 取締役会の多様性および独立性の確保
- リスクマネジメント体制の強化
- コンプライアンスの徹底
- 適切な情報開示
- 企業倫理の確立
ステークホルダーに対して、開示している項目(複数回答)
- 取締役会の健全な機能発揮状況(取締役会の実効性評価など):61.0%
- コンプライアンスの徹底状況(コンプライアンス意識指標など):43.4%
- 公正な取引、人権尊重や腐敗防止の推進状況(取引先からの評価など):28.7%
(出典:『JMAホールディングスグループ 4社合同調査―『サステナビリティ経営課題実態調査2023』速報-』)
ステップ3:情報開示とステークホルダーへの共有
サステナビリティ経営は、一度取り組んで終わるものではありません。自社が行った取り組みを内外に広く知ってもらうことが大切なので、定期的に公表しましょう。株主総会や顧客向けのリリースはもちろん、ホームページやSNSなども活用して、より多くのステークホルダーに情報を届けることをお勧めします。取り組みを適切に発信することで信頼が高まり、より良い企業活動へとつながることが期待できます。
サステナビリティ経営は、ステークホルダーへの報告まで行うことが大切
サステナビリティ経営に必要な取り組みにはさまざまなものがありますが、どれを選ぶ場合でも、ステークホルダーへの報告が必要です。持続可能な地球環境や社会の実現のため、自社が取り組めることを考え、適切に報告を行っていきましょう。
サステナビリティ経営に関してお悩みの管理者や経営者の方は、「HiPro Biz」へのご相談を検討ください。ガバナンスの専門知識を有しているプロ人材が、課題を解決に導きます。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)




