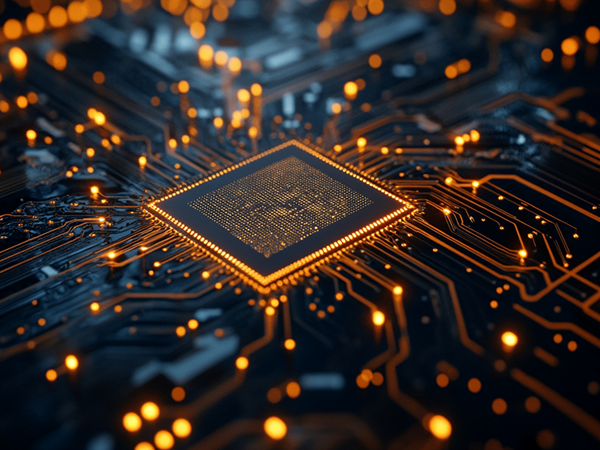製造業に求められる「サービタイゼーション」。 企業価値創出につなげるサービス開発の基本フロー&ポイントとは?
2025年10月29日(水)掲載
- キーワード:
モノがあふれ、技術の進化がさらに早まる中、製造業において製品(プロダクト)単体の価値だけで競争力を保つことがますます難しい時代になっています。 企業価値を高め、顧客から選ばれるためには、競争力強化が求められます。競争力強化のためには、製品を売り切るだけのビジネスから、製品にサービス要素を加えた「新たな顧客価値」を創出するビジネスモデルへの転換、すなわち「サービタイゼーション」の実現が一つのカギになります。
本記事では、新規事業プロジェクトなどを数多く支援するプロ人材、白神 敬太氏にお伺いし、製造業におけるサービタイゼーションの現状と課題、実践のポイントなどについて解説していただきました。
製造業で高まる「サービタイゼーション」の声
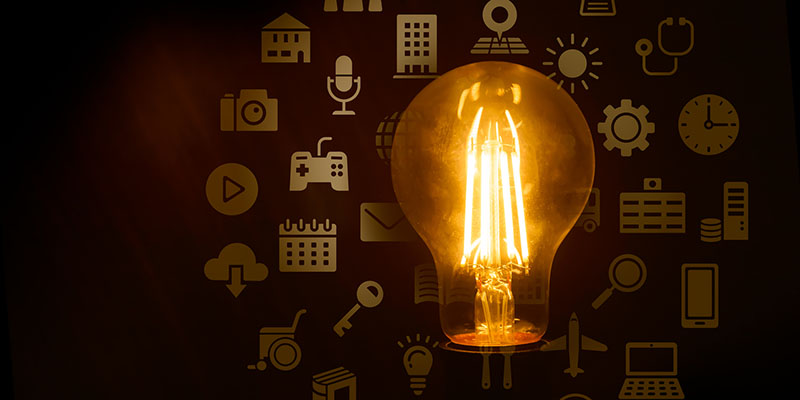
―― そもそも製造業における「サービタイゼーション」とは、どのようなビジネスモデルを示しているのでしょうか?
白神氏:一言で言えば、製品売り切りのみの事業から脱却するためのビジネスモデルです。多くの製造業は有形商材の売り切りが一番コアな事業である一方、「製品+サービス」で顧客に新たな価値を提供するビジネスを考えていこうという発想が「サービタイゼーション」です。
製品に付加する、あるいは製品と統合させるサービスには、保守メンテナンス、カスタマイズやパーソナライズ、コンサルティング、遠隔管理などがあり、また関連するソフトウエアやアプリケーションなどの無形商材も広義でサービス事業としてとらえることができます。こうしたサービス商材をサブスクリプション型や従量課金型などで提供し、利用継続型のビジネス(リカーリング)へと転換させている企業が増えています。
ただ、サービタイゼーションの定義付けや手法は実に多様で、正解は一つではありません。そのため「サービタイゼーションの重要性はなんとなくわかるが、具体的にはどうすればよいのか」という声が製造業の現場で高まりつつあります。
正解は一つではない中で私が唯一、重要視するのは、サービタイゼーションはあくまでも手段であって目的ではないということです。 サービタイゼーションは、「顧客価値の最大化(ひいては企業価値の最大化)」を狙うものであるため、サービスありきで考えると迷走してしまいます。顧客にとって真の恩恵になることは何か、さらに社会に貢献できることは何か、そのような視点から新しい商材や仕組みを考えていくことが重要です。
―― 「サービタイゼーション」への注目度が高まる中、その背景についても教えてください。
白神氏:背景にある一番の要因は、ネットワーク技術の変革です。ネットワーク、IoTによってさまざまな製品がインターネットにつながるようになったこと、データや情報に価値が生まれ、商材として提供できるようになったことが大きいと考えます。またサービスに対する課金など購入手段がネットワーク経由でできるようになったことなども、サービタイゼーションの波を引き起こしている一因といえるでしょう。
もちろん、多くの製品がコモディティ化し、製品そのものだけでは差別化しにくく、競争力を失いつつあるという環境変化も大きな要因です。その意味では、保守や技術コンサルティング、カスタマイズなど、製品に付随するところで差別化して販売につなげるサービタイゼーションは「ソリューション型」とも呼ばれ、以前からBtoBシステムを提供する企業などで行われている手法です。近年は、さらに進んだ形のXaaS(コンピュータ資源やさまざまなサービスをインターネット経由で提供するクラウドサービスの総称。ソフトウエアを提供するSaaS、プラットフォームを提供するPaaSなどもある)への関心が高まり、製造業においてもここへの参入企業が増加傾向にあります。
サービタイゼーション実践時、現場で起こりえるリアルな課題感
―― サービタイゼーションに関する支援依頼の状況はいかがでしょうか。現場の状況や課題感について教えてください。
白神氏:支援依頼は増えていますね。大手企業の新規事業や新商品開発プロジェクト支援にまつわるご相談の多くが、まさにサービタイゼーションの領域です。製品自体の企画は自社で推進できるものの、この領域については経営層も現場も具体的にどう進めていったらわからない、といった相談が顕著に感じます。 一方、中小規模の企業の場合は、製品開発の支援から入り、製品だけに留まらないサービスも一緒に考えましょうとこちらから提案することも多々あります。
たとえば、製品だけの企画ではどうしても事業規模が小さく、事業化そのものが見送りになりそうだったプロジェクトに対し、周辺アプリケーションやサービスを併せて検討し、事業企画が承認されるところまで伴走支援したケースもあります。また別のケースでは、社内向けの技術を顧客に有償で提供するサービス事業の立ち上げを支援したこともあります。
まずは小さなスタートですが、これまで製品の売り切りしかなかった企業がサービス事業を具体的に始めることで、それが前例となり、次回以降の新企画へとつなげることができます。この「ゼロからイチ」への取り組みがとても重要になってきます。
いずれにしても、経営層がサービタイゼーションを経営課題としてとらえていても、実際にどう実現するかは、経営層も現場担当者もわからないケースが多々あります。それぞれの企業の製品や技術を要素分解し、具体化して初めて見えてくるものですから、その過程を企業ごと、ケースごとに沿ってご支援することを心がけています。
―― サービタイゼーションを実行するにあたり、難航する点や陥りやすいリスクにはどういったものが考えられるでしょうか?
白神氏:まずは自社が保有する技術やノウハウなど自社の資産を洗い出していきますが、本来は高い技術力を持ちながらも、社内の人たちは当たり前の技術やノウハウだと認知しているため、価値を見いだせずに難航する場合がよくあります。 こうしたケースにおいては、客観的視点が重要となるため、顧客やパートナー企業へのヒアリングや外部の人材が関わるなどして進めるのが有効でしょう。
また陥りやすい穴として考えられるのは、たとえばサブスクリプションなどマネタイズの方法ありきで着手してしまうことが挙げられます。サービタイゼーションはあくまでも手段なので、それが目的化してしまうと、最も重要な顧客視点、社会視点を見失いがちとなり、結果、製品とサービスを統合した「価値の創出」に至りにくくなってしまいます。
もう一つ重要なのは、中長期視点に立ち戦略的に考えられているか、という点です。サービタイゼーションによる新事業の開始時、当初は一時的に売上が下降することがあります。これは有形商材を売り切る事業と売上の立ち方が違うためであることが考えられますが、この時期を乗り越えるためには、中長期的な経営判断が必要です。 そのためにもサービタイゼーションを目指す場合は、本体の事業に影響を与えないように計画を立てながら、管理部門、営業部門など必要な関連部門としっかり連携をとっておくことが一つのポイントになります。
―― ときには総合的な経営判断からサービタイゼーションを見送る場合もあるのでしょうか?
白神氏:はい、もちろんあります。サービタイゼーションを目指して多角的に検討した結果、最終的に「当面、我々は製品だけでやっていく」と企業側で結論が出る場合もあります。だからといって、サービタイゼーションを検討したこと自体が無駄になるというわけではありません。
現時点で、プロダクトオンリーでやっていくことが自社にとって最適解だと判明したこと自体、十分な成果だと言えるでしょう。将来的にサービタイゼーションを再検討する際にも、一度プロジェクトが立ち上がった実績があれば、蓄積されたノウハウや知見を積極的に活かせるでしょうから。
サービタイゼーションを検討する際に押さえておきたい実践ポイント
―― サービタイゼーションを具体的に検討する際の主な流れと押さえておきたい実践ポイントについて教えてください。
白神氏:サービタイゼーションの主な検討フローは、大きく4つのステップに分かれます。BtoB、BtoCともにこの考え方は共通します。
1.既存製品の要素分解と価値定義
最初に「製品の価値や機能 」、「自社の技術やノウハウ」を細分化し、それぞれに価値づけを実施します。たとえば開発段階の評価技術やアフターメンテナンスのノウハウであれば、それを客観的に評価することで、実は非常に高い市場価値を持っている場合も考えられます。
また顧客が製品、あるいは自社の事業に対してどんな本質的価値を期待しているかを定義し、それを抽象化していきます。たとえば、エアコンが提供する価値は、エアコンの機械そのものではなく、外気温に左右されない「快適な空間」です。製品自体にとどまらず、顧客に役立つ価値としてどんなものを提供するか定義します。
2.未来創造
次に「自分たちが創りたい未来」はどのようなものかを考える過程です。自社事業やコア技術がどう進化するか、周辺技術や環境がどう変化するか、顧客や社会の要求がどう変化するかといった予想を踏まえて「自分たちが創りたい未来」を描きます。
3.価値創出とロードマップ
ステップ1と2を組み合わせ、サービスと製品を統合する具体的なアイデアを出していきます。自社として顧客や社会に何を提供できるのか、という視点を持つのですが、ここで重要なのは時間軸を複数に分けて発想することです。
「次世代(直近で実現できそうなもの)」、「次々世代(中長期的に実現しそうなもの)」、「未来展望(考えられる究極の形態)」のように時間軸を分けることで、アイデアを整理していくことができます。このステップをきちんと実施しないと具体案になりきらず、あやふやなまま終わってしまいがちですから、丁寧に進めたい過程です。 次に、直近で実現可能な「次世代」のアイデアを起点とした具体案のロードマップを引きます。できれば並行して「次々世代」以降のアイデアについても計画化しておくことをおすすめします。
4.商品化計画
最後に、ステップ3までの作業を踏まえ、次世代サービスの事業化計画を作成します。具体的なサービスの仕様、顧客への提供手段、課金方法などを定義して開発計画、そして導入計画を立てます。
ここまでサービタイゼーションの検討フローについて説明してきましたが、重要なポイントは3つあります。
1つ目は、1~4のステップを順番に進める必要はないということです。できるところから検討し、1~4のステップを行ったり来たりすることで全体像を浮かび上がらせていきます。
2つ目は、ベクトルを自分たちだけ(事業拡大を目的化するなど)に向けず、常に顧客視点を持って考えることです。その姿勢を崩さずにストーリーを組み上げ、さらにそのストーリーに「自分たちの技術でこんな世の中を創りたい」という社会的視点が加われば、より理想的な形にまとまっていくでしょう。
3つ目は、「正解」を市場に求めてはいけないということ。冒頭でも申し上げましたが、「正解」は個々の企業、事業によって異なります。顧客や市場を観察し探れるのは課題に対するヒントのみで、顧客や市場は答えそのものを持っていません。だからこそ、「正解」を自分たちで創り出そうとする姿勢が重要です。
―― 顧客や社会に目を向け、正解を創り出そうとするスタンスが大事なのですね。最後にサービタイゼーションにこれから取り組む方々へメッセージをお願いします。
白神氏:サービタイゼーションは、大手企業にとって高い競争力を保つために今や欠かせない経営課題です。また中小規模の企業においても、今後ネットワークや情報技術がさらに発展していく中で、サービタイゼーションを検討することは自社の持つポテンシャルを掘り起こす重要な機会になると思います。
社運をかけて大きくスタートさせることもよいですが、まずはリスクを最小化しながら小さく始め、サービス事業のノウハウや仕組みを構築してみてはいかがでしょうか。自社に埋もれている価値はきっとまだまだあるはず。ぜひチャレンジしてみてください。
【プロフィール】
■株式会社プリミス代表取締役
新規事業・商品開発プロジェクトチームコーチ 白神 敬太氏
大手家電メーカーにて約25年商品企画、新規事業開発に携わる。その経験をもっと社会に役立てたいと在職中より企画コンサルタントを開始。その後コーチングを学び、支援スタイルをコーチング型に変更。2020年株式会社プリミスを設立。大手企業から中小企業まで、新規事業、商品開発チームをコーチングで伴走支援している。銀座コーチングスクール チームコーチング講座講師、国際コーチング連盟プロフェッショナル認定コーチ。
まとめ
製造業にとって「サービタイゼーション」は、自社が持つ価値をさらに高めていくための有効な方法の一つです。また、設備投資など巨額の投資を行うことなく、小規模からスタートできることも企業にとって大きな魅力となるのではないでしょうか。
自社の価値を最大化するために、提供している「真の価値」は何なのか、その価値をさらに高めるためにはどうしたらよいのか。この機会に考えてみてはいかがでしょうか。 「HiPro Biz」には白神氏をはじめ、サービタイゼーションや新規事業開発領域におけるプロ人材も多数登録しています。豊富な知見や経験と客観的視点を併せ持つプロ人材の力を上手に活用し、サービタイゼーションのプロジェクトをより有意義なものにしていただければと思います。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)