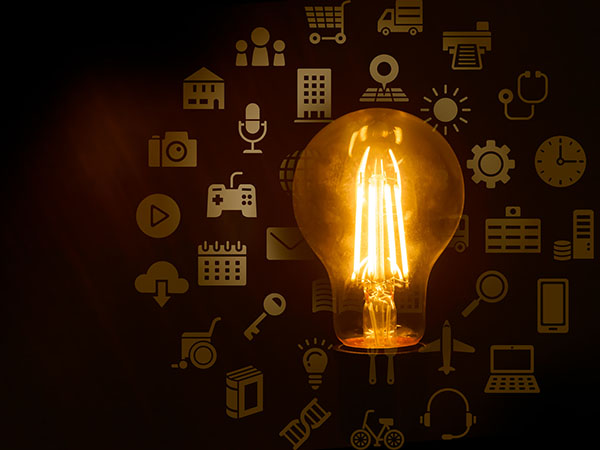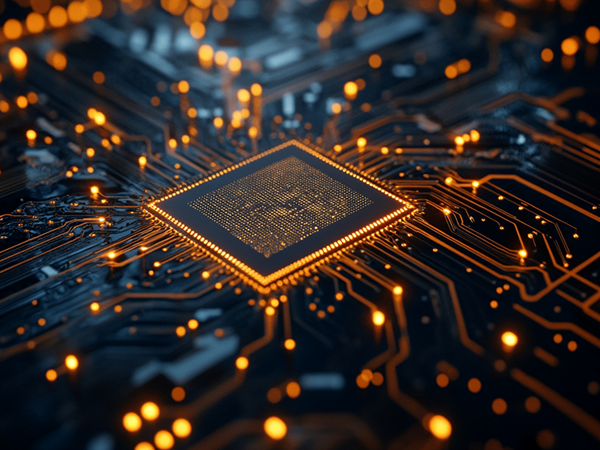【半導体のエキスパートに聞く】日本の半導体は再び世界を獲れるか?カギを握るイノベーション戦略
2025年08月28日(木)掲載
AI需要の急拡大に伴い、先端半導体市場は飛躍的な成長を続けています。海外企業が市場を牽引する一方、かつて世界一の技術力を誇った日本企業は遅れを取っている状況です。
昨今、日本では国家戦略のもと2ナノメートル(nm)のチップ開発(ナノメートル=10億分の1メートル。性能向上と省電力化が期待される極めて微細な次世代のチップ)に挑んでいますが、半導体に関連する日本企業は果たして半導体業界で勝機をつかむことができるのでしょうか。
国内の大手電機メーカーで40年以上デバイス開発に携わり、現在は大阪公立大で研究する傍ら量子超加工ラボを主宰する笹子 勝氏は、そのカギを「コア技術を磨くことと事業モデルの転換」と指摘します。次世代のコア・テクノロジーを日本企業はどのように扱い、どう戦っていくべきなのでしょうか。
▼関連資料はこちら
日本の半導体業界の再起戦略 技術優位性とXaaS型への変革の道
■「活用する」視点の欠如が招いた日本企業の低迷と一筋の勝機
■「唯一無二の技術」と「XaaSへの転換」――イノベーションを起こす組織改革
■新たな需要を見据え、世界の最先端を知ることから改革を始める
■まとめ
「活用する」視点の欠如が招いた日本企業の低迷と一筋の勝機
![]()
――半導体業界の市況感と日本企業の立ち位置について、どのように見ていますか。
笹子氏:前提として、半導体業界には材料をつくり、製造装置を開発し、そのうえで半導体を製造するというプロセスがあります。日本企業は20〜30年前、半導体製造と共に、そのリーディングにより特に材料・装置分野で半導体関連メーカーが高い技術力を誇り、その結果、世界一の半導体を製造するポテンシャルがありました。
しかし、現在、最先端半導体を活用する国内プレーヤーが存在しません。半導体は「産業の米」と例えられますが、残念ながら日本には、その米を使って料理(=製品やサービス)をつくれる人材や企業が乏しい状況です。
現状、半導体の活用においてはAI用GPUのトップシェアを誇る海外の大手GPUメーカーや、独自AIチップを開発する米国の巨大テック企業が激しい市場競争を繰り広げており、製造においても海外企業が市場において大きなシェアを占めています。かつて半導体市場で存在感を示していた日本企業群は、いまや影響力をほとんど持たないのが実情です。
こうした市況を踏まえると、半導体業界における日本企業の成功は容易ではないというのが率直な印象です。
――技術進化の観点で、日本企業に勝機はあるのでしょうか。
笹子氏:グローバルの市場競争では遅れを取っていますが、かつて半導体産業をリードした日本企業の技術力とモノづくり力は依然として健在です。半導体製造のチョークポイント(供給が止まると世界全体が止まる急所)となる材料・製造装置のメーカーとして、日本が世界トップクラスの技術を持っていることは、明確な強みです。
現在、半導体製造の進化において「3次元化」という大きな技術的変化点が訪れています。従来は小さな面積に多くを詰め込む微細化が中心でしたが、物理的限界が近づく中で、平面ではなく上下に積み重ねる3次元構造が注目されています。最先端チップにもこの技術の適用が進みつつあり、AI用GPUだけでなくスマートフォンの一部にも既に採用されています。
この3次元化では、製造時に生じるパーティクルと呼ばれる微細な異物を取り除き、半導体を“きれい”に作る技術が不可欠です。これは単に外観が整った製品という意味ではなく、製品内部に異物が一切混入しない“クリーン”な状態を保つことを指します。パーティクルは微粒子の混入リスクを高めるため、製造不良の原因となります。再加工や廃棄といった問題を引き起こすリスクを高めることを考えると、製品の信頼性や性能に直結する重要な技術といえるでしょう。そして、これは日本企業がもともと得意とする分野であり、各社のコア技術を活かせば競争力を発揮できる可能性があります。
「唯一無二の技術」と「XaaSへの転換」――イノベーションを起こす組織改革
![]()
――半導体市場に挑む日本企業は、何を意識すべきでしょうか。
笹子氏:重視すべき条件は二つあります。
一つ目は「唯一無二の技術」を持つことです。日本のメーカーは世界で戦える技術力を持ちながら、さまざまな分野で技術流出によって主役の座を他国に奪われてきました。誰にも模倣できないコア技術を持てると、従来の製品販売型ビジネスでも十分戦えます。
二つ目は、製品を売り切るビジネスモデルから脱却し、「XaaS(Everything as a Service)」型のモデルに転換することです。GAFAMをはじめとするビッグテックが急成長しているのは、サービス(データ)を継続的に提供して定期収入を得るモデルを土台としているからです。
多くの日本企業の課題は、高い技術力を活かせるビジネスモデルを持たないことです。現状のままでは海外大手の下流工程を担う立場にとどまり、優れた技術を安く提供してしまう悪循環に陥ります。唯一無二の技術を武器に、継続的利益を上げられる構造へ転換する必要があります。
さらに、SDGsやカーボンニュートラルへの配慮も欠かせません。半導体製造は膨大なエネルギーを消費し、環境負荷も高い産業です。CO2削減への取り組みは、主要顧客であるビッグテック各社が環境対応を重視する今、特にグローバル市場で競争力の一因となります。
――そうしたビジネスモデルの転換には、組織面での変革も必要になりそうです。
笹子氏:イノベーションを生み出せる組織でなければ、難しいでしょう。イノベーションははたらき手一人ひとりが強みや個性を活かし、考え抜くことでしか生まれません。
ポイントは、仕事に没頭できる環境づくりです。仕事が楽しく、時間を忘れるほど没頭できる。そして自分たちの技術が世界に影響を与えていることがモチベーションとなる。経営陣はそうした環境を意識的につくり上げる必要があります。
また、多くの企業は新規事業部を設置しますが、形骸化する例が少なくありません。担当者が気概を持ち、経営者が支援することで初めて真のイノベーションが生まれます。ウェルビーイングを実現しつつ、挑戦を評価しリターンを与える制度や体制が求められます。
さらに、日本企業は能力の高い人材を平均化する傾向がありますが、「異能人材」こそがイノベーションの核となります。そうした人材を活かす評価基準や育成方針を取り入れるべきです。
新たな需要を見据え、世界の最先端を知ることから改革を始める
――今後の半導体業界のトレンドをどう見ていますか。
笹子氏:一つはメタバースです。現状はスマートフォンが生活を支える主要デバイスですが、メタバースの浸透とAI技術の融合により、人々は手元のデバイスに依存せず、あらゆる情報を得られるようになるでしょう。例えばスマートグラスを装着して歩行中に「5秒後に転倒の恐れがあります」といった警告を受けられる世界は、そう遠くありません。
もう一つはヒューマノイドロボットです。現在は工場・物流現場や店舗接客での活用が進んでいますが、今後は生活領域にも導入が広がるはずです。特に高齢者の介護や家事支援では大きな役割を果たすでしょう。
これらを支えるのはAIであり、それに伴い半導体需要も拡大します。ただし、AIチップは電力消費が非常に大きく、今後は消費電力削減が重要な課題となります。この分野で日本企業がコア技術を活かしてイノベーションを起こせれば、世界市場での活躍の余地は十分あります。
――半導体関連の事業展開に挑む経営層の方に向けて、今後どのようなマインドで半導体市場に参入すべきか教えてください。
笹子氏:「半導体は成長分野らしい」という漠然とした意識で参入しても、成功は望めません。競争の激しい市場で日本企業が存在感を示すには、自社のコア技術を唯一無二のものとして磨き上げ、半導体分野にどう応用するかを真剣に考える必要があります。
さらに、事業モデルや組織構造など根本的な部分から見直し、改革に挑む姿勢が求められます。“尖った”人材に光を当て、心から仕事を楽しめる環境を提供することで、イノベーションを生み出す企業を目指してください。
そのための第一歩として、世界の最新技術や知見に直接触れる機会を設けてほしいと思います。グローバルな展示会や技術カンファレンスに足を運ぶことは、イノベーションのヒントとなり、挑戦へのモチベーションにもつながります。
<プロフィール>
量子超加工ラボ代表 笹子 勝(ささご・まさる)
パナソニック(旧松下電器産業)で40年以上のキャリアを持つデバイス・半導体技術のエキスパート。パナソニック半導体社では部長職として最先端半導体プロセス(90nm〜28nm)の開発から量産化までを16年間担当。その後、新規デバイス開発センター所長として、半導体からMEMSセンサー、電池まで幅広いデバイス開発とオープンイノベーション構築を手がける。技術顧問を務める傍ら、2021年に個人事業「量子超加工ラボ」を立ち上げ。基礎研究から量産化、新規事業創出、人材育成まで幅広く支援している。大阪公立大学 工学研究科客員教授。
まとめ
半導体業界は技術革新のスピードが速く、グローバル競争が激化する厳しい市場です。しかし、日本企業には装置・材料分野での優位性と、これから重要性を増す3次元化技術への対応力があります。重要なのは唯一無二の技術を活かしたXaaS型ビジネスの構築と、それを実現するためのイノベーションが生まれる組織・環境づくりです。
「HiPro Biz」では、こうした技術革新とビジネスモデル転換に精通したプロ人材が多数登録しています。限られたリソースの中でスピード感をもって変革を進めるために、「HiPro Biz」のサービス活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)