リテンション施策とは?休眠顧客を掘り起こすマーケティング施策を解説
2025年08月26日(火)掲載
- キーワード:
マーケティングでは、新規顧客の獲得はもちろん、既存顧客との関係性の維持にも意識を向ける必要があります。特に、新規顧客の獲得が困難となっている業界では後者が非常に重要です。
そこで本記事では、既存顧客との関係性を考えるにあたって重要な「リテンション施策」について、具体的な施策内容や成功のポイントを解説します。
マーケティング施策に手詰まりを感じている管理者や経営者はご覧ください。
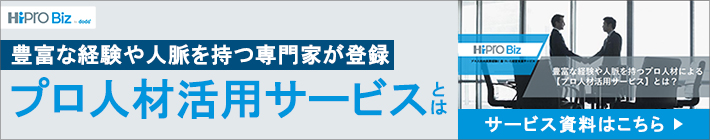
■リテンション施策とは
■リテンションマーケティングが重要な理由
■リテンションマーケティングを行うメリット
■リテンションマーケティングで見るべき指標
■リテンションマーケティングの具体的な施策
■リテンションマーケティングを成功させるためのポイント
■リテンションマーケティングを実施し、既存顧客との関係性を維持することでLTVが向上する
リテンション施策とは
「リテンション(Retention)」は、維持や保持を意味する言葉です。「リテンション施策」はマーケティングだけでなく人事の場でも使われており、いずれも対象との関係性の維持や保持を目的としています。
マーケティングと人事、どちらの場合もリテンション施策という言葉の根本的な考え方は非常に近いですが、具体的な内容が異なるので、まずは両者の違いを把握しましょう。
- 人事でのリテンション
- マーケティングでのリテンション
人事でのリテンション
人事領域のリテンション施策で企業が関係性を保持および維持する対象は、顧客ではなく従業員です。人事でのリテンションは、自社で活躍している従業員が長く定着するように行う施策を指します。
例えば、給与や福利厚生の改善や、働きやすい環境づくり、職場での良好な人間関係の構築などが挙げられます。近年は転職希望者よりも求人数が多い「売り手市場」が続いている状況のため、リテンション施策が非常に重要なのです。
マーケティングでのリテンション
マーケティングの場での「リテンション施策」は、既存顧客との関係性を維持するための施策を指しており、「リテンションマーケティング」と呼ばれることもあります。
多くの顧客が求めている製品やサービスを訴求し、既存顧客をリピーターに育成することで、売上や生涯価値の最大化を図る手法です。見込み顧客を顧客に育成する「リードナーチャリング」を実施したあとに行います。
リテンションマーケティングが重要な理由
なぜ、リテンションマーケティングが重要なのかというと、市場にいる新規顧客の数は限られており、獲得に限界があるためです。そして、新規顧客の獲得にはコストがかかるという点からも、既存顧客にアプローチするリテンションマーケティングが重要だといえます。
マーケティング分野では、「新規顧客の獲得には、既存顧客の維持に比べて約5倍のコストがかかる」と言われています。これは「1:5の法則」と呼ばれ、リテンション施策の重要性を示す考え方の一つです。
リテンションマーケティングを行うメリット
リテンションマーケティングを実施することで既存顧客との関係性を維持できるようになりますが、それによって具体的にどのようなメリットがもたらされるのでしょうか。ここでは、4つのメリットを紹介します。
- LTVの向上につながる
- 売上の貢献性や費用対効果が高い
- 休眠顧客や離反顧客の掘り起こしができる
- 顧客ロイヤルティの向上による、新規顧客の獲得につながる
LTVの向上につながる
「顧客生涯価値」、つまり顧客が企業にもたらす利益を意味するLTV(Life Time Value)は、マーケティングを考える上で重要な指標です。リテンションマーケティングを実施することで、このLTVを高められます。
ECサイトを一例に挙げると、「この商品を購入する方にはこちらもお勧め」と、別の商品をレコメンドした場合、クロスセル(合わせ買い)につなげられる可能性があります。この積み重ねによって、LTVを高められるのです。
ほかにキャンペーン情報の配信や会員限定クーポンの配布などの施策によっても、同様にLTVの向上が期待できるでしょう。
売上の貢献性や費用対効果が高い
リテンションマーケティングは、新規顧客の獲得よりも費用対効果が高いというメリットもあります。
新規顧客のほうが既存顧客よりも5倍のコストがかかる旨は、先述の通りです。新規顧客に対しては自社の商品やサービスを認知してもらうところから始める必要がありますが、既存顧客では認知のフローを省ける点がその理由として挙げられます。
「売上をつくる」という結果は同じでも、コストがかからないほうが費用対効果は高いため、その点でリテンションマーケティングには大きなメリットがあるといえます。
休眠顧客や離反顧客の掘り起こしができる
リテンションマーケティングを行うことで、休眠顧客(離反顧客)を掘り起こして優良顧客に育成できる可能性があります。
休眠顧客は、過去に自社の商品やサービスを利用したことがあるにもかかわらず、現在は関係性が途切れている顧客です。そこで「なぜ、購入や利用をやめてしまったのか」を分析し、適切なアプローチを行えば、商品やサービスへの意欲を再度高められます。
顧客ロイヤルティの向上が、新規顧客の獲得につながる
リテンションマーケティングは既存顧客にアプローチする施策ですが、新規顧客の獲得への寄与にも期待できます。
なぜなら、リテンションマーケティングの実施により顧客ロイヤルティが向上することで、既存顧客が周囲に商品やサービスを紹介する場合があるためです。また、直接紹介しなくとも、インターネット上にポジティブな口コミを投稿することで、それが潜在顧客の目に留まり、新たな利用や購入につながることも考えられます。
リテンションマーケティングで見るべき指標
リテンションマーケティングを実施する際は、以下の2つの指標を定期的に確認してPDCAサイクルを回すことで、施策の効果を高められます。
- リテンションレート
- ユニットエコノミクス
リテンションレート
リテンションレート(既存顧客維持率)は、リテンションマーケティングの成果を測る指標です。以下の公式で算出できます。
リテンションレート(%)=(対象期間終了時点の顧客数-対象期間中に増えた新規顧客数)÷ 対象期間開始時点の顧客数 × 100
例えば、対象期間を4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、期間開始時点(4月1日)で既存顧客が10,000人、期間中に増加した新規顧客が3,000人、期間終了時点(翌年3月31日)の顧客数が11,000人の場合、以下の計算でリテンションレートを求められます。
(11,000人-3,000人)÷ 10,000人 × 100 = 80%
より簡略して、以下の計算式で求める方法もあります。
リテンションレート(%)= 継続顧客数 ÷新規顧客数× 100
仮に先月に60人の新規顧客を獲得し、今月はそのうちの25人が商品を再度購入した場合、リテンションレートは約41.6%ということになります。この数値が高ければ高いほど、リテンションマーケティングに成功しているということです。
あらかじめ現時点でのリテンションレートを把握し、その後施策によってどのような変化が表れたのかを観測していくことで、施策の成功を判断できます。
ユニットエコノミクス
LTV(顧客生涯価値)とCAC(顧客獲得単価)を組み合わせて、顧客1人当たりの採算性を測る指標が、ユニットエコノミクスです。なぜユニットエコノミクスを把握する必要があるのかというと、リテンションレートが向上したとしても、LTVが下がったりCACが高くなったりしてしまうと、健全な事業活動が難しくなるためです。
ユニットエコノミクス、およびその算出に必要な数値を計算する際は、以下の公式を用いましょう。
LTVの計算式
LTV=平均購買単価×平均購買頻度×平均継続期間
SaaSなどのサブスクリプション型ビジネスの場合は、以下の計算式でLTVを求めることができます。
LTV=平均購買単価÷チャーンレート(解約率)
CACの計算式
CAC=すべての顧客獲得コスト÷新規顧客数
ユニットエコノミクスの計算式
ユニットエコノミクス=LTV÷CAC
例えば、1人の顧客の生み出す利益、つまりLTVが30万円で、1人の顧客を獲得するコストであるCACが4万円の場合、ユニットエコノミクスは7.5です。
リテンションマーケティングの具体的な施策
リテンションマーケティングで実施する施策の内容は、商品やサービスがBtoBとBtoCどちらなのかによって異なります。
- BtoBに有効な施策
- BtoCに有効な施策
BtoBに有効な施策
BtoBの商品やサービスでリテンションマーケティングを実施する際は、以下の施策が有効です。
- メルマガ
- カスタマーサクセス
- 導入事例コンテンツの作成
- 各種ツールの導入
メルマガ
メルマガの配信は、メールを通じてユーザーにアプローチし、商品やサービスに興味を持ってもらう施策です。多くのユーザーに一括でリーチが可能な上、既存顧客との接点を簡単につくれるため、効率的にリテンションを実施できます。
なお、メルマガの成果を挙げるには、メールの件名や内容などでターゲットの属性ごとに適切なアプローチを使い分けることが求められます。
具体例は以下をご覧ください。
| ターゲット | 訴求内容の例 |
|---|---|
| マーケティング担当者 | 「リード獲得の進捗が悪い…」とお悩みの方、必見! |
| 経営者 | 【2025年最新】○○業界のトレンドと市場予測 |
上記のように、現場の担当者に対しては、多くの既存顧客が抱えているであろう悩みに寄り添う内容を訴求します。経営者などの決裁権者に対しては、高レベルな情報を提供することで、アップセルやクロスセルの機会を早期に発見してもらえる可能性があります。
カスタマーサクセス
企業が能動的にはたらきかけ、顧客を支援する「カスタマーサクセス」もリテンションマーケティングで有効な手法です。具体的には、以下のようなサポートが挙げられます。
- 導入初期段階でもスムーズに商品を利用してもらうために、手厚いサポートを提供する
- 顧客の利用状況を定期的に確認し、適切な活用方法や別の製品を提案する
BtoBの商品やサービスでは、企業が能動的にコミュニケーションを取り、顧客に成功体験を実現させることで、継続利用によるLTVの向上、およびアップセルやクロスセルを促進できます。特に、商品やサービスを一定期間利用している顧客や、契約更新時期が近付いている顧客に有効です。
導入事例コンテンツの作成
既存顧客にインタビューを実施し、商品やサービスの導入事例コンテンツをWeb上で公開する方法もリテンションマーケティングの一つとして挙げられます。導入事例コンテンツは通常、見込み顧客へのアプローチのために作成するものですが、既存顧客との関係性維持にも有効なのです。
その理由は、インタビューという「自社対顧客」のコミュニケーションを設けることで両者の間に強固なパートナーシップが生まれ、長期的な関係性の維持につながるためです。また、インタビューの場で新たな課題が見つかれば、活用方法のアドバイスや、課題を解決するために別の商品の提案によるアップセルも可能となります。
さらに、導入事例コンテンツの公開によって、既存顧客のロイヤルティ向上につながることも期待できます。顧客は商品やサービスを通じて得られた成果を改めて認識する機会になるとともに、「自社の成功」を外部に発信することで、商品やサービスに対しての貢献も実感できます。それらによって、商品やサービスへの信頼や愛着が深まり、長期的な利用や自発的に周囲の人へ勧めてくれるなどの効果が期待できるでしょう。
各種ツールの導入
MA(マーケティングオートメーション)やCRM(顧客関係管理)などのツールを導入して顧客情報の管理や分析を行い、属性ごとに適切なアプローチを実施することで、精度の高いリテンションマーケティングを実現できます。
特に、MAとCRMの併用が有効です。例えばECサイトやWebサービスの場合、CRMに蓄積された顧客の属性や購買履歴のデータと、MAで取得したWeb上の行動履歴やメルマガへの反応データを統合します。これにより、顧客一人ひとりの実態をより深く把握でき、パーソナライズされたコミュニケーションを実行できるのです。
例えば、Webサービスで特定の機能の利用頻度が低い顧客に対しては、その機能の活用方法をレクチャーするウェビナーや資料の案内を送るといった施策が挙げられます。
さらに、MAは解約阻止にも活用できます。まずは「ログインが2週間以上ない」「契約更新に関するメールの開封率が低い」など、離反や解約の兆候となる行動パターンをあらかじめ定義しましょう。その上で、一定の値を超えた場合は状況確認のメールや課題解決に役立つコンテンツを配信するように設定します。
この設定が機能すれば、既存顧客が離反するサインをいち早く察知し、関係性を維持するためのアプローチが可能となります。
関連記事:マーケティングオートメーション(MA)とは?必要性やメリットを解説
BtoCに有効な施策
BtoCのリテンションマーケティングで有効な施策は、BtoBの場合と大きく異なります。- SNS
- リテンション広告
- プッシュ通知
- レコメンド機能の追加
- ポイントプログラムの活用
- オフラインイベント
SNS
X(旧Twitter)やInstagramなどを活用し、商品やサービスに関する情報を発信する手法です。継続的に発信することで、顧客満足度が向上するほか、ファンの獲得も期待できます。
既存顧客のみならず、見込み顧客にもリーチできる可能性があるということです。
なお、SNSによって適切なコンテンツが異なります。具体例は以下をご覧ください。
| 内容 | |
|---|---|
| X |
体験型のコンテンツ 例) 漫画アプリの場合:数ページの試し読み 転職サイトの場合:年収診断や適職診断 |
| 新商品の紹介や既存商品の説明、アップデートの情報や活用方法などの紹介 | |
| LINE | お役立ち情報の発信やQ&A対応など、エンゲージメントが高まるコンテンツ |
さらに、自社が扱う商品やサービスによって、最適なSNSも異なります。既存顧客が多く利用しているSNSを選びましょう。
プッシュ通知
スマホアプリを扱っている場合は、ユーザーの画面にメッセージを表示させるプッシュ通知がリテンションマーケティングとして有効です。休眠顧客に対して、キャンペーンやクーポンなどのお得な情報や、新商品を告知するメッセージを送ることで、アプリの再利用を促せます。
スマホアプリは一度ダウンロードすれば、ホーム画面からすぐにアクセスできる手軽さがメリットです。しかし、徐々に利用頻度が減り、そのまま放置してしまうユーザーも一定数います。プッシュ通知を配信すれば、そのような層にアプリのことを思い出してもらえます。
例えば「【最大20%OFF】オンライン限定セール開始!」といったように、コンパクトな文字数でお得感や限定感を演出できると理想的です。
リテンション広告
リテンション広告とは、サービスを一定期間利用していない既存顧客に対して配信できる広告のことです。Webサイトの下部や側面、動画の合間などに流れる広告などがあります。
外部の媒体に表示できる性質上、前述のプッシュ通知をOFFに設定している既存顧客にもアプローチできる点が大きなメリットとして挙げられます。
レコメンド機能の追加
ECサイトおよびアプリであれば、「あなたへのおすすめ」というレコメンド機能を追加するという方法も挙げられます。購買履歴や閲覧履歴、ユーザーの属性などからおすすめの商品やサービスをピックアップすることで、アップセルやクロスセルを促せます。
ユーザーに「自分だけに向けられた情報だ」と感じさせることで、特別感を醸成させ、サービスへのロイヤルティを高められるのです。
また、レコメンド機能を効果的に活用すれば、ECサイトが抱える「カゴ落ち」の課題を解決できる可能性もあります。お勧めの商品を表示させると同時に、ローン払いや分割払いなどの支払い方法も案内すると、支払いの負担で二の足を踏んでいた顧客の背中を押せます。
ポイントプログラムの活用
商品の購入やサービスの利用によってポイントがたまる「ポイントプログラム」もリテンションマーケティングの手法として有効です。たまったポイントを商品購入時の割引や特典の交換などに使えるように仕組みを整えれば、サービスに「お得感」が生まれ、エンゲージメントの向上が期待できます。
また、会員限定のポイントプログラムを用意し、この「お得感」を適切に醸成できれば、ロイヤルティの向上にもつながります。
オフラインイベント
実は、オフラインイベントもリテンションマーケティングに活用できます。新商品の体験会や無料配布などを行って顧客との接点を増やせば、既存顧客による再購入や新規顧客の呼び込みにもつながるのです。
またオフラインイベントの場では、企業と顧客の交流だけでなく、顧客同士の交流も期待できます。顧客間で商品に関するポジティブな情報が交換されれば、クロスセルやアップセルの促進も起こり得るでしょう。
リテンションマーケティングを成功させるためのポイント
ここまでで紹介したリテンションマーケティングの施策を成功させるために、押さえておきたい3つのポイントがあります。
- 顧客の分析を行い、ニーズを深堀する
- 顧客データを管理し、母集団形成をする
- KPIを明確にする
顧客の分析を行い、ニーズを深堀する
上記で紹介したいずれの施策を行う場合でも、顧客分析は欠かせません。まずは「データマイニング」「コホート分析」などの手法を用いて、顧客の現状を把握します。
データマイニングは、収集した顧客情報の中から、顧客の傾向や関連性を見いだす分析手法です。例えば「この機能を利用している顧客は解約率が低い」「この資料をダウンロードした顧客はアップセルにつながりやすい」といった傾向を見つけていきます。
またコホート分析は、一定の条件の下で顧客をグループに分け、時間の経過とともに各グループに見られる変化を追跡する分析手法を指します。例えば、獲得した期間別にグループを分けて分析すると、「この期間に獲得した顧客のグループはLTVが高い」「このグループは施策の効果が顕著に表れている」といった傾向が見えてくるでしょう。
さまざまな分析手法を活用することで「顧客は自社の商品を購入し、その後継続に至るまでの各フェーズで、どのような感情のもと、どのように行動しているのか」を把握できます。また、定量データだけでは見えてこない情報もあるため、インタビューやアンケートを併用して顧客の意見や要望を収集する方法もおすすめです。
顧客の感情や行動が理解できたら、各フェーズで適切な施策を立案していきます。
顧客データを管理し、母集団形成をする
CRMやMAなどの専用ツールを活用することで、リテンションマーケティングの効率と精度を高められます。ツールを用いて、特定の条件に一致する層を絞り込み、その層に重点的にアプローチして母集団を形成することがポイントです。
顧客を絞り込む項目の一例は、以下をご覧ください。
| ツール | 項目 |
|---|---|
| CRM |
・購買履歴(購入頻度、金額、最終購入日) ・商品やサービスの利用状況 ・契約期間 ・属性(業界、役職、性別、年代など) |
| MA |
・Webサイトの閲覧ページ ・ダウンロードした資料 ・メールの開封履歴やクリックの履歴 |
上記を参考に、例えば「当初はサービスの利用頻度が高かったが、最終購入日から2カ月以上経過している顧客」「契約更新まで残り2カ月を切っている決裁者」など、特定の条件に当てはまる顧客を絞り込みます。
KPIを明確にする
施策を実行する前に、必ずKPI(成果指標)を設定しましょう。これにより、施策の成果を適切に評価できるようになります。
KPIの指標としては、本記事前半でお伝えしたリテンションレートやユニットエコノミクスも使えますが、ほかにもさまざまな指標が挙げられます。
例えば、新サービスのローンチにあたり、既存顧客にアプローチする際は以下のような考え方ができるでしょう。
- 既存顧客にメルマガを送って新サービスを紹介する
- サービス紹介ページに遷移し、気になったら問い合わせてもらう
- 商談を行う
- 新サービスを契約してもらう
- メールの送付件数
- メールの開封率
- メール内のリンク経由でのサービス紹介ページへのアクセス数
- メールがきっかけのお問い合わせの件数
- メールからのお問い合わせから受注した件数
このように、メルマガという施策を一つ挙げてもさまざまなKPIがあることがわかります。効果検証まで見据えて適切なKPIを設定することが大切です。
リテンションマーケティングを実施し、既存顧客との関係性を維持することでLTVが向上する
今回は、リテンションマーケティングについて解説しました。「既存顧客との関係性維持」を意味するリテンションマーケティングを適切に実施することで、LTVの向上をはじめとするメリットを享受できます。
新規顧客の獲得に限界を感じている場合は、リテンションマーケティングを検討しましょう。
なお、マーケティング施策にお悩みであれば、「HiPro Biz」にご相談ください。マーケティングの実績豊富なプロ人材が貴社の課題解決を支援します。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)




