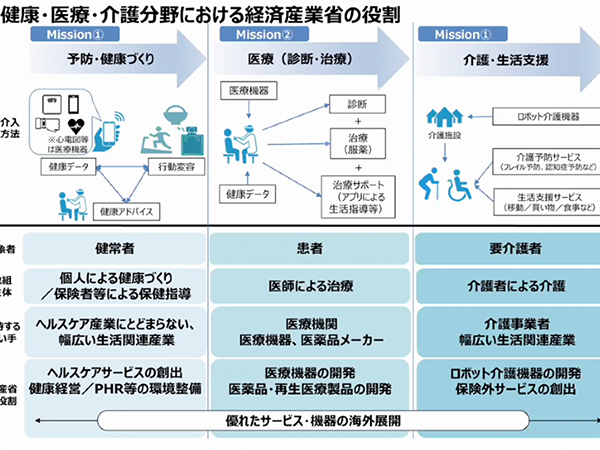【デジタル活用による新規事業創出】メディカル業界が取り組むべき「生成AI活用」「コーポレートベンチャリング戦略」の道とは
2025年07月22日(火)掲載
- キーワード:
近年、医療分野におけるデジタルトランスフォーメーション(医療DX)の重要性が高まっています。とりわけ、個人の遺伝情報や生活習慣などに基づいた「個別化医療」の実現は、一人ひとりに最適化された効率的な診断・治療を可能にし、社会全体の医療の質と持続性を左右するカギとなるでしょう。
海外では国主導の取り組みが先行し、AIや医療データの活用を軸に急速な進化を遂げている一方で、日本国内では制度面やインフラ面での課題が数多く残されている現状も見受けられます。行政官として医療DXを推進した経験を持ち、現在は大学やスタートアップを横断して新規事業開発を支援する医師・医学博士・MBA保有のプロ人材・髙﨑洋介氏は、「M&Aなどの手段も含めて企業が積極的に新規事業へ取り組む必要がある」と指摘します。
医療に携わる企業は、いま何を考え、どのように成長戦略を描くべきなのでしょうか。医療DXがもたらす変化の本質と、求められる新規事業のあり方について伺いました。
■医療DXの課題は「データの標準化と共有」と「国民の理解」
■海外では「生成AIを活用した創薬」などの新規事業が加速している
■避けては通れない新規事業。「どれだけ早く動けるか」が命運を分ける
■「顧問弁護士のNG」を乗り越えて事業化を実現した事例も
■まとめ
医療DXの課題は「データの標準化と共有」と「国民の理解」

——日本における「医療DX」とは、どのような方向性を目指すものなのでしょうか。
髙﨑氏:日本の医療DXが目指すのは、政府全体で推進されている「医療DX令和ビジョン2030」の実現です。このビジョンでは、少子高齢化などの社会構造の変化の中で医療を持続可能なものとするために、デジタル技術を活用して医療制度を革新していく方針が掲げられています。
現在は厚生労働省を中心に、「全国医療情報プラットフォームの整備」「電子カルテの標準化」「診療報酬改定のDX」の3つの柱で取り組みが進んでいます。
——海外の状況と比較した上で、日本の課題とは何でしょうか。
髙﨑氏:厚生労働省が掲げる医療DXの3本柱にあるように、医療データの標準化と共有は、日本の医療DXにおける重要課題と言えるでしょう。
イギリスではNHS(国民保健サービス)が全国で電子患者記録の導入を進め、共通のデータ標準(FHIRなど)を整備しています。アメリカでも、連邦政府の主導でFHIRをはじめとするAPI標準の普及が進み、病院間のデータ共有が広く実現されています。韓国では、国際標準に準拠した医療データ規格を整備し、臨床データの共通モデル(OMOP CDM)への統合も進められています。
これに対して日本では、医療機関ごとに電子カルテの仕様が異なるため、病院間や地域間でのデータ共有や利活用が困難な状況にあります。こうした現状を踏まえ、厚生労働省は2024年度から「標準型電子カルテ」の普及支援を本格化させるとともに、電子カルテ情報共有サービスを中核とする 「全国医療情報プラットフォーム」 の構築を推進し、全国的な相互運用性の確保を目指しています。
また、国民の意識や理解を高めていくことも、重要な課題の一つです。現在でも、マイナンバーカードを用いることで、薬剤情報や健診結果などを一元的に管理できるインフラは整いつつありますが、「マイナ保険証」など一部の制度に対しては、プライバシーや制度運用への懸念の声も上がっています。こうした不安に丁寧に対応し、透明性を確保した説明と対話を通じて、国民の理解と信頼を得ていくことが、今後の医療DX推進の鍵となるのではないでしょうか。
海外では「生成AIを活用した創薬」などの新規事業が加速している
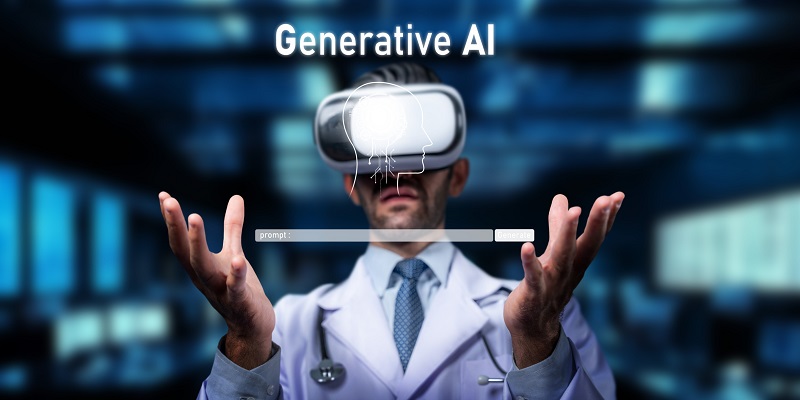
——近年注目を集めている「個別化医療」についても教えてください。
髙﨑氏:個別化医療とは、言い換えれば「その人をよく知り、その人に最適な医療を提供すること」です。
従来の医療では、治験など「集団ベースのエビデンス」に基づいて薬が開発され、処方されていました。しかし、実際には年齢や体重、生活習慣、職業など、さらには遺伝的な特性まで含めて、最適な治療は人それぞれ異なります。 こうした「一人ひとりに最適な医療」を実現するためには、まず各個人の健康データを安全かつ的確に収集・活用できる情報基盤の整備が不可欠です。現在、日本ではマイナポータルを通じて、健診結果や薬剤情報、医療費などを個人が一元的に確認できる仕組みが整いつつあります。 今後は、こうした個人の医療情報と生成AIの技術が結びつくことで、より高度な個別化医療が現実のものになると期待されています。
——生成AIはどのような役割を果たすのですか。
髙﨑氏:生成AIの革新性は、従来のAIとは異なる点にあります。たとえば従来のAIは、「レントゲン画像の陰影がこうなら肺がん」といったように、あらかじめ学習した特徴に基づいて判断するもので、決められた範囲内でしか対応できませんでした。
一方、生成AIは、Wikipediaや論文、医療記録、さらにはインターネット上の情報など、膨大で多様な人間の情報を学習しており、その文脈理解や言語生成能力を通じて、これまで人間が気づけなかった病気の因果関係や新たな診断の視点、臨床的な仮説を導き出すことも可能とされています。
——製薬企業や医療機器メーカーは、AIなどのデジタル技術をどのように活用しているのでしょうか。
髙﨑氏:現状では、先進事例の多くが海外発となっています。
一例を挙げると、アメリカでは、NIH(アメリカ国立衛生研究所)が主導する「All of Us Research Program」という大規模コホート研究を通じて、生成AIを活用したドラッグリポジショニング(既存薬の別用途への転用)の取り組みが進められています。たとえば、アルツハイマー病などに対して、AIが膨大な医療データを解析して候補薬を特定し、すでに臨床データがあることから、副作用のリスクを抑えつつ開発期間を短縮できる可能性があります。これは、生成AIの特性を活かした非常に効果的な手法といえるでしょう。
また、Google DeepMind社が開発した「AlphaFold」は、タンパク質の立体構造を予測するAIとして創薬を飛躍的に加速させてきました。さらに2024年に発表された最新バージョン「AlphaFold 3」では、より高精度に予測できるようになり、創薬の可能性がさらに広がっています。
こうした海外の先進事例を踏まえると、日本企業においても、スタートアップと連携して新たな知見を取り入れたり、AI・データ人材を積極的に登用したりする取り組みが、今後ますます重要になるでしょう。
避けては通れない新規事業。「どれだけ早く動けるか」が命運を分ける

——髙﨑さんはメディカル業界における新規事業開発の現場を数多く支援されています。日本企業にはどのような課題があると感じていますか。
髙﨑氏:新規事業には新たな視点や高度なデジタルを含むスキルが求められます。またトライアンドエラーの繰り返しなので、それらを許容する体制が必要です。その中で、日本企業は「内製化を重視する」傾向があると感じています。
日本企業では、AIやデータに関するリソースやノウハウがない中で、中途採用と社内公募による新規事業チームを組成して内製化する企業が多いと思います。もちろん内製化での対応がうまくいかないわけではないですが、やはり立ち上がりまでに時間を要します。そうした起業家気質を持ち、公募に手を上げる意欲的な人材、デジタルスキルが高い人材に対して特別な報酬体系や、失敗を許容するといった評価制度が用意されていないという現実があり、成功率を高める体制とは言い難い状況にあります。
こうした点を踏まえ、私は日本企業が「コーポレート・ベンチャリング」を本気で戦略として捉え、スタートアップ企業の人材によるスキル・知見・チャレンジングな精神など新たな風を積極的に取り入れることで、早期立ち上がりと円滑な運用につながると考えています。
しかし日本企業は伝統的にM&Aに対して慎重で、スタートアップを買収することに後ろ向きです。一方のスタートアップ側も、日本では「売却=負け」と考える傾向があり、大企業とスタートアップの間でマッチングが成立しにくい構造があるのです。
経済産業省の報告書によれば、アメリカではスタートアップの約9割がM&Aを通じてイグジットしており、成長戦略の一環としてごく自然に取り入れられています。対して、日本ではM&Aを通じてイグジットするスタートアップはまだ3割程度。もちろんそれぞれの文化的なギャップを乗り越えなければならないという課題はあるものの、事業成長に向けては、企業が「内製化ありき」の姿勢を見直し、社外との連携にオープンになることが求められているのではないでしょうか。
——メディカル業界が直面する今後の課題や、デジタル活用について教えてください。
髙﨑氏:製薬業界でいえば、特許期間の終了によって売上が減少する「特許の崖(パテントクリフ)」は重大な課題です。業界の分析によれば、世界の製薬企業は2027年から2028年にかけて、集中的に医薬品の特許が失効すると予測されています。この「パテントクリフ」と呼ばれる現象は、業界全体が直面する重大な経営課題です。
既存薬だけに依存せず、新たな事業を育成していくことは、あらゆる製薬企業にとって避けられないテーマです。そのためには、新規事業への挑戦やコーポレート・ベンチャリングの推進が不可欠であり、そのカギを握るのがデジタル活用なのです。
デジタルの世界では「ネットワーク効果」といって、ユーザー数そのものが価値を生む構造が広く知られています。たとえばGoogleの検索エンジンやAmazonのECサイトは、多くのユーザーが集まることでさらに利便性が高まり、新たなユーザーを引き寄せるという好循環を生み出しています。
医療分野でも同様の構造が成り立ちます。早期にプラットフォームを構築し、多くのユーザーやデータを蓄積している企業は、そのアセットを活用して成長を加速させています。今後の事業展開や競争優位を見据えると、どれだけ早く動き出せるかが、企業の命運を分けると言っても過言ではありません。
「顧問弁護士のNG」を乗り越えて事業化を実現した事例も
——医療DXに挑む企業が直面しがちな「現場のリアルな壁」についてもお聞かせください。その壁を乗り越えるために、髙﨑さんはどのように関わっていますか。
髙﨑氏:企業からは「こんなプロダクトを作ったもののうまくいかない」といった相談が寄せられることが多いです。背景を紐解いていくと、ニーズの見極めが不十分だったり、初期設計に問題があったりするケースがあります。支援する側の本音としては「もっと早く相談してくれれば…」という本音を抱くことも少なくありません。
私が理想とする関わり方は、戦略立案の初期段階からプロジェクトに参画し、現状の課題や将来的なリスクを見極めた上で、技術動向も踏まえてプロダクト・ライフサイクル全体を俯瞰した設計支援を行うことです。こうした伴走型の支援を通じて、事業の持続的な成長と価値創出に貢献したいと考えています。
実際、私は、自らが主宰する医療AIプラットフォーム「Medical AI Nexus」を通じたAI人材の育成や、AIを活用した新規事業創出をハンズオンで支援しています。企業側の顧問弁護士がNGを出したテーマでも、レギュレーションと向き合いながら突破口を模索し、実現にこぎ着けた経験もあります。新規事業の現場でぶつかりがちな壁に対して、私自身多くの経験を持っています。そのリアルな経験を活かし、本質的な支援ができるよう努めています。
——髙﨑さんもスタートアップで新規事業に取り組みながら、大学での教育・研究など多岐にわたる活動を展開されています。なぜそこまで他社に貢献したいと思うのでしょうか。
髙﨑氏:私は長年、行政官として制度の枠組みをつくる側の仕事をしてきました。当時手掛けていた仕事は日本の発展のために欠かせないものだったと自負していますが、行政の立場ではやりきれなかったこともあります。だからこそ、民間で「実際に手を動かし、価値を創り、顧客に直接届ける立場」となった今は、社会全体やこれから生きる次世代のためにやり残したことをすべて実現したいという気持ちがあるんです。
とはいえ、自分一人の力だけでできることや、スタートアップという小規模な枠組みでできることが限られているのも事実です。大企業には大企業の強みがありますし、保有しているデータもアセットも豊富です。だからこそ日本の大企業はもっともっと成長できるはずだと思っています。
他方、一人の父親としては「子どもたちに誇れる背中を見せたい」とも強く思っています。世の中を少しでも良くし、子どもたちにより良い未来を残すこと——それこそが自分の使命だと感じています。
そして何より、新規事業は面白いんですよね。これまでにないテーマに挑み、新たな価値を創造することにワクワクしています。誰に何を言われても、私はワクワクすること、日本の未来をよくする支援をこれからもずっとやり続けたいと思っています。
【プロフィール】
合同会社ディケイズ 代表社員(医師・医学博士・MBA) 髙﨑 洋介氏(たかさき・ようすけ)
AI physician-scientist・連続起業家・元厚生労働省医系技官・医師・医学博士・ハーバード大学理学修士・ケンブリッジ大学MBA・コロンビア大学行政修士。岡山大学医学部卒業後、内科・地域医療に従事。厚生労働省入省、医療情報技術推進室長、医療国際展開推進室長、救急・周産期医療等対策室長、災害医療対策室長等を歴任。文部科学省出向中はライフサイエンス、内閣府では食の安全、内閣官房では医療分野のサイバーセキュリティを担当。国際的には、JICA日タイ国際保健共同プロジェクトのチーフ、WHOインターンも経験。
退官後は、日本大手IT企業にて保健医療分野の新規事業開発や投資戦略に携わり、英国VCでも実務経験を積む。また、複数社起業し、医療DX・医療AI、デジタル医療機器開発等に取り組むほか、東京都港区に内科クリニックを開業し、社外取締役としても活動。現在、大阪大学大学院医学系研究科招へい教授、岡山大学研究・イノベーション共創機構参事、ケンブリッジ大学ジャッジ・ビジネススクールAssociate、広島大学医学部客員教授として、学術・教育・研究に従事。あわせて、医療関係者のための医療AIプラットフォーム「Medical AI Nexus」を主宰。 社会医学系指導医・専門医・The Royal Society of Medicine Fellow
まとめ
医療DXと「個別化医療」の進展は、社会課題の解決と企業の持続的成長を両立する大きな可能性を秘めています。生成AIや医療データの利活用が加速する中で、製薬企業や医療機器メーカーに求められるのは、内製化にこだわらず、スタートアップをはじめとする社外パートナーとの共創を柔軟に取り入れることです。M&Aや提携といったコーポレート・ベンチャリング戦略を、単なる選択肢ではなく“成長の中核”として位置づけることが重要です。挑戦や失敗を恐れず、未来の成長可能性に信じて一歩を踏み出せるかどうか。それがこれからの時代における企業の生き残りを大きく左右する要因となるでしょう。
行政、企業、スタートアップのそれぞれの現場に深く関わり、戦略立案から実行フェーズまで一貫して、自らも挑戦し、そして多くのクライアントと伴走してきた髙﨑氏は、こうした変革の時代における非常に心強いパートナーです。自社の課題を可視化し、変革に踏み出す第一歩として、「HiPro Biz」のプロ人材を頼ってみてはいかがでしょうか。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)