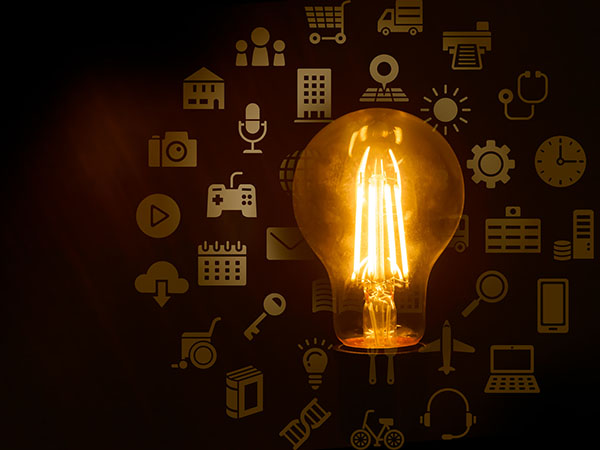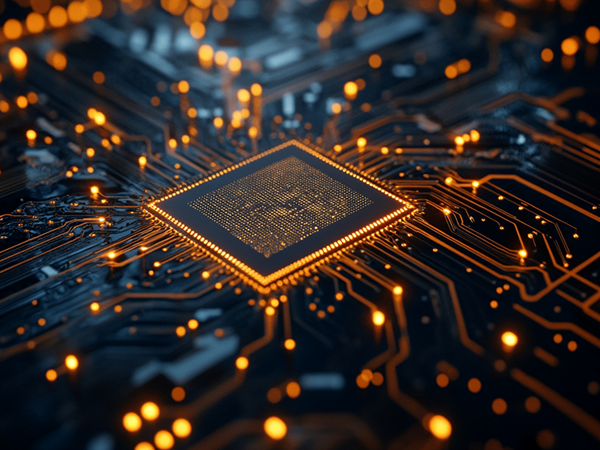製造業の新規事業はなぜ迷走するのか?自社シーズと市場ニーズをマッチングさせるカギとなるのは、「顧客の声」と「当事者意識」
2025年09月29日(月)掲載
既存事業や関連技術の成熟を機に、新たな収益柱を模索する製造業企業が増加しています。優れた技術やノウハウを持ちながらも、市場ニーズと合致した新規事業を立ち上げることに苦戦する企業は少なくありません。
IoT化やデジタル技術の進化に伴い、豊かなデータを得られるようになったにも関わらず、なぜ自社シーズと市場ニーズのマッチングは困難なのでしょうか。大手写真関連メーカーにおける技術開発や新規事業開発の豊富な経験を持ち、現在は多数の製造業企業の新規事業開発で支援に携わるプロ人材、中台 加津男氏に製造業界における新規事業開発の肝を聞きました。
情報過多やビッグワードの乱立が新規事業開発の障壁に

――製造業における市場ニーズについて、近年の変化をお聞かせください。
中台氏:これまで国内産業を成長させてきた多くの技術が成熟期を迎えたことで、従来に比べて市場ニーズを的確に捉えるのが難しくなっています。IoTやクラウドの活用が進み、データを通じた問題の可視化は容易になりました。しかし、それは本質的な市場ニーズを捉えることとは別の話です。
むしろ情報過多であることが裏目に出て、顕在化した事象に囚われすぎて表面的な分析に留まり、ゼロベースでの本質的課題解決の選択肢を狭める要因にもなっています。私に支援を依頼される企業にも、様々な情報の整理が進まず、自社の強みやアセットの活用策が絞り込め無いまま試行錯誤しているケースをよく見かけます。
――では、アセットをどのように整理すれば、新規事業の成功につながりやすいのでしょうか。
中台氏:新規事業開発の初期段階で、多くの企業が「技術の棚卸し」を試みます。それは必要なステップではあるものの、技術の棚卸しさえすれば事業テーマが描けるというものではありません。
技術の棚卸しは「どの分野に、どのように挑むのか」というビジョンを前提にしなければ、単なる技術名の列挙に終わってしまいます。また、抽出された技術が本当に強みなのか、なぜ強いのかといった考察も深めなければ、戦略的に活かすことはできません。
さらに、「脱炭素」「AI」「IoT」といったビッグワードも、新規事業開発においては扱いに注意が必要です。それらのキーワードを漠然と議論するだけで満足してしまい、具体的なターゲット戦略に落とし込めていない活動を多く見かけます。現場を推進するメンバーが「当社の画像処理技術をAI化で強化して、製造検査工程の不良検知率を2桁改善したい」というような主体的な視点で、ビッグワードを起点に具体的な業界ニーズを反映した実行シナリオを描くことが重要です。
答えは市場が知っている――議論を生み出す実践的なアプローチ

――自社シーズと合致する市場ニーズを見つけるための有効なアプローチはありますか?
中台氏:新規事業開発に必勝法はありません。しかし確実に言えるのは、その答えを知っているのは社内メンバーではなく“お客さま”、つまり市場であるということです。
具体的なアプローチとしては、社内会議の討議テーマを「事業アイデア導出、市場ニーズ想定」から、「自社の技術をどのように外部に理解してもらうか」に切り替えましょう。わかりやすく伝える工夫をしながら、外部の人々に自社技術を理解してもらい、お客さまとの対話に結び付けていくことが市場ニーズの発見へとつながります。
登山に例えるなら、事前情報に基づいた準備は欠かせませんが、頂上への最適ルートはその山を知る人に聞きながら進むほうが効率的ですよね。社内会議で市場ニーズの可能性について議論を延々とし続けるのは、登山道の入口から一歩も進まず、まだ見ぬルートの作戦を悩み続けているのと同じことだと思います。
また、自社技術をわかりやすく伝える工夫として、実物サンプルの準備は極めて有効です。手に取れるサンプルは、冗長な説明資料よりも議論の起点となりやすく、顧客の新たな気付きを引き出す効果があります。さらに新規市場の参入プロセスにおいては、一度に多くの潜在顧客に訴求できる技術展示会などを活用するのも効果的です。
――これまでのご経験の中で、新規事業開発において重要だと思うポイントをエピソードと共にお聞かせください。
中台氏:過去、新しい機能性材料を市場導入すべく、ある企業に提案した時の話が参考になるかもしれません。先方担当者の反応は、「技術的に魅力はあるが、こんな風に改良できないの?」というものでした。
その要望は社内で検討したことも無く、その場では「ちょっと考えてみます」と答えを濁したのですが、そこには大きなヒントがありました。社内で改めて顧客要望について理解を深め、開発を本格化すると技術的な実現可能性も見出され、サンプル準備に至りました。改良した材料は、最終的に複数の大手メーカーに採用され、差別性の高い高付加価値を持つ商品へと進化しました。
製造業の大手メーカーは自社技術に自負を持っているので、自らが正解を知っていると思いがちです。顧客の声を引き出し、そのアイデアを活かすことが成功への道を拓きます。
――逆に陥りがちな失敗や、それを引き起こす要因はありますか?
中台氏:新規事業開発が迷走する多くの要因は内部にあります。特に、既存事業の経験則ベースの判断に拘ることで、新規事業の可能性を狭めてしまうケースを多く見受けます。既存事業の成功体験を新規事業に持ち込もうとすると、新しい挑戦の芽を摘んでしまいます。
意思決定を担う上位者は、新規事業の不確実性を受け入れつつ、挑戦の芽を摘まない議論が行える環境を整えることが重要です。問いかけるべきは「売れるのか?」「作れるのか?」といった目先の問いではなく、「このテーマで勝つためには何が必要か?」という本質的で高い視点からの問いです。また現場のメンバーは、新しいテーマに対して当事者意識と熱量を持ち、一つひとつの課題に向き合いながら地道に乗り越えていくほかありません。
新規事業の成功要因となるのは、謙虚に学ぶ姿勢と圧倒的な当事者意識
――仮説検証から市場導入までのプロセスにおいて、実務的な部分でのアドバイスはありますか?
中台氏:自社技術のプレゼン資料の準備にも注意が必要です。製造業でのBtoB提案においては、顧客側の担当者が技術者であることが多く、彼らの知的好奇心を喚起する提案が効果的です。専門分野が異なる相手にも理解できるよう自社技術を伝えることが、議論を深め合うきっかけになります。
また、新規参入業界の「作法」を謙虚に学ぶ姿勢も重要です。商品開発では、開発プロセスごとにチェックポイントを設け、設定された要件を満たしたら次のステージに進む「ステージゲート方式」を採用することが多いと思います。しかし、自社の既存事業を前提にしたステージは、異なる市場に挑む新規事業開発においては役立たないどころか障害になることもあります。参入業界特有の検証プロセスや承認手続きををお客さまから学び、柔軟かつスピーディに対応していくことが確度の高い事業化へとつながっていきます。
――最後に、新規事業開発担当者が必要なマインドやスキルを聞かせてください。
中台氏:既存事業のスキームの中で新規事業を開発する挑戦には、多くの困難が伴います。しかも新規事業開発の成功確率は約2〜3割と言われていますから、心理的な負担も大きいでしょう。そこを突破するには、「私はこのテーマを成功させたい」という強い当事者意識が不可欠です。私が支援させていただいている企業においても、主体的に取り組むリーダーを中心として社内外の関係者を巻き込んでいくプロジェクトが良い結果に結び付いています。
このように取組むことで、たとえ新規テーマが失敗したとしても、そこに関わったメンバーに培われた課題形成力や市場観察力といったスキルは、個人、会社双方にとって貴重な資産として残ります。
もし、新規事業開発担当に任命された場合は、自身を大きく成長させる機会と捉えてください。これから自分がリードする新規事業開発やインキュベーション活動は必ず事業貢献に結び付くという確信と当事者意識を持って挑めば、それは必ずあなたの将来の武器になります。
<プロフィール>
中台 加津男(なかだい・かつお)
ウィンバリュープロジェクト代表
大手写真関連メーカーで20年以上のキャリアを持つ新規事業開発のエキスパート。1982年の入社後、黎明期の電子映像機器開発に従事し、デジタル技術の進化を最前線で体験。2000年を境に基幹事業である写真材料事業が急速に縮小する中、新規事業開発部門の責任者として自社の技術資産を活用した「高機能性材料分野の創出」を推進し、高付加価値商品の市場導入を主導した。2017年より独立し、製造業を中心に上場、非上場30社以上の新規事業開発や事業戦略策定を伴走支援。技術シーズと市場ニーズのマッチングから事業化まで、製造業の新規事業創出を総合的に支援している。
まとめ
製造業における新規事業開発は、技術の成熟化とデジタル化の進展により、従来以上に本質的な市場ニーズを導くのが困難な状況にあります。しかし、日本の製造業には長年培われた優れた技術資産があり、それを市場ニーズと適切にマッチングできれば大きな成長機会を創出できます。重要なのは社内議論に終始せず、顧客との対話を通じて潜在ニーズを発掘し、当事者意識を持って取り組むことです。また、既存事業の成功体験に囚われず、新規市場の作法を謙虚に学ぶ姿勢も欠かせません。「HiPro Biz」では、製造業の新規事業開発や事業戦略策定に豊富な実績を持つプロ人材が多数登録しています。新規事業を力強く推進していくために、「HiPro Biz」のサービス活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)