成果につながるビジネスコンセプトとは?設計フローや具体的なポイントを解説
2025年05月20日(火)掲載
- キーワード:
「コンセプト」は、ビジネスを成功させる上で欠かせない概念です。コンセプトの設計次第で、その商品やサービスが消費者に受け入れられるかどうかが決まるといっても過言ではありません。
本記事では、ビジネスコンセプトの重要性や設計フローについて、コンセプトの活用シーンとあわせて解説します。ターゲットに刺さる商品やサービス開発を検討中のご担当者様は、ぜひお役立てください。
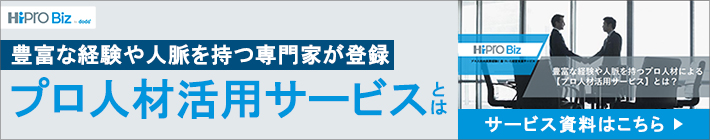
■そもそもコンセプトとは?
■ビジネスシーンでコンセプト設計が必要な理由
■ビジネスに活用できるコンセプトの設計方法とそのフロー
■コンセプトを設計する際のポイントと理由
■設計したコンセプトの活用シーン
■ビジネスシーンでコンセプト設計は必要不可欠
そもそもコンセプトとは?

コンセプトとは、日本語で「概念」や「構想」と訳される言葉で、ビジネスや芸術、哲学などの幅広い分野で用いられます。この言葉が示す意味は、それぞれの分野によって異なりますが、作り手の意図、あるいは目的を表しているという点は共通しています。
ビジネスにおけるコンセプト
ビジネスシーンにおいて、コンセプトは主に企業が提供する商品やサービスの方向性を決定する目的で使用されます。「誰に、何を、どのように提供するか」を言語化し、ビジネスの構想を他者に共有するために使われる言葉です。
コンセプトによって定まるものは、商品やサービスの特徴だけではありません。顧客へのアプローチ方法や、競合他社との差別化のポイントなども明瞭になります。いずれも、ビジネスの成功に欠かせない基盤となる要素といえるでしょう。
テーマとの違い
コンセプトに類似する言葉に「テーマ」があります。どちらも日常的に用いられる言葉ですが、普段から厳密に区別して使っている人は少ないかもしれません。
ビジネスの場では、コンセプトが商品やサービスの構想であるのに対し、テーマはその前提となる「主題」といえます。一般的に商品やサービスを開発する際は、テーマを基にコンセプトを設計するという手順を踏みます。
また「コンセプト=テーマ+切り口」という言い換えも可能です。従って、同じテーマで考えたとしても、切り口によっては異なるコンセプトに仕上がるはずです。
ビジネスシーンでコンセプト設計が必要な理由
ここで改めて、ビジネスを成功させるためにコンセプト設計が必要である理由を見ていきましょう。
マネタイズの判断指標になるため
ビジネスを始める上で「それは本当にお金になるのか?」という視点を持つことは、極めて大切です。あいまいなアイデアのままでは、その先の収益化を判断することは困難です。コンセプトを明確にすることで初めて、消費者のニーズや市場規模、提供する価値の内容などが整理され、マネタイズが可能かどうかを見極められます。
具体的なコンセプトがあってこそ、将来的な収益化の可能性をより現実的に検討できるのです。
共通の指針になるため
コンセプトは、事業に関わる全ての人にとって、いわば「共通言語」といえるものです。企業が多くの社員やパートナーと協力して事業を展開する際、全員が同じ方向を向いて進むには、軸となる考え方が必要不可欠です。
コンセプトがはっきりしていれば、日々の業務や意思決定の際に判断のよりどころとなり、統一感のある行動を生み出せます。業務の中で迷いが生じたときも、原点であるコンセプトに立ち戻ることで、ぶれない判断が可能となります。
意思決定のスピードが上がるため
ビジネスの現場では、迅速な意思決定が求められる場面が少なくありません。その際に全体の方向性や価値観が明確であれば、「何を優先するか」「どこにリソースを投入するか」といった判断もスムーズになります。
反対に、コンセプトがあいまいな状態ではチーム内の認識もバラバラになり、意思決定が遅れたり、迷いが生じたりするリスクがあります。コンセプトとは、企業がスピーディーな経営判断を必要とする際の理念であり根幹なのです。
競合と差別化できるため
コンセプトの設計は、独自性を強調する際にもプラスに働きます。
市場にはすでに多くの類似商品やサービスが存在しており、後発で成功するためには明確な差別化が不可欠です。コンセプトをつくる過程では、市場や競合、ターゲット層の調査が行われ、それらを踏まえた上で独自の価値や立ち位置が定まります。結果として「自社にしかない魅力」が鮮明になり、消費者から選ばれる理由が生まれるのです。
中途半端なコンセプトでは、先発の商品やサービスに埋もれてしまう可能性が高くなります。
共感が得られれば購買やリピートにつながるため
現代の消費者は、単に商品やサービスのスペックだけでなく、その背景にある想いや理念にも関心を寄せています。そのため、コンセプトに共感してもらえれば、継続的な支持を得られる可能性が高まります。
たとえば「環境への配慮」や「地域貢献」といったメッセージを含む商品は、その価値観に響く層からの支持を集めやすいでしょう。こうした共感は、ファンの育成やブランドロイヤルティの向上にもつながります。
ビジネスに活用できるコンセプトの設計方法とそのフロー
続いて、ビジネスコンセプトを設計するための基本的なフローを紹介します。
コンセプトは、商品やサービスの価値を伝える核であり、全ての戦略や施策の軸となるものです。以下のフローに沿って効果的なコンセプトを設計し、ビジネスに活用しましょう。
ステップ1市場の調査
最初に取り組むことは、市場の動向や競合の状況を正しく把握することです。どのような商品やサービスが人気を集めているのか、また市場にどのような隙間(ニッチ)があるのかを探ることは、コンセプトの設計に欠かせません。
さらに、過去に同じようなビジネスが失敗していないか、成功している事例との違いは何かを分析することで、方向性を定めやすくなります。市場を俯瞰して現状を理解することで、立案するコンセプトに説得力を持たせられるでしょう。
ステップ2ターゲットの選定
次に重要なことは「誰に向けたビジネスなのか」を明確にする、ターゲットの選定です。ターゲットが漠然としたままだと、商品開発やサービス設計がぼやけてしまい、訴求力のあるコンセプトを打ち出すことが難しくなります。年齢や性別、ライフスタイル、職業、価値観など、複数の切り口から顧客像を具体化しましょう。
さらに、ペルソナの設定まで踏み込めば、よりリアルな視点でニーズを読み取れるはずです。ペルソナの具体的な設定方法は、後ほど解説します。
ステップ3ターゲットが持つ不満や課題の調査
ターゲットが明確になったら、彼らが抱えている不満や課題を探ります。SNSやレビューサイト、アンケートなどを通じて、ターゲットの声を拾い上げましょう。
「使いにくい」「価格が高すぎる」「選択肢が少ない」など、日頃から商品やサービスと接しているユーザーの不満の中には、新しいビジネスのヒントが眠っています。こうした小さな声を丁寧に拾うことが、競合とは一線を画すユニークな価値の提案へとつながります。
ステップ4不満や課題の解決方法を明確化
見えてきた課題に対し、具体的な解決策を設計します。たとえば「操作が複雑に感じる」という課題にはUIの簡素化で対応する、あるいは「持ち運びにくい」という声には軽量設計や折り畳み機能の実装などがひとつの解決策になるでしょう。
この段階では、現実的な実装可能性にも配慮しながら、ターゲットにとって本当に価値あるソリューションを模索することが求められます。小さな不満へのきめ細かな対応こそが、顧客に選ばれる理由につながるのです。
ステップ5抽象化したキーワードを組み合わせてコンセプトを設計
最後に、見えてきた不満や解決策を、短く印象的な言葉に落とし込めば、コンセプトの設計は完了です。抽象的なキーワードを組み合わせて、魅力的なコンセプト文へと仕上げてください。
この一文が、社内外での共通認識として、ブランドの世界観や方向性を伝える旗印になります。言葉の選び方次第で受け手の印象は大きく変わるため、ターゲットの心に響くキーワードを丁寧に選定しましょう。
コンセプトを設計する際のポイントと理由
コンセプト設計は、ただのアイデア出しではありません。伝えたい価値を「誰に、どう届けるか」という視点で整理することで、初めて意味を持つのです。
そのためには、いくつかの要点を確実に押さえる必要があります。ここでは、コンセプトを設計する際に特に重要な3つのポイントを解説します。
ペルソナを詳細に設定する
まず取り組むことは、具体的な「ペルソナ」の設定です。ペルソナとは、単に年齢や性別といった属性だけでなく、その人物の生活スタイルや価値観、日常の行動パターンまでを深掘りした、いわば仮想のユーザー像です。
たとえば、以下のような人物像を詳細に思い描いてみましょう。
- 35歳
- 女性
- 既婚・共働き
- 平日は多忙、週末は家族と外食を楽しむ
- 移動は車が中心
- 買い物は利便性重視
ペルソナが不明瞭では、「コンセプトが完成しても誰にも響かない」という可能性があります。有効なペルソナを設定することで、コンセプトの方向性が定まりやすくなり、消費者にとって本当に価値あるものを考える土台ができあがるのです。
関連記事:これからのカスタマージャーニーの捉え方、マップの作り方やペルソナ設計
バリュープロポジションを考える
次に重要なことは「バリュープロポジション」の明確化です。バリュープロポジションとは「顧客ニーズが大きく、競合他社にはない独自の強み」のことです。
似たような商品やサービスがあふれている今日では、単に便利だったり見た目が良かったりするだけでは消費者から選ばれません。市場で生き残るためには、ニーズの大きさと競合との違いの両方を踏まえ、顧客に選ばれるポイントを明確に打ち出す必要があります。
コンセプトを考える際は、このバリュープロポジションを押さえることを意識すると良いでしょう。
ゴールを設定する
コンセプト設計の最後に、具体的な「ゴール」を設定しましょう。ここでいうゴールとは、商品やサービスに対してユーザーに期待するアクションのことです。
- 資料請求
- 商品やサービスの購入
- リピーターの獲得
ゴールが明確に定まっていないとコンセプト自体がぶれてしまい、発信するメッセージが弱くなります。反対に、ゴールがはっきりしていれば、ユーザーに取ってほしい行動もクリアになり、マーケティングの効果が高まります。
設計したコンセプトの活用シーン
最後に、設計したコンセプトを活用できる具体的な分野の一例を紹介します。自社で取り組んでいるものがあれば、ぜひ参考にしてください。
商品やサービス開発
繰り返しになりますが、コンセプトの設計は商品やサービスの開発時に役立ちます。コンセプトが確立しているおかげで、企業は企画から販売までの業務に対して一貫性を持って遂行できるのです。
開発に携わる社員全員が、定まったコンセプトによって同じビジョンを共有できていれば、効率的な製品開発が可能になるでしょう。
マーケティング戦略の策定
できあがった商品やサービスのプロモーション活動を展開する際も、コンセプトが軸になります。最初に設計したコンセプトに沿ってマーケティング戦略を練ることで、消費者に一貫性のあるメッセージを届けられます。
各タッチポイントでの発信にコンセプトを反映することを意識すれば、ターゲットに強い印象を与えられるはずです。
Webサイト制作
コンセプトが活用されるシーンとしては、Webサイトの制作も挙げられます。
Webサイトのデザインやコンテンツを考える際は、制作に関わる外部の企業やクリエイターにコンセプトの共有を徹底しましょう。共通認識を持って制作することで一貫性が担保され、ユーザーにとっても魅力がわかりやすく伝わるWebサイトが実現します。
ビジネスシーンでコンセプト設計は必要不可欠
本記事では、ビジネスコンセプトの重要性について解説し、商品やサービスの開発時にどのように活用できるのかを探ってきました。
ビジネスで競合他社に打ち勝つには、明確なコンセプトの設計が欠かせません。具体的なペルソナやバリュープロポジションを押さえたコンセプトを設計し、商品やサービスの開発、さらにはその後のマーケティングに活かしましょう。
また、コンセプトを設計する際は、外部の専門家からの客観的なアドバイスを受けることも一つの方法です。
「HiPro Biz」は、経営課題に取り組む企業向けに、高度な課題を解決できるプロ人材と共に課題解決に導くサービスです。興味を持たれたご担当者様は、お気軽にお問い合わせください。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)




