ブランディング戦略の立て方と具体的な手順、成果を出すポイントを解説
2025年07月28日(月)掲載
- キーワード:
企業が商品やサービスの認知度を高め、競合と差別化を図る上では「ブランディング戦略」が重要な要素となります。ブランディングに成功すれば、多くのファンを獲得でき、持続的な利益の確保につながります。
本記事では、ブランディング戦略を立てる具体的な手順を紹介し、あわせて成功のポイントをお伝えします。自社のブランディングに力を入れたいとお考えの経営者や管理者の方々は、ぜひ参考にしてください。
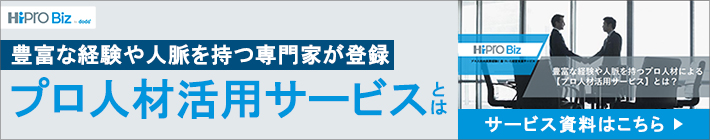
■ブランディング戦略とは
■ブランディング戦略を実施するメリットや効果
■BtoBとBtoCのブランディング戦略の考え方の違い
■ブランディング戦略の立て方と具体的な手順
■ブランディング戦略を成功させるポイント
■ブランディング戦略では、競合との差別化を意識することが重要
ブランディング戦略とは
ブランディング戦略とは、自社が持つブランドの価値やイメージを高め、競合と差別化を図りながら顧客に強く印象付けるための取り組みを指します。広告施策や販促活動にとどまらず、ブランドとしての方向性や世界観を整理し、それを一貫して発信しながら顧客との信頼関係を築くことが目的です。
また、ブランディング戦略はマーケティングと連動させながら進める必要があります。効果的なマーケティングを実施してこそ、商品やサービスを届けたい相手に手に取ってもらうことが叶い、持続的な利益の確保に寄与します。
そもそもブランディングとは?
そもそもブランディングとは、自社の商品やサービス、さらには企業そのもののイメージをつくり上げ、顧客に魅力的に伝える活動を指します。例えば、コーヒーが飲みたい顧客に対して「あのブランドのコーヒーを飲みたい」と思わせることが、ブランディングの力です。
同じような商品やサービスがあふれている現代では、品質の良さだけで差別化が図れません。ブランディングによって自社ならではの価値を表現し、共感を得ることが求められているといえるでしょう。
ブランディング戦略を実施するメリットや効果
ブランディング戦略を実施することで、企業は商品やサービスを売る以上の価値を生み出せます。ブランディング戦略によって得られる代表的なメリットや効果は、次の通りです。
- ブランド価値に共感してくれるファンやリピーターの獲得につながる
- 競合他社との差別化が図れる
- 広告や広報活動による認知拡大の効果を高められる
- 資金調達のハードルが下がる
ブランド価値に共感してくれるファンやリピーターの獲得につながる
ブランディング戦略を進めることで、自社の理念や世界観に共感してくれるファンを獲得しやすくなります。
ファンが重視するものは、商品やサービスの質よりもそのブランドが持つ「価値観」です。故に、価値観を重視した戦略を展開すれば、ファンの自社に対する愛着は自然と深まり、長期的な顧客関係の構築に寄与するでしょう。こうしたファンはリピーターとして継続購入してくれる可能性が高く、企業にとって安定した売上を支えてくれる大きな基盤となります。
競合他社との差別化が図れる
市場に似たような商品やサービスがあふれる中では、自社独自の魅力を打ち出すことが競争優位性を確保する上で重要です。ブランディング戦略により自社のストーリーや強みをしっかりと伝えられれば、顧客に「このブランドだから選ぶ」という理由を提供できます。
また、自社にしかない価値を提供することでファンが定着し、単純な価格競争に巻き込まれるリスクが抑えられるようにもなるでしょう。
広告や広報活動による認知拡大の効果を高められる
ブランドの認知度が高まることに伴って、広告や広報活動の成果も向上します。すでに一定のイメージが浸透しているブランドは、これまで築いた信頼が土台となり、メッセージが届きやすくなるのです。
こうしたブランドは、顧客に発信内容を受け入れられる可能性が高いため、SNSやメディアを活用したマーケティングでも効率的に集客できる傾向にあります。
資金調達のハードルが下がる
ブランド力と知名度が確立されている企業は、金融機関や投資家から評価される傾向にあります。これにより、事業拡大や新規事業の立ち上げ時に、必要な資金をスムーズに調達しやすくなるのです。
このようにブランディング戦略は、販売面だけでなく企業活動全体にプラスの効果をもたらしてくれます。
BtoBとBtoCのブランディング戦略の考え方の違い
ブランディング戦略は、ターゲットが「企業」か「個人」かによって、考え方が大きく異なります。BtoB(Business to Business)では企業同士の取引が前提となるため、より論理的かつ合理的な価値訴求が求められます。一方でBtoC(Business to Consumer)は、顧客一人ひとりの感情や直感に訴えかけるアプローチが重要です。
さらに、購買決定のスピードや意思決定に関わる人数、信頼構築のプロセスにも違いがあるので、それぞれに最適化したブランディングを考えなければなりません。以下の表に、BtoBとBtoCのブランディング戦略の違いをまとめました。
| BtoB(企業向け) | BtoC(個人向け) | |
|---|---|---|
| 意思決定のプロセス | 複数人、複数部署での合意が必要で、意思決定までの期間が長い | 個人が比較的短期間で意思決定する |
| 価値訴求の軸 | 論理的かつ実用的なメリット(コスト削減や業務効率化など) | 感情的な価値(共感や楽しさ、安心感など) |
| 信頼構築のポイント | 導入実績や専門性、営業担当者の対応などで信頼を醸成する | 口コミやSNSなどでブランド体験を共有し、共感を得る |
| 主な施策 | メディアでの露出、ホワイトペーパーの作成、展示会への参加など | マスメディア広告、SNSキャンペーン、インフルエンサーの活用など |
BtoBでは「実績」や「業務改善の効果」といった、合理的な基準で判断されるケースが多いことに対し、BtoCでは「共感」や「ブランドイメージ」で選ばれる傾向にあります。自社のビジネス領域に合わせて、それぞれの特性に沿った戦略を練ることが、ブランドの価値を最大限に引き出すためには大切です。
関連記事:BtoB企業のブランディング、基本の進め方や成功事例
ブランディング戦略の立て方と具体的な手順
ブランディング戦略を成功させるには、担当者の感覚や勘に頼るのではなく、体系的な手順に基づいてプランを設計することが重要です。ここでは、実践的かつ効果的なブランディング戦略の立て方を段階的に解説します。
- 1.自社の商品やサービスが与える価値を正確に把握する
- 2.ブランディングを展開するターゲットを決める
- 3.競合ブランドとの差別化要素を特定する
- 4.市場や競合の中でのポジショニングを決める
- 5.ブランドアイデンティティを構築する
- 6.ブランディング戦略のPR方法を決定する
- 7.効果測定を行い、戦略を継続的に改善する
関連記事:新事業・新ブランド立上げ時の体験的マーケティング論-消費者にどうプロモーションするべきか?
STEP1 自社の商品やサービスが与える価値を正確に把握する
まずは、自社の商品やサービスが顧客にどのような価値を提供しているのかを明確にする必要があります。顧客アンケートやインタビュー、社内ヒアリングなどを通じて、自社が選ばれている理由や評価されている強みを洗い出しましょう。
客観的な視点を取り入れるために、外部の専門家に依頼することも有効です。
関連記事:ブランドストーリーとは?注目される理由や作成方法、成功事例を解説
STEP2 ブランディングを展開するターゲットを決める
次に、ブランドの価値を伝えていく顧客層を絞り込みます。自社の強みを整理した上で、商品やサービスを特に利用している層をイメージすることが大切です。
ペルソナを設定して顧客の具体的な人物像を描けば、ターゲットが明確になりブランディング戦略の方向性に一貫性が生まれます。
STEP3 競合ブランドとの差別化要素を特定する
ターゲットが決まったら、競合他社と比較したときに自社が持っている、独自の価値や特徴を洗い出して言語化します。この差別化要素は、自社のブランドが顧客に選ばれる決め手となります。機能面やサービス面だけでなく、理念や世界観といった無形の価値にも目を向けることがポイントです。
STEP4 市場や競合の中でのポジショニングを決める
競合他社との差別化要素を基に、市場の中でどのような立ち位置を目指すのかを決定します。「品質」「価格」「サービス内容」など、自社の強みになり得る項目はさまざまです。これらの強みを軸に、顧客に選ばれる理由を明確に伝えられるポジションを取りましょう。
なお、市場から求められる立ち位置は常に変化していくため、顧客の意見や競合他社の動向を基に、定期的に見直すことも大切です。
STEP5 ブランドアイデンティティを構築する
ブランドとしての存在意義や将来像を定義し、顧客に持ってもらいたい企業イメージ、つまりブランドアイデンティティを築きます。ブランドに触れた顧客がどのような印象を受けるのかをコントロールするために、細部まで丁寧に創り上げましょう。ブランドアイデンティティを構築する具体的な方法としては、以下の2つが挙げられます。
ブランドパーパスやビジョンの言語化
ブランドが存在する目的(ブランドパーパス)や将来像(ビジョン)を明確な言葉で表現し、社内外で共有します。これにより、ブランドの方向性がぶれることを防ぎ、全ての活動に統一感を持たせられます。
ブランドを象徴するキャッチコピーやロゴ、デザインの作成とトンマナの確立
ブランドの価値やメッセージを直感的に伝えるために、ロゴやキャッチコピー、デザインなどを作成します。色やフォント、トンマナ(トーン&マナー)を統一し、Webサイトや広告、営業資料など、あらゆる場面でブランドの世界観を感じてもらえるように工夫しましょう。
STEP6 ブランディング戦略のPR方法を決定する
アイデンティティに基づき、ブランドの価値をプロモーションする具体的な手段を検討します。企業がブランディング戦略に活用できる方法は、SNSやオウンドメディア、動画広告、イベントなど、多岐にわたります。ターゲットに届きやすい方法を選び、認知拡大やファンの獲得を目指しましょう。
また、活用するメディアごとにメッセージの内容や表現を最適化することも重要です。
【関連記事】
デジタルマーケティングにおける戦略と戦術とは?
広報戦略とは?事例や必要な理由、実践するメリットを解説
STEP7 効果測定を行い、戦略を継続的に改善する
ブランディング戦略は一度立てたら終わりではありません。戦略の実施後には効果測定を行って、ブランドの浸透度やイメージの変化を確認します。アンケートやインタビュー、アクセス解析などで得られたデータを基に戦略を見直し、常にブラッシュアップを重ねていくことが成功の鍵となります。
ブランディング戦略を成功させるポイント
ブランディング戦略を効果的に進めるには、単に施策を実施するだけでなく、その裏側にある考え方や運用の工夫が欠かせません。ここでは、ブランディング戦略を成功に導くための具体的なポイントを解説します。
- ブランドの一貫性を保つことを意識する
- 定期的なマーケティングリサーチで認知度の変化を確認する
- 顧客を深掘りして新たなニーズを発見する
関連記事:ブランド戦略の成功例を紹介。概要や効果、戦略の立て方も解説
ブランドの一貫性を保つことを意識する
ブランディング戦略では、一貫性のある情報発信が何より重要です。個々の施策で一定の成果が出たとしても、ブランドとしての軸が揺らいでしまうと顧客に覚えてもらえない恐れがあります。ブランドのコンセプトや価値観をしっかりと定義し、それに基づいたメッセージを継続的に発信し続けることで初めて、顧客に強い印象を残せます。
ホームページや広告、SNSなどを活用する際は、ブランドが伝えたい世界観やストーリーに紐づいた情報を発信するように意識しましょう。
定期的なマーケティングリサーチで認知度の変化を確認する
ブランディング戦略の精度を継続的に高めるためには「実際にどの程度ブランドイメージが浸透しているのか」を定期的に確認する必要があります。顧客へのアンケートやインタビュー、自社の営業担当者からのヒアリングなどを通じて、ブランドの認知度や評価の変化を把握しましょう。得られた情報を基に改善点を見つけ出し、必要に応じて戦略をアップデートしていくサイクルを回せば、ブランドの価値をさらに磨き上げられます。
関連記事:マーケティングデータの活用方法~過去から現在、そして未来のデータ活用とは~
顧客を深掘りして新たなニーズを発見する
マスのデータだけでは見えにくい潜在的な価値や本音をつかむためには、顧客を徹底的に掘り下げるアプローチが効果的です。例えば、特定の顧客にインタビューを実施し、深層心理や実際の行動理由を深掘りすれば、自社のブランドに求められる価値や体験が浮かび上がってきます。顧客の声から見えてくる新たな気づきを基にブランドを再構築することで、持続的なブランディングを実現できるのです。
ブランディング戦略では、競合との差別化を意識することが重要
本記事では、企業のブランディング戦略の重要性とポイントを解説しました。
ブランディング戦略は、自社の価値や世界観を計画的に発信し、競合と差別化を図りながら顧客との信頼関係を築くための一連のプロセスです。自社の商品やサービスが提供する本質的な価値を把握した上で、明確なターゲットを設定し、発信情報の一貫性を保つことがブランディングを成功させる鍵となります。
ブランディング戦略を実行するための専門知識やリソースが不足している場合は、経営支援サービス「HiPro Biz」にお任せください。経験豊富なプロ人材がブランディングやマーケティングに関する課題を解決に導きます。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)
