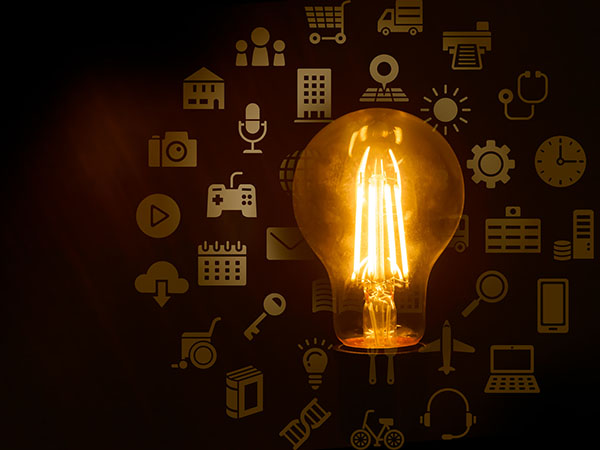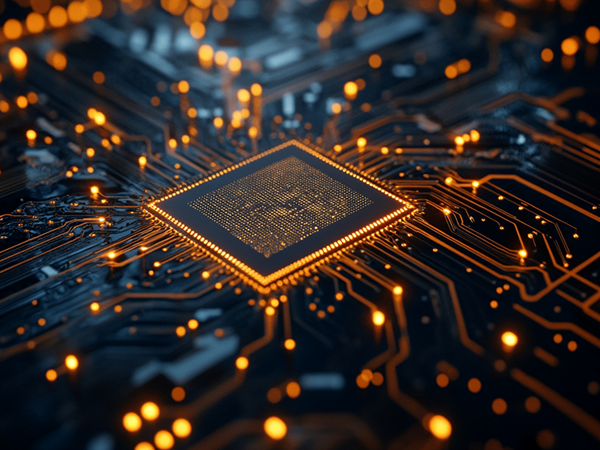【宇宙ビジネス入門】激変する宇宙ビジネス!参入チャンスが広がる今こそ知っておきたいポイントを解説
2025年07月16日(水)掲載
一般的に、宇宙産業というと、JAXA(宇宙航空研究開発機構)や大手重工業、電気メーカーが主体となる巨大事業だというイメージが、日本ではまだ強く残っています。米国がリードする民間の宇宙開発の様相や、衛星データを利用したリモートセンシング技術の進展などに注目していたとしても、宇宙ビジネスを自分事としてとらえている人、企業は少ないかもしれません。しかし、今や宇宙ビジネスは、業界・業種・企業規模を問わず、参入チャンスが広がる領域へと変化しています。
この激変する宇宙ビジネスを理解するには、どのような視点が必要なのでしょうか。航空宇宙事業に豊富な知見をお持ちで、「HiPro Biz」にプロ人材登録をいただいている田代真一氏にお話を伺います。本コラムは、宇宙ビジネスについて概観する入門編です。知識ゼロの状態から一歩二歩踏み出し、宇宙ビジネスを事業戦略の一環としてとらえ直すきっかけとなるでしょう。
▼関連資料はこちら
激変する宇宙ビジネス!非宇宙分野から参入するチャンスはあるのか?
宇宙ビジネス業界の動向

世界の市場規模は約54兆円、2040年には120兆円に達すると予想
経済産業省の資料(※1)によると、世界における宇宙産業の市場規模は2021年の段階で約54兆円。2040年には120兆円に達すると予想されています。米国、ロシア、ヨーロッパに加え、中国やインドの台頭が著しく、たとえばロケットの打ち上げ数で言えば、2020年以降、大幅に増加しています(※2)。
しかし、分野別の売上高比率としては、ロケット打ち上げなどの「宇宙輸送」や「衛星製造」よりも、「衛星用地上機器」と宇宙で取得したデータを利活用する「民間衛星データ利活用サービス」が主流であり、「宇宙ビジネス」の拡大とは、実は地上で行われる「宇宙関連ビジネス」が急激に広がっている状況を反映したものだと言えます。
裾野が広がる日本の宇宙ビジネス、2030年代早期には約8兆円規模に
日本においても2008年に宇宙基本法を施行。これを根拠法として2009年に「宇宙基本計画」(3年ごとに改定)と工程表(毎年改定)を策定し、日本独自の宇宙産業を進展させています。2024年には「宇宙戦略基金(JAXA基金)」が始動し、民間企業や大学における宇宙技術開発や技術実証、宇宙分野への新規参入などを支援する体制が整いました。
日本の宇宙産業の市場を分類すると、大きく3つに分かれます。
- 宇宙機器産業(ロケット、衛星製造等)
- 宇宙利用サービス(衛星通信・放送の提供、リモートセンサーデータ提供等)
- 宇宙関連民生機器・ユーザー産業群(BS/CSチューナー付TVの製造、気象観測、資源開発、農林漁業等の宇宙利用等)
政府は、2030年代早期に向けて、これら宇宙産業の市場規模を急拡大させることを目指しています。掲げられている目標値は、「1.宇宙機器産業」の約3,500億円(2020年)を約6,000億円へ、「2.宇宙利用サービス」と「3.宇宙関連民生機器・ユーザー産業群」を合わせた宇宙ソリューション産業の約3兆5,000億円(2020年)を約7兆4,000億円へ。すなわち、宇宙産業全体の市場規模を約4兆円から約8兆円に倍増させるため、さまざまな施策を打ち出しています(※1)。
衛星データの解析技術が進み、利活用のハードルが下がる
宇宙産業の中で最も裾野が広いのは「3.宇宙関連民生機器・ユーザー産業群」です。特にユーザー産業群は、新しいビジネスを生み出す領域であり、市場拡大に向けて重要な役割を担います。その柱となるのは、地球観測衛星データの利活用ですが、従来はデータを処理するために特殊なソフトウェアを必要とする等、技術的難易度の高さが、十分な民生化を阻んでいました。
しかし、近年はAIを使ったデータ解析技術が開発され、多種多様な業界で利活用が進んでいます。経済産業省でも、衛星データプラットフォーム「Tellus(テルース)」を開発。国が保有する衛星データを無償で公開する機能、商用衛星データやデータ処理アルゴリズム、アプリケーションの売買を可能にするマーケット機能、アプリケーションの開発機能など、さまざまなサービスを提供して新しいビジネスの創出を促しています。
かつて、オフィスアプリケーションが普及してデータの共有化が図られ、一気にデジタル化が進んだ時代がありました。今、それと同じパラダイムシフトが「宇宙ビジネス」で起きようとしています。「宇宙ビジネス」を新規事業開拓の選択肢の一つとする企業は確実に増えていくと予測されています。
※1 出典:「国内外の宇宙産業の動向を踏まえた経済産業省の取組と今後について」(令和6年/経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室)
※2 出典:「宇宙産業における今後の取組の方向性について」(令和7年/経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課)
日本の宇宙ビジネスにおける実状
各業界にイノベーションを起こす宇宙ビジネス
人工衛星に搭載されたセンサーで地球の観測をするリモートセンシング技術は、すでに多くの分野で利活用されています。
例1)農業
広範囲の農地を観測でき、人手を要する監視が不要になります。作物の生育状況と気象情報とを複合的に分析することで収穫時期を把握。土壌分析による適切な栽培地の探索、災害や獣害による被害状況の確認なども可能。トラクターの自動運転等も含めたスマート農業を実現させます。
例2)漁業
リアルタイムで良好な漁場を予測。漁獲の効率化や漁獲量の管理、漁場環境の保全等、持続可能なスマート漁業を実現させます。
例3)林業
衛星データを使って森林の状況を把握して分析。林業従事者が現地まで足を運ぶ労力を軽減します。世界中で深刻化している違法な森林伐採問題にも対応します。
例4)不動産業
衛星写真で広範囲にわたって駐車場や事業用地を探したり、建設中の新築物件を探したり、災害リスク等を分析したりといった不動産情報を自動取得して業務効率化につなげます。
この他、宇宙空間にも持ち込めるスキンケア製品の研究成果を一般商品に応用した「スペースコスメ」や、宇宙空間でしか生成できない高品質なタンパク質結晶を利用した創薬等、多種多様な業界・業種で宇宙ビジネスが展開されています。
日本のスペーステック・ベンチャーと地方自治体
まちと企業が連携して宇宙産業の拠点化を進める
一方、国内でも20年ほど前から、独自の小型・超小型人工衛星を開発、製造する民間企業の起業が続いています。その多くは、優れた研究者が独立する形の大学発ベンチャーや企業からのスピンオフで、2023年から2024年にかけてベンチャー4社が上場しています。また、九州工業大学では、衛星開発プロジェクトのチームを組み、学術機関が運用する小型・超小型衛星の数が世界1位(2014年~2023年)という実績をあげています。
国としても、衛星コンステレーション(多数の小型衛星を打ち上げて一体的に機能させるシステム)を確立して、高頻度での観測を可能にするという課題があり、小型・超小型人工衛星は、量産化に進むと考えられます。
小型・超小型の衛星を開発してきたスペーステック・ベンチャーでよく見られるのは、自治体とタイアップして事業展開している例です。助成金などの形で資金提供したり、地域企業によるサプライチェーンの強化を支援したり、自治体と企業が連携して宇宙産業の拠点化につなげています。
内閣府・経産省では、衛星データの利活用を積極的に推進しようとする13の自治体を「宇宙ビジネス創出推進自治体」として選定しています(※3)。―北海道、茨城県、福井県、山口県、福岡県、大分県、佐賀県、鹿児島県、鳥取県、群馬県、岐阜県、豊橋市、長野市の13自治体。―
たとえば福井県では、県と地元企業11社からなる「福井県民衛星技術研究組合」を組織。東京大学等の協力で小型衛星の研究を続け、「県民衛星」の打ち上げに成功しています。
※3 出典:「地域経済が支える宇宙産業」(令和7年/経済産業省 製造産業局 宇宙産業課)
スペース・テック新規参入のハードル
上記にあげた自治体以外でも、宇宙ビジネスに関心を持つ自治体は数多くあります。宇宙ビジネスを中核とした地元企業の事業拡大・雇用拡大、流入者の拡大、地元学生の地元就職推進等、地方創生を目指す動きと連動しています。
そうした地方自治体においては、たとえば自動車の部品メーカー等が、技術を活かして小型衛星のサプライヤーとして参入したいといった意欲を持つ例もよくあります。とはいえ、既存品の転用は、基本的に宇宙環境に耐えられることを実証する必要があり、新規開発の場合は当然、厳格な設計、製造、検証、品質管理までが求められます。社内体制やルールを新たに構築することが不可欠なことから、短期的にはあまり需要が見込めないと言えます。ハードルは高く、利益は低いという見方もできますが、夢に向かって挑戦する企業が相次いでいるのが現状です。
外部専門家との連携による宇宙ビジネスへの参入
宇宙ビジネスのプロ人材にできることは
今後、企業が新たな事業領域に進出する際、宇宙ビジネスも有力な選択肢の一つとなることは確かです。自社で積極的に計画する場合だけでなく、取引先からの依頼をきっかけに参入するケースもあります。
現時点では宇宙ビジネスへの参入など到底考えられないという企業であっても、宇宙ビジネスを専門とするプロ人材の目から見ると、不可能ではない例が相当数あります。たとえば、バックオフィスの支援業務が中心のソフトウェア企業で、その技術・人材を子細に検討すると、衛星データの利活用領域において多くの可能性があることに気付くケースもあります。
いずれにしても、宇宙ビジネスへの参入は、現実的な可能性や戦略的アプローチを探る段階に入っています。ただし、課題が多く何から始めればよいかわからない場合は、専門知識と経験を有するプロ人材の力を借りることが有効です。
宇宙ビジネスに参入するメリット、デメリットは何か。参入によって新規需要の開拓にチャレンジするのか、「宇宙」に関わること自体を企業価値の向上につなげるのか。こうした観点から、企業ごとに抱える課題を踏まえて、経営支援を行っていきます。
<今回お話を伺ったプロ人材>
(公益財団法人)栃木県産業振興センター 航空宇宙マネージャー、宇都宮市航空宇宙コーディネータ 田代 真一 氏
航空宇宙事業を展開する大手企業の技術本部で、航空機・宇宙機器などの開発、量産設計などに30年以上携わる。国内外での共同開発経験、産官学におけるコネクションを活かし、航空宇宙領域の事業拡大、新規参入を支援するプロ人材として活躍中。
※支援例 宇宙用搭載製品の開発支援/宇宙ビジネスの市場動向調査、勉強会講師/宇宙ビジネス人材育成企画、講座講師/新規参入の相談、支援/宇宙領域のキーパーソン、企業、大学等の紹介/地方自治体の宇宙産業施策の推進支援など
まとめ
宇宙ビジネス業界は急成長を続けており、世界市場は2040年に120兆円規模になると予想されています。日本も2030年代早期に市場を約4兆円から約8兆円へ倍増を目指しています。従来のロケット・衛星製造に加え、衛星データを活用した地上ビジネスが主流となり、AI技術により農業や不動産業など様々な分野で利活用が拡大。国内でも大学発ベンチャーや地方自治体との連携が活発化しています。
特に「月」は、大きなビジネスの場になってきます。50年以上前のアポロ計画は人類が月に降り立つことが目的だったのに対し、今後は月で人が生活して他の惑星へのハブ基地にすることが目的になります(アルテミス計画)。月面生活を見通す新しい宇宙ビジネスは、建設業界、旅行業界、産業機器業界、食品業界、医療業界など多方面の産業に拡張する可能性があります。月面で生活するために必要なすべてのインフラ関連産業に月面ビジネス進出のチャンスがあると言えるでしょう。
経営支援サービス「HiPro Biz」
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)