営業のモチベーションが低下する原因と高める方法を解説
2025年05月21日(水)掲載
営業部門のマネジメントで生じる課題の一つに、チームメンバーのモチベーション低下があります。日々の業務で高いパフォーマンスを発揮し、目標を達成するにはモチベーションの維持が不可欠です。
そこで本記事では、営業のモチベーションが低下してしまう原因とメンバーのモチベーションを高める方法をご紹介します。
チームマネジメントにお悩みの管理者はぜひご覧ください。
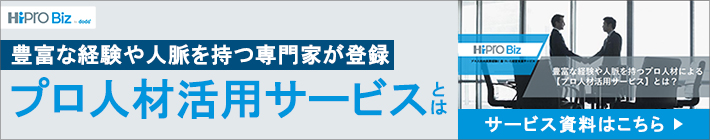
■営業のモチベーションを上げることで期待できる効果
■モチベーション改善が進まない理由
■営業のモチベーションが低下する原因
■モチベーションの種類
■営業のモチベーションを高める方法
■営業力の改善や組織強化なら「HiPro Biz」
■「HiPro Biz」での営業支援の実績
■営業のモチベーション改善には、内発的モチベーションを引き出すことが大切
営業のモチベーションを上げることで期待できる効果
「チーム内のモチベーションを上げたい」と考えてはいるものの、それによってもたらされる詳細なメリットまではイメージしきれていない方もいるのではないでしょうか。具体的な効果を知ることで、モチベーションを上げる目的がより明確になります。
以下では、営業のモチベーションを上げることで期待できる変化を紹介します。
営業活動の生産性と売上が上がる
チーム内で高いモチベーションが維持されることによって営業生産性が上がり、それに伴い売上の増加も期待できます。
業務に対して前向きな気持ちがあれば「より良い結果を出すために試行錯誤してみよう」という意思が生まれ、一人ひとりが高い熱量で業務に取り組むことが考えられます。そうなれば、営業生産性はおのずと向上するでしょう。
そして、営業生産性の向上は売上の増加に直接寄与します。一人のモチベーションが周囲のメンバーにも伝わり、チーム全体の営業生産性が向上することで、売上の増加へとつながるのです。
社員のエンゲージメントが上がる
営業のモチベーションが上がることで、社員と自社の信頼関係、すなわちエンゲージメントが向上します。
一定のモチベーションで営業活動に向き合うメンバーであれば、会社に対し愛着や貢献意欲を抱いていることが考えられます。また、チーム内で個々人のモチベーションが影響し合い、一人ひとりが高い志を抱く環境であれば、団結力も向上していくでしょう。
チーム単位での信頼関係が形成されることで、会社へのエンゲージメントも向上していくことが期待できます。
離職率が低下する
営業のモチベーションが高いメンバーが集まれば、離職率が低下する可能性があります。
モチベーションが高いということは、つまり仕事にやりがいを感じている状態だということです。メンバーがやりがいを感じており、なおかつ前述のように会社へのエンゲージメントが高い状態であれば、簡単に離職しないことが考えられます。
チーム全体のモチベーションを維持し、高い視座で営業に向き合うメンバーを、可能な限り長く定着させることが理想的です。
モチベーション改善が進まない理由
「チーム内のモチベーションを上げたくとも上げられない…」とお悩みの担当者もいるのではないでしょうか。マネージャーがモチベーション改善を図っているにもかかわらず実現しない場合には、以下のような理由が考えられます。
- マネージャーと現場の間で熱意にギャップがある
- 改善の目的がチーム内に浸透していない
- 改善案が現実的ではない
モチベーション改善に向けて何らかのアクションを起こしたとしても、その施策の必要性や目的が現場で認知されていなければ、想定通りにはなかなか進まないでしょう。また、モチベーション改善のための施策が現場に合っていない、あるいは優先順位が不適切などの理由で、現実的でない可能性も考えられます。
まずは現状の課題と、それを改善する目的を現場にしっかりと伝えましょう。具体的な改善案については、本記事の後半でお伝えする「営業のモチベーションを高める方法」もご覧ください。
営業のモチベーションが低下する原因
当初はある程度のモチベーションがあったものの、営業活動を続けるにつれ、モチベーションが低下してしまうケースもあるでしょう。その場合は、以下のような原因が考えられます。
実現が不可能な目標設定
営業には目標が必ずありますが、その目標設定が実態に対し高すぎるとモチベーションの低下を招きます。
初めから実現が難しいほど高い目標を設定すると、「どうせ無理だ」とあきらめてしまい、挑戦する意欲が湧かないことがあります。そのため、目の前の目標に対する意欲も低下し、結果として仕事そのものへのモチベーションも下がる可能性があります。
社内でのサポートや情報共有が不十分
本人の意欲に対して適切なサポートが提供されなければ、メンバーは「自分は会社から期待されていない」と感じ、モチベーションが低下することが考えられます。入社当初に「このように活躍したい!」というビジョンがあったとしても、それを実現できる環境でなければやりがいを感じられなくなってしまうでしょう。
また、サポートのほかに情報共有が不十分な場合も同様に、モチベーションに影響する可能性があります。自分が知っているべき情報が適切に共有されていなければ、孤独感が芽生え、やはり「会社から求められていない」といった考えに発展してしまいます。
組織内の風通しの悪さ
上司の顔色をうかがわなければならない、あるいは自分の意見がすぐに否定されるといった、いわゆる「風通しの悪い」環境もまた、モチベーションが低下する要因となります。自分の言動がいつ否定されるかわからないような環境では、仕事上の小さな疑問や困りごとも相談できず、孤立感を深めてしまうでしょう。
そのような状態となっては、会社への帰属意識も生まれず、モチベーションを維持できなくなります。
業務過多による多忙
営業職は多忙な傾向にありますが、個人のキャパシティに対して業務量があまりにも多いと、精神的な余裕や時間的な余裕が失われてしまいます。一生懸命はたらいてもタスクが終わらず、目標を達成できない日々が続けば、モチベーションに影響します。
特に、長時間の残業や休日出勤が必要になるほど多忙な環境は、非常に危険です。多忙によりワーク・ライフ・バランスが保てなくなれば、モチベーションが下がるだけでなく、大きな精神的ストレスとなります。
このような状況を適切に改善できなければ、離職率が上がり、人材が定着しにくくなってしまうことも考えられます。
あいまいな評価基準
社内の評価基準も、モチベーションに直結します。成果に対し「適切な評価がなされていない」と感じられるような環境であれば、不満や不信感につながり、モチベーションが下がってしまうことは明白です。
特に人によって評価基準が異なるように見える状況であればなおさらでしょう。
モチベーションの種類
実は、一口に「モチベーション」と言っても2つの種類があります。「内発的モチベーション」と「外発的モチベーション」は性質が異なるので、営業のモチベーションを引き上げるためにもそれぞれの特徴を把握しておきましょう。
内発的モチベーション
内発的モチベーションは「内発的動機づけ」とも呼ばれることがあります。個人の興味や関心や欲求といった、内面の感情から引き起こされるモチベーションのことです。
例えば、「目標を達成するために、より高いスキルを身につけたい!」「もっと案件を受注して、会社に貢献したい」といった思いが内発的モチベーションとして挙げられます。次に紹介する外発的モチベーションと異なり、報酬や評価などの外的な要因に影響されず、自分自身の感情が起点となります。
外発的モチベーション
外からの報酬や評価をきっかけに生まれるモチベーションが、外発的モチベーションです。「外発的動機づけ」と呼ばれることもあります。
企業での活動に当てはめると、ボーナスや昇進、社内での表彰や称賛によって生まれる「もっと頑張ろう」という気持ちが該当します。
なお、外発的モチベーションは一時的に効果を発揮することはあるものの、基本的にはあまり長続きしません。そのため、外発的モチベーションのみに頼るのではなく、内発的モチベーションを基本とした上で適切に意欲を引き出すことが大切です。
営業のモチベーションを高める方法
営業のモチベーションを高める方法は、一つではありません。以下で紹介する方法をご覧ください。
実現可能な目標を設定する
目標の規模がチームや個々人のレベルに即しておらず、実現可能性が低いことが原因でモチベーションが下がっている場合は、まずは目標を見直すところから始めます。チーム全体の目標はもちろん、個々人の営業スキルに応じて個別に目標を設定しても良いでしょう。
このとき、メンバー自身が目標を決めるという方法もあります。自分で目標を決めることは、内発的モチベーションと直結するためです。
現時点でのチーム全体のレベルを基準とした上で、現実的な目標を設定することがモチベーション改善の第一歩です。
チーム内でナレッジシェアを行う
成功例や業務を円滑に進めるコツなどのナレッジは、ぜひ共有するとよいでしょう。スキルの高いメンバーが持っている情報を知る機会があれば、「自分も試してみよう!」という気持ちを促し、内発的モチベーションを生み出せるかもしれません。
また、ナレッジを共有するために横連携の仕組みを整えれば、チーム内での交流が活発になり、チームへの帰属意識が高まることも期待できます。組織への愛着が育つことでもまた、「この組織に貢献したい」という内発的モチベーションが生まれるでしょう。
営業のロールプレーイングを行う
メンバーのスキル不足がモチベーション低下の要因となっているのであれば、ロールプレーイングを実施しスキルを磨く機会を提供することも一つの手です。
経験の浅いメンバーが、マネージャーや経験豊富なメンバーを相手に商談や提案を模擬的に演じます。その上で適切なフィードバックを受けることで、自身の長所や改善点が明確になり、自信を持って営業活動に向き合うことができるでしょう。
ロールプレーイングという実践的な教育によって、営業活動の不安が解消されれば、業務へのモチベーションも高まることが期待できます。
意見が言いやすく、風通しの良い環境を整備する
営業職は業務の性質上、個人での活動がどうしても多くなってしまいます。しかし、だからこそ風通しの良い環境をつくり、チーム内でのコミュニケーションを意識的に増やすことが理想的です。
立場に関係なく、誰もがオープンなコミュニケーションを取れる環境を目指しましょう。そのためには、マネージャー層や長く所属しているメンバーが日々の振る舞いを意識することはもちろん、新たな施策を試すという手もあります。
例えば、社内SNSを導入して気軽にコミュニケーションを取れる環境を整えたり、アンケートを実施して一人ひとりの意見を吸い上げたりするという方法があります。
チームビルディングを行う
営業部門として、チーム全体の強化を図りモチベーション向上を目指すのであれば、チームビルディングも非常に重要です。
チームビルディングとは、メンバー一人ひとりの個性に焦点を当て、能力を最大限に発揮するために、環境を整備する取り組みのことです。具体的には、チーム編成の段階から人間関係や能力のバランスを考慮し、それぞれの役割を明確にすることなどが挙げられます。
チームの環境を整えたら、イベントやワークショップを通じてメンバーの相互理解を深めることも欠かせません。
各メンバーが能力を発揮できる環境が整えば、チーム全体のパフォーマンスが向上します。それにより、営業成績が上がればモチベーションも生まれるでしょう。
業務DX化を行う
近年、よく耳にする「DX化」は営業部門も無関係ではありません。
業務のDX化によって、業務効率が向上するだけでなく、メンバーのモチベーション改善も期待できます。なぜなら、業務上の小さな手間やストレスが解消されることで、メンバーが業務に集中しやすくなるためです。
生産性が改善し、限られた時間を業務に充てられるようになれば、モチベーションの向上にもつながると考えられます。
例えばSFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)を導入し、営業活動の可視化および効率化を図れば、これまでに時間がかかっていた社内会議や報告の時間が短縮できます。これにより、重要な業務に集中できる時間が増えれば、モチベーション向上も期待できるでしょう。
営業の業務DX化についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
業務改善・効率化する
上述のDX化と関連する事項ではありますが、業務改善も非常に重要です。
営業職は一つの業務を行えば良いわけではなく、業務量が多いことが一般的です。その中には、営業活動と無関係の業務が含まれている場合もあります。
業務過多で残業時間が多いメンバーに対しては特に、業務の棚卸しを行い、営業活動と関係のない業務は削減しましょう。必要な業務に集中できる時間を確保することが、モチベーションの向上につながります。
キャリアパスを伝える
キャリアパス、つまり「現在の業務が、将来の社内および市場でどのように役立つのか」をメンバーに伝えていない場合は、適宜伝えていきましょう。
自身の仕事が、顧客や自社、ひいては社会にとって重要であることがわかれば、メンバーはやりがいを感じられ、内発的モチベーションを生み出します。また、キャリアパスが明確になることで「こんな営業担当者になりたい」という目標、つまりは内発的モチベーションが生まれることも考えられます。
成果やプロセスを褒める
自身のはたらきぶりが評価されることは、外発的モチベーションに直結すると言っても過言ではありません。特定のメンバーの成果やプロセスが素晴らしいと感じられる場合には、マネージャーから感謝や称賛の言葉を伝えましょう。
ポイントは「対応時の、この言葉が良かった」「こういった姿勢が周囲に良い影響を与えている」といったように、具体的な言動を引用することです。これにより、メンバー本人は自分の振る舞いに自信を持ち、モチベーションを高められます。
根拠のある評価を行う
上述のように称賛や感謝の言葉をかけることはもちろん大切ですが、その言葉に説得力を与えるには、人事評価制度上でも適切に評価することです。
人事評価の結果もまた、外発的モチベーションに関係します。評価を行うにあたっては、基準が明確であり、なおかつ公平であることが非常に重要です。
評価は明確な基準に沿って実施し、根拠をきちんと伝えましょう。
目標達成に応じたインセンティブを与える
評価と関連して、インセンティブを与えることもまた、外発的モチベーションに影響します。
なお、インセンティブも評価と同様に、チーム内で基準を明確にすることが前提となります。営業職は数字という客観的な目標を立てられるので、目標に応じたインセンティブも決めやすいでしょう。
適切に休暇が取れる仕組みを整える
メンバーが適切に休める環境を整えることも大切です。過剰な残業や休日出勤は可能な限り改善することは大前提とした上で、リフレッシュ休暇や長期休暇などの制度を設けても良いでしょう。
ワーク・ライフ・バランスは仕事の内発的モチベーションに直結する要素であるため、現状を踏まえて制度や労働環境を適宜見直すことが理想的です。
1on1ミーティングを実施する
上司と部下が一対一で行う「1on1ミーティング」の実施も、モチベーション改善のきっかけとなります。
例えば、メンバー自身が営業に対する悩みや課題を1on1ミーティングの場で上司に共有し、アドバイスを得られたとします。そのアドバイスを実践し、成功体験を得られれば、悩みが一つ解決し、業務に対して前向きに取り組むことができるでしょう。
営業力の改善や組織強化なら「HiPro Biz」
「適切な目標が設定できず、チームメンバーのモチベーションがなかなか改善しない」「業務が属人的になってしまっていて、若手メンバーのモチベーションを引き出せるような教育ができていない」
このようにお悩みであれば、パーソルキャリアの経営支援サービス「HiPro Biz」にご相談ください。
「HiPro Biz」は、経営課題に解決に取り組む企業向けに、経営層・CxO・エキスパートクラス等、高度な課題を解決できるプロ人材と共に解決に導くサービスです。営業でお悩みの企業に対しては、現場を長年経験したプロ人材がメンバーの育成や営業の戦略立案、販路開拓などを支援します。
「HiPro Biz」での営業支援の実績
「HiPro Biz」では、メンバーのモチベーション向上だけでなく、企業の営業に関するさまざまな課題へのアプローチが可能です。
「HiPro Biz」に営業の課題をご相談いただいた企業の事例を紹介します。
▼営業支援「HiPro Biz」の導入事例
与信管理規定の大胆改定。海外市場におけるリスクヘッジで新規販路開拓のスピード感が飛躍的に上昇
営業のモチベーション改善には、内発的モチベーションを引き出すことが大切
今回は、営業のモチベーションを改善に導くためのポイントをお伝えしました。
モチベーションには2つの種類があり、効果を長く続かせるにはメンバー自身の意欲による内発的モチベーションを引き出すことがポイントとなります。そのためには、目標の設定やチームビルディングといった環境の整備が非常に重要です。
本記事の内容を参考に、自社に合う改善方法を実践してください。
なお、自社での改善が難しい場合や、メンバーのモチベーション以外でも営業で課題を抱えている場合は、「HiPro Biz」にご相談ください。
営業や業務改善に精通したプロ人材が、営業課題の改善をサポートします。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)




