営業を効率化する8つの方法と具体的な手順やツール活用方法も解説
2025年05月20日(火)掲載
- キーワード:
企業の売上拡大のためには、効率的な営業活動が必要不可欠です。しかし、その重要性を理解していても、効率の低下を招いている原因や改善策がわからなければ、営業効率を高めることは難しいでしょう。
そこで本記事では、営業効率が低下する原因を洗い出し、その改善策として有用な8つの方法を解説します。「営業効率の低さが慢性的な課題」というお悩みがある方は、ぜひご覧ください。
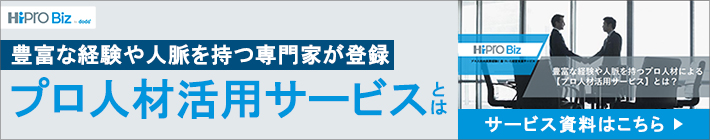
■営業の効率化とは?
■営業効率が低下する原因
■営業の効率化を図るための手順とポイント
■営業を効率化するための方法8選
■営業を効率化するためのツール
■営業支援ツールを導入するときのポイント
■自社の状況や目的に合った施策を実施することが、営業効率の向上につながる
営業の効率化とは?

営業の効率化とは、営業活動にかかる時間や労力の中から無駄な部分を省き、より効率の良い営業活動を実現するための試みです。たとえば、報告書作成やメールの送付といった付帯業務の時間短縮などが該当します。
営業活動の効率が改善すれば、より多くの新規顧客にアプローチできるようになるほか、既存顧客に対しても手厚いサポートを提供できます。営業の本質的な業務に割ける時間やリソースを多く確保し、売上を拡大させることが、営業の効率化の大きな目的といえるでしょう。
営業効率が低下する原因
そもそも、なぜ営業効率は低下するのでしょうか?考えられる原因としては、主に以下の5つが挙げられます。
目標が明確化されていない
営業効率の低下を招くと考えられる原因の一つが、「会社全体の目標が明確になっていないこと」です。
営業効率の良否を判断するためには、目標に対する到達度、つまり理想と現状のギャップを把握しなくてはなりません。しかし目標が明確に定まっていなければ、そのギャップを把握することすら難しく、改善すべき箇所も洗い出せません。そのため、必然的に営業効率も低下の一途をたどってしまいがちです。
担当者が案件の進捗を管理できていない
各案件の担当者が進捗を適切に管理できないことも、営業の効率化を阻む原因の一つになりえます。進捗管理が不十分だと、顧客に対して効果的にアプローチできず、成約につながる可能性が減ってしまうためです。
なお近年は、市場競争の激化や人材不足などの影響を受けて、営業担当者一人当たりが受け持つ案件の数が増加傾向にあります。進捗管理にかかる工数も増えており、担当者一人ひとりの努力だけでは課題を解決できないことも少なくありません。このような状況に対処するためにも、必要に応じて後ほど紹介するツールなどを活用してみましょう。
コア業務に集中できていない
報告書作成やデータ入力などの付帯業務に追われている状況では、本来時間を割くべき顧客とのコミュニケーションなどのコア業務に注力することが難しくなります。その結果、営業活動全体の効率が低下し、成約率や既存顧客の満足度も下がってしまう要因にもなりかねません。
必要性の低い会議や打ち合わせが多い
コア業務に集中できない別の要因として、必要性の低い会議が多いことも挙げられます。
営業活動に必要な会議であれば問題ありませんが、惰性的に行われている会議も存在するかもしれません。特に、毎週や毎月のように行う定例会議は、そのような状態に陥っている可能性があります。
そうした会議については「ここにいる全員が本当に必要なメンバーなのか」「チャットやメールでの報告で事足りないか」といった観点で必要性を再検討してみましょう。また、必須の会議に関しても、事前に資料を配布する、取り上げる議題を絞るなど、進行面での工夫を行い、開催時間を短縮できると理想的です。
長時間労働が当たり前になっている
働き方改革が進んでいる昨今ですが、「とにかく長時間働いて成果を出す」という考え方が残っているケースもあります。
たとえそれにより本当に成果が出ていたとしても、あまりにも多くの時間と労力を割いていては効率的とはいえません。労働時間全体を見直し、「作業効率を上げてコア業務に集中する」「無駄な会議を減らす」といった点を改めて意識し、生産性を高めることが重要です。
営業の効率化を図るための手順とポイント
前項で説明したような営業効率を妨げる原因を解決するため、以下のプロセスに沿った対応を実施してみましょう。各プロセスの対応ポイントもあわせてご紹介します。
目的やゴールの設定
最初に、営業の効率化で達成すべき目的やゴールを設定しましょう。目的が明らかになれば、その実現のために必要となる戦略や具体的な改善策を検討できます。
なお、目的を設定する際は、可能な限り具体的な数値を掲げることが望ましいでしょう。定性的な目的だけでは成果の有無を明確に判断することが難しく、効率化の試みが頓挫してしまう可能性が高いためです。「売上の〇%増加」「営業活動にかかる費用の〇%削減」「営業担当者の稼働時間を〇時間削減」といったように、定量的な指標を設定することが重要です。
関連記事:OKRの目標設定とは?組織で成果を上げるためのポイントを解説
業務全体の整理
続いて、自社全体の営業業務の内容を一度整理します。
管理職や上長がメンバーの業務を漏れなく把握できていれば理想的ですが、中には案件を進める中で各担当者だけが把握している業務もあるでしょう。そういったものも含め、全ての営業業務を洗い出し、現場の実態を正確に把握することが重要です。業務の実態を包括的に把握できれば、課題も自然と浮かび上がってくるでしょう。
業務課題の把握
営業業務を整理できたら、次は課題の洗い出しへと移ります。
各業務に要する時間やコスト、進め方などを把握した上で、最初に設定した目的とギャップがある部分を明確にしていきます。特に「案件の管理方法」「社内の情報共有体制」「コア業務以外に割いている時間」などは効率化に直結しやすいポイントなので、重点的に確認してみましょう。
改善すべき業務と優先度の設定
課題が明らかになった後は、その課題がすぐ改善すべきものなのかどうか検討しましょう。
まずは、洗い出した課題に対する改善策とその効果、そして実施に要するコストなどを基に、改善対象となる業務を選別します。「最初に設定した目的の達成につながるか」「実現性はあるか」の2点のバランスを考慮することが、このプロセスでは重要です。
改善対象となる業務が決まったら、さらにそれらを「すぐに対応するもの」と「計画的に対応するもの」の2種類に仕分けます。全ての課題を一度には解決できないため、重要度の高いものから優先的に対応しましょう。
施策の詳細とスケジュールの設計
改善対象となる業務が決まり次第、改善施策の詳細を詰めていきましょう。施策の具体的な内容やアサインする担当者、導入するツールなど、実施にあたって必要な要素をこの段階で一通り決めていきます。施策の開始後に社内で混乱が起きないよう、関係各所の役割を明確にするなどのフォローも必要不可欠です。
また、施策の検討と同時に、実施スケジュールも決める必要があります。「業務の効率化」という目標を達成するためには、無駄のないスケジュール設計が不可欠です。施策の各フェーズに要する期間を算出し、さらにボトルネックになり得る部分も洗い出しておけば、最適なスケジュールを設定できるでしょう。
施策の実施と効果測定
スケジュールまで決定したら、いよいよ改善施策の実施です。
実施後は、施策の効果測定を継続的に行い、必要に応じて施策の見直しや調整をすることが重要です。目的としていた指標で改善が見られなければ、施策内容の修正や追加施策の検討などを行います。
また、定量的に定めた指標で効果測定をするだけでなく、営業担当者からの現場目線のフィードバックも確認しましょう。「実際に業務は効率化されたのか」「負担は減っているか」「施策の内容で見直すべき点があるか」などをヒアリングし、以降の取り組みに反映していきます。このように効果測定と修正を繰り返し、施策をブラッシュアップしていくことが、営業効率化には欠かせません。
営業を効率化するための方法8選
上記で解説したプロセスを踏まえて、ここからは営業の効率化を実現するための具体的な方法を、短期施策、中期施策、長期施策の3種類に分けてご紹介します。
短期施策
ここで紹介する2つの施策は、大がかりな準備が不要ですぐに実施可能です。そのため、短期間で成果を出す必要があるケースに適しています。
1.メールチェックなど付帯業務の時間を短縮する
コア業務以外となる付帯業務の時間削減は、シンプルでありながら一定の効果が見込める取り組みです。報告書の作成やメールチェックなどに充てていた時間を短縮し、その時間を商談の準備や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に回せれば、より営業効率を高められるでしょう。
付帯業務を効率よく終わらせる具体案としては、資料のテンプレート化や作業の自動化などが挙げられます。「自動化」と聞くと大規模な取り組みが必要に思えるかもしれませんが、個人レベルでもExcelのマクロなどを活用すれば、比較的容易に作業の自動化が可能です。個々人が短縮できる時間は微々たるものかもしれませんが、それが全社的に行われれば、トータルで相当な時間短縮となるでしょう。
関連記事:営業生産性アップを目指す具体的な企業事例と効果的な施策を紹介
2.アウトソーシングサービスを利用する
一部の業務をアウトソーシングサービスなどへ外注すれば、社内のリソースを使うことなく、すぐに業務の効率化に取り組めます。
たとえば、付帯業務の一部を外部に任せて、自社の営業担当者には顧客との商談や受注活動などのコア業務に注力してもらう、といったかたちで効率化を図れます。特にダイレクトメールの送信、データの入力や集計などは、担当者が変わっても品質に差が出にくいと考えられるため、外部に委託しやすい業務といえるでしょう。
関連記事:営業顧問とは?導入するメリットと依頼方法や報酬体系、注意点を解説
中期施策
改善活動にある程度の時間をかけられるのであれば、以下で紹介する中期施策も検討してみましょう。
3.営業に関する情報やナレッジをシェアする
プレゼンテーションの手法やコミュニケーションの取り方、また顧客ごとの特徴など、営業に関するナレッジを集約することは、営業の効率化を実現する上で非常に効果的です。
営業の業務は属人化しやすい傾向があり、担当者ごとに独自のスキルやノウハウを習得していることが少なくありません。そういった現場で活きるナレッジをほかの担当者にも共有できれば、会社全体の営業力が向上し、効率よく営業活動を進められるようになるでしょう。営業マニュアルの作成や情報交換会の実施といったナレッジ共有の場づくりに積極的に取り組み、自然とノウハウが共有される環境を整備することが重要です。
【関連記事】
きちんと「機能する」ナレッジシェアリングとは?陥りがちな失敗要因とその解決策
ナレッジマネジメントとは?有効な手法や導入方法、成功のポイントを解説
4.営業支援ツールなどを導入する
営業の効率化を目指しつつ社員の負担も減らしたいのであれば、営業支援ツールの導入も検討してみましょう。
近年はマーケティングや顧客情報の管理、分析などさまざまな用途に特化したツールが出てきています。自社の状況に合わせて適切なツールを導入すれば、営業の効率化を果たせるだけではなく、営業担当者の業務負担削減にも期待がもてます。
ツールの種類や具体的な用途などは本記事の後半で解説するので、引き続きご覧ください。
関連記事:営業DXとは?必要な理由や進め方、成功例・失敗例をそれぞれ解説
5.生成AIを活用する
近年は、営業支援ツールだけではなく生成AIを活用している企業も増えつつあります。
これを活用すれば、営業担当者の時間を極力使わずに、プレゼンテーションの原稿や資料に差し込む画像などを作成できます。
ただし、利用に際しては一定の知識が必要となるため、事前の学習期間は必要となります。また、生成AIからアウトプットされた成果物の確認やそれを実際に活用するかどうかの判断は人間が行わなくてはなりません。あくまでもサポートツールとして捉え、正しく活用することが求められます。
長期施策
以下の3つの施策は長期的に取り組む必要がありますが、営業効率に関わる課題を抜本的に解決できる可能性を秘めています。実施に向け割り当てられる担当者やスケジュール面などの問題をクリアできるのであれば、積極的に検討してみましょう。
6.情報管理の体制を一元化する
営業関連情報を一元管理できる体制を整備することで、業務の効率を大きく高められます。
顧客情報や過去の商談履歴などがチームごと、あるいは担当者ごとの管理下にあると、その情報を探す際に一定の時間と労力を要します。これは業務効率の低下のみならず、スピーディーな対応ができないことにより大きな機会損失にもつながりかねません。
営業に関する情報が一元管理できていれば、このようなリスクも少なくなるため、結果として営業の効率化にもつながります。一元管理可能な体制や仕組みを整えるにはそれなりの期間が必要となりますが、得られる効果もその分大きいものになるでしょう。
7.問い合わせフォームや資料ダウンロードページを改善する
問い合わせフォームやダウンロード資料といった、Web上で展開するマーケティング施策、コンテンツの導入や改善も検討してみましょう。
これら取り組みが最適に実施できれば、こちらからアプローチすることなく「この商品やサービスは自社に適しているだろうか」という観点を、将来の顧客企業となりうるユーザー側でも検討してもらえるようになります。
これにより、自社に対して興味や関心があるユーザーからの問い合わせのきっかけづくりや、新規顧客を獲得する機会にもつながります。また、ユーザーからの問い合わせであるためサービスに対する一定の意欲や熱量にも期待ができ、商談へ進める可能性も高まることで結果的に営業効率向上にもつながります。
8.営業担当者の業務意識を改善する
営業担当者の業務意識改善も非常に重要です。そもそも「コア業務に割く時間を少しでも増やしたい」「もっと効率的に業務を進めたい」という意識が担当者自身になければ、どのような施策を実施しても営業の効率化は見込みにくいでしょう。
営業担当者に自分事として業務改善に取り組んでもらうためにも、営業の効率化の目的や対応すべき事項などは、重要度の高い共有テーマとして周知することが重要です。
すぐには意識改善につながらないかもしれませんが、コンスタントに周知を続けていれば次第に担当者個々の中でも意識変化が表れ、施策の取り組み意欲向上にもつながるのではないでしょうか。
営業を効率化するためのツール
先述の通り、営業支援ツールを活用すればより効率的な業務改善につながります。代表的なツールを以下で解説するので、改善活動へ取り組む際にぜひご参考ください。
MAツール
MA(Marketing Automation)ツールは、その名の通りマーケティングに関する業務を効率化するためのツールです。MAツールを活用すれば、たとえば自社のWebサイトに訪れたユーザーの行動を分析し、成約の見込みがあるリードの獲得や育成にも寄与できます。そのほかにも、見込み顧客リストの管理やレポートの作成など、さまざまな機能が備わっており、営業活動を多面的にサポートしてくれます。
関連記事:マーケティングツールとは?課題に合わせたツールの選び方を紹介します。
SFAツール
営業活動の自動化や効率化を図る上で有用なツールとしては、SFA(Sales Force Automation)ツールも挙げられます。
先ほど紹介したMAツールがリード獲得などのフェーズで効果を発揮するのに対して、SFAツールは主にリード獲得後の営業活動をサポートします。営業担当者の活動記録、案件や商談の進捗など、成約に至るまでの活動に関するさまざまな指標の一元的な管理が可能で、申請や承認作業やタスクの割り当て作業なども自動化できるため、業務スピードの改善も見込めます。
このように、SFAツールはMAツールとは役割が異なるので、どちらかだけを導入するのではなく併用して連携することも検討してみましょう。
CRMツール
成約が済んだ顧客と良好な関係を築くために必要となるツールが、CRM(Customer Relationship Management)ツールです。
CRMツールでは、顧客の基本情報や購買履歴、問い合わせ状況などを一元的に管理します。それらの情報を基に営業担当者が分析をし、顧客満足度をさらに高めるための施策を実施する、というのが理想的なパターンです。
CRMツールもMAツールやSFAツールとはできることが異なるので、単体で活用するのではなく、別の種類のツールと組み合わせての導入を検討してみましょう。
関連記事:顧客管理とは?CRMシステムを活用する際のポイントを解説
生成AI
すでにご紹介した通り、生成AIを活用することでも業務の効率化を図れます。
生成AIで対応できることとしては、原稿や画像の作成のほかにメールの自動返信なども挙げられます。また、近年ではSFAツールにAIが搭載されたこともあり、顧客情報を管理するだけにとどまらず、その情報を基にした提案をツールから受けることも可能です。
関連記事:営業におけるAIの活用とは。AIを搭載した営業支援システムの効果について。
オンライン会議システム
社内ミーティングや顧客との商談で生じる時間的および金銭的コストを削減したいなら、オンライン会議システムを活用しましょう。地理的な条件に縛られず移動時間そのものを削減できるため、それまではアプローチできなかった顧客層にも接触可能となります。
なお、最新のオンライン会議システムには、デジタルホワイトボード機能や自動文字起こし機能などが搭載されていることが一般的です。それらを利用すれば、会議中のディスカッションや、議事録作成業務も効率化できます。
日程調整ツール
「打ち合わせの日程調整に時間を取られてしまう」という声が担当者から上がっているなら、日程調整ツールの導入も検討してみましょう。会議や商談の日程を自動で調整してくれるため、営業担当者の業務負担を大きく削減できます。
日程調整に費やしていた時間を、資料のブラッシュアップや顧客の分析などに充てれば、商談が成功する確率が高まり、結果として売上の創出へとつながるでしょう。
営業支援ツールを導入するときのポイント
さまざまなツールを紹介してきましたが、これだけ種類があると、自社に合ったものを選ぶ段階で時間がかかってしまうかもしれません。そこでここからは、営業支援ツールを選ぶ際に重視したいポイントをご紹介します。
求めている機能があるか
まずは、改善活動に必要な機能があるかどうかを確認しましょう。
業務改善に取り組む上では、最初に設定した目的の達成を目指して施策を実践することが重要となります。よってツールを選定する際にも「このツールで本当に目的を達成できるのだろうか?」という観点を持つ必要があります。
ツールごとの機能や利点の違いを入念に比較し、自社の業務改善活動に合ったものを選びましょう。
サポートが充実しているか
ツールを導入してからしばらくの間は、「操作の仕方がわからない」「何ができるのか把握していない」といったケースが予想されます。そのような状況を迅速に解消するためにも、導入後のサポート体制が充実しているツールを選びましょう。
確認が必要な点としては、問い合わせ方法の種類(メール、電話など)や対応までのスピード、そのほかの制限事項の有無などが挙げられます。また、より確実に現場へツールを浸透させたいのであれば、導入時にトレーニングを実施してくれるサービスがあるかどうかも確認するポイントになります。
自社のツールやシステムとの連携が可能か
すでに何らかのツールを導入している、あるいは複数のツールを同時に導入する場合には、連携機能の有無についてもチェックしておきたいところです。
特にMAツール、SFAツール、CRMツールの3種は、相互連携によって営業活動をトータルサポートできます。リード獲得から顧客管理、成約後のサポートまでを一気通貫で実施できれば、業務の大幅な効率化が図れるので、連携可能であるかもサービス選定の重要なポイントになります。
このほかにも、日程調整ツールとチャットツールの連携など、確認が必要なポイントは数多くあるため、検討漏れがないよう、事前に検討項目をリスト化しておきましょう。
自社の状況や目的に合った施策を実施することが、営業効率の向上につながる
今回は、営業効率を高める8つの方法や、活用ツールなどをご紹介しました。
会社としての目標が定まっていない、または担当者がコア業務に注力できていないなど、営業効率の低下を招く原因にはさまざまなものがあります。「自社の営業のどこに課題があるのか」「優先すべき課題はどれか」といったポイントを明らかにした上で、最適な施策を実施していくことが重要です。
自社だけでの対応に不安が残るのであれば、営業領域に精通したプロ人材が多数登録する「HiPro Biz」の活用も、改善への取り組みのひとつの選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。
営業活動に関するお悩みをお持ちであれば、まずは一度ご相談ください。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)




