組織課題の見つけ方や解決に役立つフレームワーク5選を紹介
2025年05月02日(金)掲載
企業として成長するためには、まず自社内に存在する「組織課題」を解決しなくてはなりません。しかし、そうした課題はそもそも顕在化していないことがあり、ノウハウなしで解決することは困難を極めます。
そこで本記事では、組織課題を発見する方法を押さえた上で、解決にあたって有用なフレームワーク5選を紹介します。会社の停滞感を打破したいとお考えの経営者や管理者の方は、ぜひご覧ください。
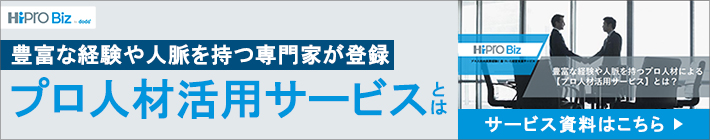
■組織課題とは?
■組織課題の解決はなぜ必要?
■組織課題としてよくある具体例
■組織課題の見つけ方
■組織課題の解決方法と流れ
■組織課題の解決に使えるフレームワーク
■組織課題の解決のために管理職が意識すべき点
■人材・組織開発なら「HiPro Biz」
■組織課題を解決するためには、社員が一丸となって施策に取り組むことが重要
組織課題とは?
組織課題とは、組織が何らかの目標を達成する、または理想像に到達するにあたって障害となる課題のことです。
こうした組織課題は、会社を取り巻く環境や業界の情勢とともに変化します。そのため、自社の課題を常に把握し、臨機応変に対応する必要があるのです。
なお、組織課題は顕在化しているか、潜在化しているかの違いで2種類に分けられます。それぞれの詳細は以下の通りです。
顕在化している組織課題
組織課題の中には、経営層や社員が認識できている、つまり「顕在化」している課題が存在します。具体例としては以下が挙げられます。
- 明確な人材不足
- 高い離職率
- 業績の悪化
顕在化している組織課題は、解決に向けての取り組みがすでに進んでいる、またはその原因が明らかになっていることが珍しくありません。そのため、後述する潜在化している組織課題と比較すると、解決しやすい傾向にあります。
潜在化している組織課題
「潜在化」している組織課題とは、明確に認識されていない、または認識されていても根本的な原因が明らかになっていない課題を指すものです。以下の課題などはこれに該当します。
- 管理職やリーダー候補となる人材の不足
- 関係者間での価値観の不一致
- コミュニケーションが取れていないことによるストレス
このような組織課題は、表面上は別の課題として浮かび上がってくるので、対処が容易ではありません。例えば、「業務効率の低下」が課題になっていたとしても、その裏に本当の課題として「コミュニケーション不足」が隠れている、ということが起こり得るのです。よって潜在化している組織課題に関しては、まずその存在を認識する段階から始める必要があります。
組織課題の解決はなぜ必要?
先ほどお伝えした通り、企業を取り巻く環境は目まぐるしく変化し続けています。このような状況下で組織課題が残ったままでは、競合他社に大きく差をつけられてたり、売上が低迷したり、最終的には会社の存続すら危ぶまれる可能性もあるでしょう。
会社を成長させて競合他社との競争に打ち勝つためにも、組織課題は優先的に解決しなくてはならないのです。
組織課題としてよくある具体例
一口に「組織課題」といっても、その種類や内容は多岐にわたります。そのため、まずはどのような事例が組織課題として発生し得るのかを把握する必要があるでしょう。
そこでここからは、組織課題の代表的な6つの具体例を紹介します。
事業戦略や会社の指針が社内に浸透していない
「会社の定める事業戦略や指針が社内に浸透していない」という事例は、組織課題としてよくあるものです。
社員が会社の方針を理解していないと、ビジネスに対する価値観や目線が全社的に揃えられず、業務が非効率的になってしまいます。また、組織としての一貫性もないため、顧客や世間からの信頼を損なう事態にも発展しかねません。
このように、事業戦略や指針に関する組織課題は非常に影響度の高いものであるため、速やかに対処する必要があります。
離職率が高い
転職が当たり前となった昨今、離職率の高さは多くの企業で発生し得る組織課題といえます。
離職する社員が多くなれば、人材不足や業務の停滞はもちろん、ノウハウの流出や採用コストの増加など、さまざまな面で会社に悪影響を与えます。特に専門性の高い人材、例えばITエンジニアなどが離職すると、市場での競争力も大きく損なわれてしまうかもしれません。また若手社員の離職率が増加すると、自社の将来を担う人材が減り、結果として大きな損失をもたらします。
離職率の課題が放置されたままでは、「あの会社でははたらきたくない」という悪評にもつながってしまう可能性もあるので、早急に対処すべきでしょう。
求める人材の採用ができていない
自社に合った人材を採用できていないことも、組織課題のよくある事例として挙げられます。
自社の雰囲気に合っていない、あるいは求める経験やスキルを持っていない人材を採用しても、当然ながら成果は出ないでしょう。これは、採用費用の浪費だけではなく、既存社員のモチベーション低下や、離職率の上昇といった事態も招いてしまいます。また、求める人材を採用できたとしても、入社後のフォローがうまくいかずに早期退職してしまう、ということもあります。
こうした採用に関する課題は、求める人材像が統一されていない、または社内の教育体制が整備できていないことに原因があるケースがほとんどです。採用活動を始める前に、その目的を社内で統一し、連携体制を構築することが大切です。
関連記事:採用戦略の立て方と効果的なフレームワーク・成功事例を解説
評価制度があいまいに設定されている
明瞭な評価制度が設けられていないことも、影響度の大きい組織課題の一つです。
評価の内容や基準が不透明だと、「自分に対する評価は妥当なのか?」と、社員の会社に対する不満や不信感が募ります。そうなれば、社員の業務に対する意欲、さらにはパフォーマンスが低下して、最終的には会社の業績悪化へとつながる可能性があるでしょう。
このような事態を避けるためには、評価項目やその詳細、また昇進の条件などは明確に定めておく必要があります。
コミュニケーションが不足している
先述の潜在化している組織課題についての説明時にも触れましたが、社員間のコミュニケーション不足は、また別の課題を生み出す要因となり得ます。情報が共有されていないことによる業務の非効率化、認識のずれや誤解から生じる人間関係のトラブルなどが、その最たる例でしょう。
活発なコミュニケーションは組織を運営する上で必要不可欠な要素であるため、この課題も可能な限り迅速に解決したいところです。チャットツールの導入や、多くの社員が交流できるイベントの開催など、コミュニケーションの活性化を図りましょう。
重要性の低い業務が多く効率が悪い
コア業務とは直接関係のない作業や対応が多すぎると、仕事の進め方が非効率的になってしまいます。
例えば、「出勤や退勤報告は口頭で直接伝える」「業務に関する報告書は必ず紙で作成する」といったアナログな業務は、デジタルな手法と比べて非効率的といえます。また、これらは非効率的であるだけでなく、口頭での報告は記録に残らず、紙の書類は紛失する恐れもあるため、その観点からも早急に改善すべきでしょう。
なお、このケースはあくまでも事例の一つに過ぎません。企業ごとに「この業務は本当に必要なのだろうか?」と見直せる部分は異なるので、自社に合った改善策を検討することが重要です。
組織課題の見つけ方
組織課題の具体例は把握できましたが、これらをどのようにして発見すれば良いのでしょうか?さまざまな方法がありますが、ここでは特に有用と考えられる4つの方法を紹介いたします。
社員アンケートを実施
現場ではたらく社員に向けたアンケートを実施して、課題だと感じていることや改善要望などを集める試みは、組織課題の対処法として非常に効果的です。
先に紹介した例を見てもわかるように、組織課題の多くは、現場の業務や人間関係に関連しています。当然、経営陣や管理職が認識できていない課題も存在するでしょう。そうした課題を洗い出して解決の糸口をつかむためにも、アンケートを実施する必要があります。
なお、アンケートは匿名で行うことをおすすめします。直接伝えられないことや会議では言いにくい意見も収集できるようになり、より効果的に組織課題を洗い出せます。
1on1ミーティングの実施
各社員が課題だと感じていること、困っていることを深掘りしたいのであれば、1on1ミーティングを実施しましょう。1on1で課題の詳細を把握できれば、改善に向けた取り組みをスムーズに進められます。
また、立場や考え方が違えば課題に対する捉え方も変わります。そのため各社員の課題に対する意見を集約すれば、多面的なアプローチが可能となるでしょう。
このほか、良好な関係を構築する上でも1on1は非常に有用であるため、定期的に実施することをおすすめします。
社員同士の意見交換の実施
社員同士が自由に意見を交換できる場を設けることも、組織課題の発見のためには欠かせません。ほかの社員の意見を聞くことで、それぞれが感じていた違和感が言語化されて、隠れていた組織課題の顕在化につながる可能性があります。
このような意見交換会を実施する際は、各自が安心して発言できるような雰囲気づくりを心がけましょう。心理的安全性が高まれば本音ベースで意見を出せるようになり、組織課題に関する本質的な議論を展開できます。
専用ツールを活用した分析
ツールを活用して分析を行えば、工数や作業時間といったデータを基に組織課題を明らかにできます。
個人の考え方や経験則も重要ではありますが、定量的なデータが必要となるケースも当然あります。特に、社員数が多く会社全体で意見をまとめることが難しい場合には、ツールを用いた画一的な分析が効果的なアプローチとなります。
一点、ツールを導入する際は「業務のどの分野に関する分析を行うのか」を事前に明確化しておきましょう。分析を行う分野が異なれば、最適なツールも変わるためです。さまざまな製品を比較して、自社の状況に合ったものを選びたいところです。
組織課題の解決方法と流れ
組織課題の見つけ方を踏まえた上で、次は解決方法について解説します。組織課題を解決するまでの流れは以下の通りです。
- 組織課題の調査と把握
- 組織課題の共有
- 組織課題の優先度決め
- 原因分析と改善策の検討
- 改善策の実行
- 効果検証と振り返り
各ステップの詳細を、順を追って見ていきましょう。
STEP1組織課題の調査と把握
まずは前項で紹介した方法を活用して、社内に存在する組織課題を調査し、把握しましょう。
その際、あらゆる観点から組織課題を洗い出すためにも、複数の方法を併用することをおすすめします。少しでも多くの情報を得て、検討材料を増やすことが大切です。
STEP2組織課題の共有
組織課題をある程度把握できたら、その内容と、会社としての対応方針を社員に共有します。「自社にはこれだけの課題がある」という意識を社員に持ってもらい、自分事として解決にあたってもらうことがこのステップの目的です。また、方針を示すことで、以降の対応内容が社員ごとにぶれないようにする狙いもあります。
このように、組織課題を共有することは、解決に向けた取り組みとして必要不可欠です。ただし、課題の内容が人間関係をはじめとするセンシティブなものである場合は、取り扱い方に注意しなくてはなりません。「そもそも取り扱うべきか」というポイントのほか、情報を開示する範囲などを慎重に検討する必要があります。
STEP3組織課題の優先度決め
明らかとなった課題の数にもよりますが、全てを一度に解決することは現実的ではありません。改善活動を効率的に進めるためにも、優先して解決すべき課題とそうでない課題を選別する必要があります。
事業に大きく影響している課題や、会社の成長を明確に妨げている課題は、優先的に解決したいところです。その一方で、まずは解決しやすい課題から取り組んで成功事例を増やす、といった方針も考えられます。最適な選択肢はケースごとに異なるので、自社の状況を踏まえた上で決めましょう。
STEP4原因分析と改善策の検討
課題ごとの優先順位づけが完了したら、原因分析を行います。
繰り返しになりますが、表面的に把握できている課題の裏には、本当に対応が必要な課題が隠れていることが少なからずあります。そのため、「何がこの課題を引き起こしているのか」を順番に辿っていくことが、有効な改善策を検討する上では欠かせません。
STEP5改善策の実行
組織課題に対する改善策の策定後は、実行計画を立てて、それに基づき取り組みを開始します。組織課題を確実に解決するためには、スケジュールや部門ごとの分担、社員ごとの分担などをこの段階で可能な限り具体的に決めましょう。
なお、複数の改善策がある場合は、並行ではなく一つずつ実施することをおすすめします。
同時に取り組みを始めると、成果が出た際にどの改善策によるものなのか判断できないためです。一つひとつ実施すると時間がかかるかもしれませんが、そこで成果を急がないことが大切です。全社的に焦らず、根気強く取り組む姿勢の維持が重要です。
STEP6効果検証と振り返り
最後に、実施した改善策によって組織課題が解決できたかどうかを検証します。そして、解決できたのであれば何が成功要因になったのか、あるいは未解決の場合にはどこに問題があったのかを、最初のステップから順に振り返っていきます。
実際のところ、一度の取り組みで組織課題を完全に解決できるケースはそう多くありません。組織課題が残ったまま「だめだった…」とあきらめてしまうのではなく、改善点を話し合った上で次の機会に向けて施策をブラッシュアップしていくことが、最も大切なポイントだといえるでしょう。
組織課題の解決に使えるフレームワーク
組織課題の発見から解決までをスムーズに行う上で、以下の5つのフレームワークは非常に役立ちます。それぞれ適したケースが異なるので、自社の状況に合ったものを取り入れましょう。
7S
7Sとは、組織運営を以下の7つの観点から見直して、課題や改善点を洗い出すためのフレームワークです。
- Strategy:事業戦略や市場競争の方針
- Structure:組織の構造や形態
- System:社内の各制度や管理方法などの仕組み
- Skill:自社が持つ事業に関する技術や強み
- Staff:各社員の特徴
- Style:社風や方針
- Shared Value:会社の理念や将来像
最初の3つは会社の「ハード面」に関する要素であり、比較的容易に修正できる範囲とされています。対してそのあとの4つは「ソフト面」、つまり概念的な内容であり、改善に際して一定の時間と労力をかけざるを得ない部分です。自社の現状をこれらの観点に基づいて分析すれば、課題のある部分、そして解決方法や要する期間などをスムーズに検討できます。
ミッション・ビジョン・バリュー
会社の価値観や方向性に関して何か課題が見られるのであれば、ミッション・ビジョン・バリューの活用をおすすめします。 ミッション・ビジョン・バリューとは、文字通り以下の3つの観点を指すフレームワークです。
- ミッション:会社の使命
- ビジョン:会社の将来像
- バリュー:会社の価値観や行動指針
この3つの観点が社内で統一できていれば、会社としての一体感が保たれ、認識の齟齬を原因とする組織課題が生じることを防げます。新規事業を立ち上げる際など、活動の方針がぶれ始めてしまうことが多いタイミングには、ミッション・ビジョン・バリューをベースに認識のすり合わせを行いましょう。
関連記事:ビジョン・ミッション・バリューの重要性と浸透、作り方を解説
SWOT分析
自社の課題を客観的に把握するためのフレームワークとしては、SWOT分析も候補に挙がります。
SWOT分析は、強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の4つの観点から自社の分析を行うフレームワークです。自社の強みや弱みという内部的な要因と、ビジネスの機会や自社に対する脅威などの外部的な要因の両面から総合的に分析を行い、課題の把握を試みます。また、会社を取り巻く環境について分析する関係上、今後の企業戦略やマーケティングの方針を決める上でも有用です。
KPI
改善策に取り組む段階であれば、KPI(Key Performance Indicator)を活用することをおすすめします。
KPIは、施策の目的を達成するために必要な行動に対する具体的な数値指標を示すものです。例えば、「売上5,000万円」を最終目的とする施策なら、その過程で必要となる「アポイントメント数50社」「成約数10件」などの指標がKPIに該当します。
改善策の実施時にこのKPIを設定すれば、中間目標が明確になり、社員が施策に取り組みやすくなります。また、進捗状況を数値で把握できるため、状況が芳しくなければ内容を見直すといったリカバリーも容易に実施可能です。
PDCAサイクル
先ほどお伝えした通り、組織課題を改善する取り組みでは、実施後の振り返りとブラッシュアップが非常に重要となります。そこで活用したいフレームワークが、PDCAサイクルです。
PDCAサイクルでは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)を繰り返し、施策の確度を段階的に高めていきます。改善策の実行や見直しの際にこのサイクルを強く意識できれば、より効率よくブラッシュアップを図れるでしょう。PDCAサイクルによって継続的に組織課題を改善していくことが、会社の将来的な成長につながります。
組織課題の解決のために管理職が意識すべき点
全社員一丸となって組織課題の解決にあたるためには、経営層と社員をつなぐ管理職の活躍が欠かせません。そこで最後に、管理職が意識すべき4つのポイントをお伝えします。
関連記事:プロ経営者が実践!社員が辞めない組織つくり |3年間離職者0を出した施策とは
メンバーに主体的な行動を促す
経営層や管理職だけが主体的に施策に取り組んでも、組織課題を根本的に解決することはできません。現場ではたらいているチームのメンバーや部下にも積極的に取り組んでもらう必要があります。そのためには、管理職がメンバーに主体的な行動を促すことが重要です。
取り組みに対する姿勢や成果が評価に反映されることをきちんと伝えれば、メンバーの主体性を効果的に引き出せる可能性が高まります。その上で、先に紹介したKPIなどを活用して具体的な中間目標を定めておけば「何をしてよいかわからない」という社員もサポートできるでしょう。
関連記事:人材育成とは?基本的な考え方や人材活用の目標設定方法
職場環境を改善する
メンバーのモチベーションを高めるという点では、職場環境に対して意識を向けることも非常に大切です。そもそもはたらきづらい環境では「組織課題を改善しなくてはならない」という意識が社員の中に生まれず、改善策が成功することはありません。
各種休暇制度をはじめとする福利厚生やオフィス環境に不足があるなら、管理職が率先して改善を提案しましょう。「ここでなら安心してはたらける」と思う社員が増えれば、そのモチベーションの高さから改善活動の質も上がると考えられます。
関連記事:EVP(Employee Value Proposition)とは?重要性や事例を解説
個別でのコミュニケーションを増やす
メンバーとこまめにコミュニケーションを取り、各自の得意分野や近況を把握することも、管理職が意識すべきことの一つです。
メンバーが潜在能力を発揮できる領域を管理職が理解していれば、改善策を実施する際の役割を適材適所で割り振れます。また、潜在化している組織課題を洗い出す上でも、個別に話を聞くという対応は効果的です。さらに、コミュニケーションを密に取れば信頼関係も構築できるため、改善活動に対する社員のモチベーションも高められるでしょう。
改善策の実施結果を共有する
改善策を実施したあとは、成否にかかわらず結果の全てをメンバーや部下に共有しましょう。
組織課題が無事に解決されたことを共有できるのであれば、それに越したことはありません。しかし、失敗した結果を共有することも、PDCAサイクルを回す上では必要不可欠な対応です。一人ひとりが結果を把握し改めて意見交換を行うことが、組織課題の根本的な解決、ひいては会社の成長につながるのです。
人材・組織開発なら「HiPro Biz」
組織課題の見つけ方や解決方法がわかっていても、それを実践できる人材が社内に存在せず、取り組みを始められないということもあるでしょう。そのような状況の企業におすすめの経営支援サービスが、「HiPro Biz」です。
さまざまな領域のプロ人材が登録している「HiPro Biz」であれば、現在抱えている組織課題を的確に解決できる、最適な人材をご紹介可能です。効率よく組織を成長させるために、ぜひ「HiPro Biz」をご利用ください。
組織課題を解決するためには、社員が一丸となって施策に取り組むことが重要
組織課題を発見する方法や施策を実践する流れ、そして有用なフレームワーク5選を紹介しました。
全社的に意見や悩みを収集し、自社にどのような課題があるのかを把握することが、組織課題を解決するためのスタート地点といえます。その上で、今回紹介した5つのフレームワークを活用しつつ、社員が一丸となって改善策に取り組めば、組織課題を効率よく解決していけるでしょう。
「組織課題を解決できる人材がいない…」とお悩みであれば、さまざまな領域のプロ人材が登録している「HiPro Biz」をご利用ください。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)




