経営顧問とは?業務内容や契約形態、依頼する方法を解説
2025年08月29日(金)掲載
大手企業であっても、経営課題に直面することは少なくありません。特に、経営層と現場の間で戦略が噛み合わない、社内に経営戦略の専門家がいないといった課題は、企業の成長を阻害する要因となります。
そのような状況を打開する上で重要となる人材が、「経営顧問」です。
本記事では、経営顧問に依頼できる業務内容や利用するメリット、また依頼方法などを解説します。経営課題の対処が難航している経営者や管理者は、ぜひご一読ください。
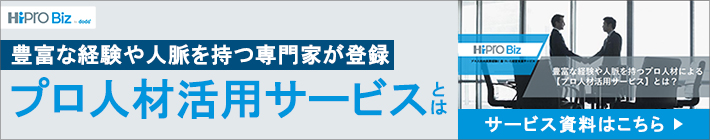
■経営顧問とは
■経営顧問に支援を依頼するメリット
■経営顧問を活用する際の注意点
■経営顧問の種類
■経営顧問の報酬体系
■経営顧問へ支援を依頼する方法
■経営顧問に支援を依頼する前に確認すべき点
■経営顧問を登用すれば自社の成長が実現する
経営顧問とは

経営顧問とは、企業の経営者が意思決定を下す、または問題解決に臨む際に支援を行う専門家のことです。豊富なノウハウと知見を活かして経営者や役員に適宜アドバイスを行い、企業の成長を促進します。また、単にアドバイスをするだけではなく、時には経営方針の具体的な案を提示する場合もあります。
ただし、経営顧問の役割は「第三者の視点からアドバイスする」という範囲にとどまる点は理解しましょう。経営顧問を登用したとしても、最終的な判断はその会社の経営者が責任を持って行うことには変わりないのです。
経営顧問の支援業務の内容
経営顧問が提供する支援の内容は多岐にわたります。その一例が以下のとおりです。
- 中長期的な経営戦略の立案
- 経営戦略を企業が実行に移す際の補佐
- 事業拡大の方針に関するアドバイス
- 財務面でのアドバイス
- 組織改革や人材育成の実施
- リスクマネジメントの実施
ただし、全ての経営顧問が同じように支援してくれるわけではありません。人によって得意とする領域は異なるため、自社の状況に合った経営顧問を迎え入れることが、非常に重要となります。
関連記事:プロ人材とは?活用するメリットや有用性、コンサルティング会社活用との違い
相談役や参与との違い
経営顧問に似ている役割として、「相談役」と「参与」が存在します。
どちらも、経営に深く関わるという点では経営顧問と同じに思えますが、企業内での立場や詳細な役割には明確な違いがあります。
| 経営顧問 | 相談役 | 参与 | |
|---|---|---|---|
| 登用される人材 | 社外の専門家 | その企業の元社長や元会長 | 特定分野に精通した社内の人材 |
| 役割 | 第三者の視点から企業を分析した上で、専門的知見に基づいたアドバイスを述べる | その企業で長年経営に携わってきた経験を活かし、経営に関する助言を行う | 特定分野の知見を活かし、経営の意思決定に深く関わる、また業務の実質的な主導者として動く |
大きな違いとして挙げられる点は、登用される人材の出所です。経営顧問が基本的に社外の専門家であるのに対して、相談役や参与には、もともとその企業で活躍していた重役、あるいは在籍中の人材が登用されます。
また、この違いが役割の差にも大きく影響しています。
先述したとおり、経営顧問の役割は第三者の視点からアドバイスを述べることです。それに対して、相談役はアドバイスを述べるという点では共通していますが、外部からではなく内部からの視点に基づいている点が異なります。参与に関しては、相談役と同じく内部からの視点を持っていること、そして最終的な意思決定にも関与する点で相違があります。
関連記事:顧問とは?活用のメリットや報酬、ほかの役職との違いや事例を解説
経営顧問に支援を依頼するメリット
経営顧問を登用することで得られるメリットとしては、主に以下の3つが挙げられます。
- 有益な客観視点でのアドバイスを受けられる
- 経営課題の解決につながる
- 新たな経営幹部の育成につながる このような支援を行う経営顧問は、単なるアドバイザーではなく、企業の成長を共に目指すパートナーです。
有益な客観視点でのアドバイスを受けられる
プロフェッショナルの客観的な知見を得られる点は、経営顧問を登用することの明確なメリットの一つです。
周囲を社内の人間だけで固めて業務に携わっていると、いつの間にか視野狭窄に陥り、冷静な判断が下せなくなることが少なくありません。そのような状態に陥らないためにも、第三者視点からアドバイスを授けてくれる経営顧問が必要となるのです。
また、法律や財務、人事、マーケティングなどの企業経営に欠かせない領域の専門家が常にいれば、トラブルが発生した際にも即座に対応方針を定められるでしょう。
経営課題の解決につながる
企業の成長を阻害している経営課題を解決する上でも、経営顧問の登用は効果的です。
経営顧問として活躍している人材は、それまでの経歴の中でさまざまな問題に直面し、解決してきたと考えられます。よって、自社が直面している経営課題についても、的確な解決策を提示してくれるはずです。また、普段の業務を経営顧問に分析してもらうことで、隠れていた課題の顕在化も可能となります。
新たな経営幹部の育成につながる
このような支援を行う経営顧問は、単なるアドバイザーではなく、企業の成長を共に目指すパートナーです。
自社を長きにわたって発展させるためには、会社の将来を任せられる新たな経営幹部を育成しなくてはなりません。しかし、日々多くの業務に追われている経営者が、自ら率先して人材を育成することは非常に困難です。
しかし経営顧問に育成を任せれば、経営者は主業務に注力したままに、経営に関するノウハウや知見を幹部候補の人材が学べるようになります。また、経営顧問が直接的に指導を行わなくとも、経営課題に向き合う姿勢やその際の活躍が、幹部候補となる人材の大きな糧となるはずです。
経営顧問を活用する際の注意点
経営顧問を自社で活用する際は、以下の3つのポイントに注意しましょう。
- 社員との摩擦が生じる可能性がある
- 高額な費用が発生する可能性がある
- 経営顧問に依存し、社内の判断力が低下する恐れがある
社員との摩擦が生じる可能性がある
自社の業務や意思決定のプロセスに社外の人材を関わらせることを、快く思わない社員がいないとは限りません。特に、自社に長く貢献してきたベテラン社員は、その長さ故に経営顧問のやり方や意見に対して反発してしまう場合があります。
経営顧問の力を借りることも大切ですが、そのせいで社員との関係性が悪化しては元も子もありません。そのため、経営顧問を登用する際は、まず社内の人間に対してしっかりと説明を行い、意義や重要性を理解してもらえるように努めましょう。
高額な費用が発生する可能性がある
経営顧問に支払う報酬は、ケースバイケースではありますがその支援内容や影響力ゆえ、相応の金額となります。特に、豊富な実績がある、または専門性の高い分野をカバーしている経営顧問には、高額の報酬を支払う必要があるでしょう。
場合によっては、その報酬が自社に大きな負担をかける可能性もあります。自社の財務状況を確認した上で、費用対効果が十分に見込めるかどうかを事前に検討することが大切です。
経営顧問に依存し、社内の判断力が低下する恐れがある
経営顧問が自社の経営をサポートしてくれることは間違いありませんが、依存し過ぎると自社の不利益につながる恐れがあります。経営課題に直面するたびにアドバイスをもらって実行しているだけでは、経営者自身ないし社員の判断力や問題解決力が低下してしまうためです。
繰り返しになりますが、経営顧問はあくまでもアドバイザーに過ぎません。経営に関する最終決定を下す主体は経営者であると理解し、経営顧問からのアドバイスに従うかどうかは都度判断することを徹底してください。
経営顧問の種類
経営顧問には、「内部顧問」と「外部顧問」の2種類が存在します。
| 種類 | 内部顧問 | 外部顧問 |
|---|---|---|
| 人材の種類 | 内部の人材 | 社外の専門家 |
| 務める人材の例 |
・元取締役 ・元会長 ・現役の役員 |
・弁護士 ・税理士 ・公認会計士 |
| 特徴 | 社内事情に精通しており、実務に即したアドバイスができる | 専門的な知見を持ち、第三者目線でのアドバイスができる |
両者の違いを、さらに深掘りしていきましょう。
内部顧問
内部顧問は、自社にもともと勤めていた人材、あるいは現役の社員といった、内部の人間が顧問を務める場合の分類です。自社での実務経験があり、社内の事情や企業文化、風土などに精通している点で相談役や参与と似ている役割だといえます。
この特性上、一般論ではなく、社内の事情をある程度考慮したアドバイスが欲しい場合に最適です。具体的なケースとしては、以下が挙げられます。
- 自社の事業や業務の特性を理解した上でのアドバイスがもらいたい
- 企業文化や風土を大きく変えることなく組織改革を進めたい
- 社員との関係性が良好な経営顧問を登用したい
また、経営顧問にふさわしい人材を探す手間やコストを抑えたい場合にも、内部顧問はお勧めです。すでに関係が構築されているためコンタクトが取りやすく、報酬面の交渉もスムーズに進められる可能性があります。
外部顧問
社外の専門家が顧問を務める場合、その人材は外部顧問と呼称されます。弁護士や税理士、公認会計士、中小企業診断士など、特定分野の専門家を登用することが一般的です。
外部顧問の強みは、社内の人間ではないからこその客観性の高さにあります。
内部の人間では持ち得ない多角的な視点からのアドバイスを受けられるため、経営方針や事業の進め方などの軌道修正を行う際に最適です。また、自社に知見のない領域のプロ人材を登用すれば、社内のリソースを割くことなくその領域をカバーできます。
- 経営判断を下す際に第三者からの客観的な意見がもらいたい
- 自社の大規模な改革を行う際のサポートが欲しい
- 特定分野に関する専門的な知見が欲しい
上記のほか、社外での人脈を築く際にも、豊富なコネクションを持つ外部顧問を頼りたいところです。
関連記事:【ひな型付き】顧問契約書の作成手順や注意点を徹底解説
経営顧問の報酬体系
経営顧問の報酬体系は、主に以下の3種類に分けられます。それぞれの詳細を順に解説します。
- 固定報酬制
- 時間単価制
- 成果報酬制
固定報酬制
固定報酬制は企業と経営顧問が契約した上で毎月一定の額の報酬を支払います。報酬の額は、経営顧問の専門性の高さや、依頼する業務内容の難易度などによって変動します。
固定報酬である以上、仮に大手企業との商談が成立し相当な額の利益が出たとしても、それによって支払う報酬の額も増える、ということはありません。そのため、予算管理もしやすくなります。
こうしたメリットがある一方で、成果が出ていない状況でも報酬が発生することは理解しておく必要があります。
時間単価制
時間単価制では、経営顧問が実際に活動した時間によって報酬額が決定します。 サポートを必要とする期間だけ活用しその分の報酬を支払う、といったふうにコンパクトな利用が可能です。特定の分野に関するノウハウを取り入れたい場合に最適です。
成果報酬制
成果報酬制は、成果に基づいて料金が発生する報酬体系です。一般的に一定の成果が得られたときのみ報酬を支払うため、成果が想定より得られなかった場合に備えたリスクヘッジができる点が成果報酬型のメリットです。
経営顧問へ支援を依頼する方法
経営顧問を探し業務の支援を依頼する場合は、以下の3つの方法を利用しましょう。
- 顧問紹介サービスを利用する
- 取引先や知人、顧問税理士から紹介を受ける
- 経営支援サービス「HiPro Biz」を活用する
顧問紹介サービスを利用する
外部人材とのコネクションや人脈がまだ築けていない場合は、顧問紹介サービスの利用がお勧めです。自社の希望条件に合った人材を顧問契約に精通したプロが探してくれるため、効率良く経営顧問との契約まで進められます。人材を探す手間も省けるため、サービスの利用料を捻出できるのであれば積極的に活用したいところです。
取引先や知人、顧問税理士から紹介を受ける
取引先や知人から紹介してもらえるルートがあるなら、外部サービスを使わずとも経営顧問を迎え入れられます。自社の内情をある程度知っている人物からの紹介であれば、即戦力として期待できる経営顧問を見つけられるでしょう。
また、自社の顧問税理士のコネクションを利用すれば、同じ士業である弁護士や税理士、公認会計士の経営顧問を紹介してもらえる可能性があります。
経営支援サービス「HiPro Biz」を活用する
自社が抱える経営課題にマッチした営業顧問を探したいのであれば、パーソルキャリアが運営する経営支援サービス「HiPro Biz」の活用をご検討ください。
3万名を超える(2025年3月現在)プロ人材が登録している「HiPro Biz」には、営業のプロフェッショナルも多数登録しています。得意とする領域も多種多様で、営業戦略、販路開拓やコーチング戦略の立案、海外進出の際のサポートなど、さまざまな形での支援が可能です。
なお「HiPro Biz」には「コンサルティングプラン」「成果完成型プラン」「独立役員紹介プラン」あります。
「コンサルティングプラン」は、プロ人材の業務工数や、解決を依頼する課題の難易度に応じて報酬の額が決定するプランで、営業戦略立案や新規顧客開拓や販路拡大といった、必要な期間、必要なタイミングで特定分野のノウハウや人脈を自社に取り入れたい時に適しています。
「成果完成型プラン」は、必要な納期で、特定分野の知見と実行力をもとにした、具体的な成果物が必要な場合に適しており、リサーチ報告書や業務改善報告書といった具体的な成果物を求めるケースで最適です。
「独立役員紹介プラン」は、常勤役員や社外取締役などのプロ人材を、中長期的に活用したい場合に最適です。
※参考:サービスプラン(HiPro Biz)
経営顧問に支援を依頼する前に確認すべき点
最後に、経営顧問に自社のサポートを依頼する前に確認すべき3つの点を解説します。
- 経営課題と依頼する目的を明確にする
- 社内への周知と社員の理解を得る
- 顧問税理士に依頼できる業務領域かどうかを確認する
経営課題と依頼する目的を明確にする
「自社をサポートしてほしい」という漠然とした依頼では、経営顧問もアドバイスを述べられず、その本領を発揮できません。そのため、まずは解決したい自社の課題と、それを経営顧問にどのように解決してほしいかという目的の両方を明確化する必要があります。
例えば「新規事業を始めたいが事業基盤がまだ盤石ではないので、まずそこから着手したい」といった感じで伝えられれば、経営顧問から的確なアドバイスや意見をもらえます。それが難しい場合は、課題を洗い出すところから支援を依頼する、という方法を取っても良いでしょう。
社内への周知と社員の理解を得る
経営顧問を迎え入れる旨を事前に社内に周知し、社員からの理解を得ておくことも重要です。「費用対効果は得られるのか」「自社の企業風土や雰囲気が変わってしまわないか」といった懸念が残ったままでは、経営顧問と社員の間に不和が生じかねないためです。
いかに経営顧問が優秀であっても、協力的な風土でない環境下では成果を出すことはままなりません。故に、経営顧問を登用する目的や見込める効果などを全社員に対して説明し、理解を示してもらう必要があるのです。
顧問税理士に依頼できる業務領域かどうかを確認する
顧問税理士がすでにいる場合は、その人材に経営課題の対処にあたってもらえないかどうかを確認しましょう。それで済むようであれば、新たに経営顧問を探す必要はありません。
顧問税理士は財務面を通して自社の状況を客観的に見ているため、経営面での総合的なアドバイスや意見も述べられる可能性があります。また、自社の顧問税理士に対応を断られたとしても、経営顧問に適した別の人材を紹介してもらえる可能性はあるので、まずは一度相談してみることをお勧めします。
経営顧問を登用すれば自社の成長が実現する
今回は、経営顧問について解説しました。
経営顧問には、経営戦略の立案や財政面でのアドバイスなど、経営に関わる多種多様な事項を任せられます。また、外部の視点を取り入れることによる、自社の状況の客観的な分析も可能です。経営顧問に頼りきりにならない、また依頼する事項を事前に明確化するなどの注意点も考慮した上で、経営顧問とともに自社をさらなる発展へ導きましょう。
自社の成長を一からサポートしてくれる経営顧問をお探しであれば、ぜひ一度「HiPro Biz」にご相談ください。各業界のトップクラスのプロ人材が、貴社の事業に伴走し、経営課題を根本から解決いたします。
関連記事:経営支援サービス「HiPro Biz」
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)




