きちんと「機能する」ナレッジシェアリングとは?陥りがちな失敗要因とその解決策
2025年05月20日(火)掲載
- キーワード:
組織全体の生産性を向上させる取り組みの一つに、「ナレッジシェアリング」と呼ばれるものがあります。
業務の属人化を防ぎ、新人教育や引き継ぎの負担を軽減するためにも有効といわれるナレッジシェアリングとは一体どんなものなのでしょうか。
本記事では、ナレッジシェアリングの概要や実施メリット、具体的な手順などについて解説します。
業務の属人化や品質面にお悩みのご担当者はご一読ください。
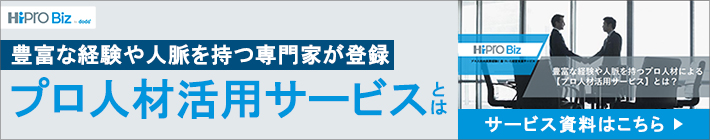
■ナレッジシェアリングとは?
■ナレッジシェアリングの重要性
■ナレッジシェアリングのメリット
■効果的なナレッジシェアリングを行う手順
■ナレッジシェアリングがうまくできない理由
■ナレッジシェアリングを成功させるためのポイント
■ナレッジの見える化やプロ人材によるノウハウの蓄積なら「HiPro Biz」を
■ナレッジシェアリングを適切に行えば、組織の成長を目指せる
ナレッジシェアリングとは?

「ナレッジシェアリング」とは、組織の生産性向上を目的に、メンバー一人ひとりが持つさまざまな知識や情報を共有する取り組みです。具体例としては、社内マニュアルの整備や定期的なミーティングによる情報交換などが挙げられます。
この取り組みにより、業務の属人化を防げることはもちろん、効率化や品質向上にもつながります。組織全体で同じ知識を活かすことで、業務の標準化を進められるのです。
そのため、ナレッジシェアリングは単なる情報共有ではなく、組織の成長を促す重要な戦略として捉えるとよいでしょう。
ナレッジシェアリングの重要性
ナレッジシェアリングは、はたらき方の多様化が進んでいる昨今、非常に重要な取り組みといえます。
近年、年功序列や終身雇用といった考え方が変化し、転職が一般的になる中、見方を変えれば、自社業務を遂行してきた社員が持つ知見やノウハウなどが、他社に流出してしまうリスクも考えられます。そのような特定のノウハウが外部に流出すると、自社にとって大きな損失となり、場合によっては企業活動の継続に影響を及ぼす可能性も否定できません。
自社で活躍する社員の離職はもちろん防ぎたいところですが、万が一離職してしまうケースに備え、社員個人が蓄積してきた情報を随時社内に残しておくことが、リスクヘッジにつながります。特定の人材に依存せず、ほかの社員も同じ知識を得られる状態をつくることで、業務の属人化に陥らない企業活動の実現につながります。
ナレッジシェアリングのメリット
ナレッジシェアリングには、さまざまなメリットがあります。
業務の属人化を防げる
ナレッジシェアリングの本来の目的であり、まず挙げられるメリットは、属人化の防止です。
社歴の長い社員が多く在籍すると、属人化は起きやすくなります。特に営業職のように、顧客情報や提案履歴、過去のやりとりなど、多様な情報を常日頃から扱う業務では顕著でしょう。
たとえ属人化している状態で問題なく業務を回せていても、担当者の急な退職や体調不良による欠勤など、万が一の事態が起きた際にトラブルに発展する可能性があります。情報の引き継ぎが適切にできていなければ対応に手間がかかり、顧客からの信頼を失うことにもなりかねません。
そのような場合に備えて、普段からナレッジシェアリングを行えば、別の担当者が対応することになっても、共有された情報を基に一定の業務品質を担保できるようになります。
スキルアップにつながる
ナレッジシェアリングは、万が一の際に備えた引き継ぎだけでなく、日々の業務の品質向上にも役立ちます。特定の業務に慣れている社員が保有するノウハウやコツを周囲に共有することで、ほかの社員のスキルアップも促すことができます。
商談の交渉術や業務をスムーズに進めるコツなど、これまでは「見て、感じて、覚える」としていた感覚的なものも、情報として言語化し共有すれば、スムーズなキャッチアップにつながります。社員一人ひとりの理解が深まり、結果的に各スキルが向上すれば、組織全体の底上げも実現できるでしょう。
組織力を強化できる
ナレッジシェアリングによるスキルアップで力をつけられる対象は、社員個人だけではありません。前述の通り、一人ひとりがスキルを身につけることで、組織力そのものの強化にもつながります。
ナレッジシェアリングを促進することで、多くの社員が新たな知識やスキルを効率的に学べる機会を得られ、それが各社員の能動的で意欲的な成長につながります。このような成長意欲の向上も組織力強化の契機となるでしょう。
また、ナレッジシェアリングの文化が根付けば、「自分の持っている知識をみんなにも共有しよう」という協力意識が強まり、このような面からのシナジー効果にも期待が持てます。
業務改善や効率化につながる
適切なナレッジシェアリングにより、業務効率が改善し、一人ひとりの業務負担も軽減できる可能性があります。
必要な知識や手順などをいつでも可視化し参照できる状態に整えることで、不明点がある社員が上長やほかの社員に都度質問する手間が削減され、効率的に業務を進められるでしょう。また、整理した情報を改めて説明することなく、可視化された内容を相手に見てもらうだけになるため、知識を伝える側の負担も軽減されます。
社員のモチベーションが向上する
ナレッジシェアリングを行えば、社員が新しい知識を効率的に得られることは前述の通りですが、これにより、一人ひとりのモチベーションが向上するというメリットも得られます。
業務の品質向上につながる知識を社員各自が得られれば、「この知識を活かしたい」「もっと高いパフォーマンスを発揮したい」といった気持ちが自然と芽生え、モチベーション向上の契機にもなるでしょう。また、情報を提供する側も、提供したことを周囲から感謝されることで、ナレッジシェアリング自体はもちろん、それを通じた実業務に対しても、より前向きな気持ちで取り組めるのではないでしょうか。
また、モチベーション向上にくわえ、社員のエンゲージメント向上への取り組みにも着手すると、企業経営にさらなるプラスの影響を見込めます。以下の記事で解説している、エンゲージメントの高め方についても併せてご覧ください。
関連記事:従業員エンゲージメントを高める6つのステップ~一連の方法をご紹介~
イノベーションを促進できる
ナレッジシェアリングは、前述までのような既存課題を解決するだけでなく、新しいアイデアの創出、すなわちイノベーションの促進にも寄与します。
専門分野が異なる社員同士でそれぞれが持っている知識を共有すれば、お互いの情報を組み合わせて新しいアイデアを生み出すきっかけの場にもなりえます。新たな製品やサービスを開発するためにも意識的に促進し、活用してもよいかもしれません。
効果的なナレッジシェアリングを行う手順
ナレッジシェアリングを行うには、ただ情報を共有すればよいわけではありません。ここでは、ナレッジシェアリングの効果を最大化するために押さえておきたい手順をお伝えします。
具体的な目標を設定する
まずは、ナレッジシェアリングを行うそもそもの目的、「ナレッジシェアリングを通じて、どのような目標を達成したいのか」を明確にします。たとえば、「業務の品質を一定に保つ環境を整える」「新人教育の工数を削減する」などが挙げられます。
このあと、共有すべき具体的な情報やその手法を適切に決めるためにも、初期段階での目的や目標の整理は欠かせません。
共有したいナレッジやスキルを明確にする
ナレッジシェアリングの目的や目標が決まったら、その実現のために共有すべき情報を洗い出しましょう。「どのような知識が足りていないのか」「どんなノウハウが欲しいのか」を現場の社員に聞き取り、必要な情報を絞り込みます。
情報の共有方法を選定する
続いて、目的や組織に合った情報共有の方法を考えます。ナレッジシェアリング専用のツールもあるため、必要に応じてツールの導入も検討しましょう。
ただし、必ずしもツールを使わなければならないわけではありません。場合によっては、共有フォルダにWordなどを保管するだけで事足りる場合もあります。導入の有無を判断する目安を以下に整理しましたので、ご参考ください。
| ツールを導入したほうがよいケース例 | ツールを導入しなくてもよいケース例 |
|---|---|
| ・共有する情報量が多い ・社内全体など、共有範囲が広い ・効率的に共有できる環境を整えたい など |
・共有する情報があまり多くない ・担当者間のみなど、共有の範囲が狭い ・すでに共有の仕組みがある程度整っている など |
また、自社に不足している知識やノウハウを新たに取り入れる方法としては、このほかに、外部の専門家を活用するという選択肢もあります。パーソルキャリア株式会社が提供する「HiPro Biz」は、経営課題解決に取り組む企業向けに、経営層・CxO ・エキスパートクラス等、高度な課題を解決できる個人と共に、課題解決に導く経営支援サービスです。知識やノウハウを取り入れる選択肢のひとつとしてご検討ください。
定期ミーティングなど共有の場を設ける
ツールあるいはテキストファイルなどを用いて情報を蓄積するだけではなく、口頭のコミュニケーションによる情報共有の場も適宜設けたいところです。
ミーティングを定期的に実施することで、ナレッジシェアリングの機会を増やせます。週次や月次などの単位でミーティングを開催し、直近で各自が学んだことや成功事例などを共有しましょう。
効果の振り返りと改善を行う
業務改善には、PDCAサイクルが欠かせません。「この情報は本当に必要か」「いまの共有方法や仕組みに問題点はないか」「共有した情報は適切に活用されているか」などを定期的に振り返り、見直しましょう。情報を共有する社員と、共有された情報を受ける社員の双方に現状をヒアリングし、多角的な視点で分析することが重要です。
ナレッジシェアリングがうまくできない理由
ここまで、ナレッジシェアリングのメリットや進め方についてお伝えしてきました。しかし、上記の手順で進めても、想定したようなメリットを実感できないこともあります。
ナレッジシェアリングで想定通りの効果を得られない場合には、以下のような要因が考えられます。
- ナレッジシェアリングの文化が社内に根付いていない
- ナレッジシェアリングの必要性が理解されていない
- ナレッジの共有や管理に手間がかかっている など
社内に情報共有の文化が根付いておらず、ナレッジシェアリング実施の必要性が関係者に十分理解されていない場合は、まずは実施する理由や実施を検討するに至った経緯などを丁寧に説明する必要があるでしょう。必要性を理解されないままナレッジシェアリングを実施するのではなく、目的や理想像と現状とのギャップ、つまり課題感など、現場視点を大事にした話し合いから始めましょう。
また、ナレッジの共有や管理、閲覧自体に手間がかかる仕組みとなっている場合、情報発信する側のハードルが高まり、周囲が求めている情報を共有しにくくなっている可能性があります。あるいは逆に、せっかく情報共有しているにもかかわらず、その情報にアクセスしづらく、閲覧意欲を阻害してしまっているかもしれません。
このような事態を回避するために、次章で紹介するポイントを実践しましょう。
ナレッジシェアリングを成功させるためのポイント
前述の通り、ナレッジシェアリングを行ったとしても、適切に効果を得られないことがあります。ナレッジシェアリングが意義のある取り組みとなるよう、以下のポイントを意識してみてください。
欲しい情報がすぐ見つかるように管理する
情報を無作為に蓄積するだけでは、新たな情報を求める社員が「この情報が欲しい」と思ったときに素早く簡潔にアクセスできません。欲しい情報にいつでも簡単にアクセスできるよう、仕組みを整えましょう。
専用ツールを用いている場合は、カテゴリーの分類やタグの設定を行い、情報整理をしてみましょう。また、特定のワードで検索したら必要な情報が表示されるよう、たとえば見出しであれば、一般的に想起しやすい語句を意識的に使うなど適切な設定をすることも重要です。
対象のナレッジが社員のニーズとミスマッチを起こしていないか確認する
そもそも、プロジェクト主導側が「これから蓄積を進めよう」と考えている情報と、現場が求めている知識にミスマッチがないか確認することも重要です。さまざまな情報を共有しても、共有される側の社員にその情報の需要がなければ、ナレッジシェアリングを行う意味がなくなってしまいます。
このようなミスマッチを起こさないためにも、ナレッジシェアリングの目的や必要な情報は、現場目線を意識したヒアリングを実施した上で判断しましょう。
情報を定期的に更新する
情報がある程度蓄積されてきたら、その内容を定期的に見直してみましょう。時間の経過とともに、情報の鮮度が古くなっているかもしれません。
また、組織が成長するにつれて、当初は必要だった情報も必要なくなる場合もあります。「今の組織にとって必要な情報」だけがシンプルに残るよう、常にアップデートしていきましょう。
共有時のプロセスやルールの設定や運用を行う
必要な情報を誰でも簡単に共有できる環境を実現するためには、共有時のプロセスを整備し、ルールを適切に設定することを心がけましょう。
たとえば、情報共有のフォーマットを統一することや、保管場所を一定の箇所に定めるなど、属人的にならない共通認識のもとで運用できるような設定が挙げられます。特に保管場所の設定は、利便性の向上だけでなく情報漏えいリスクの抑止にも寄与します。
ナレッジの見える化やプロ人材によるノウハウの蓄積なら「HiPro Biz」を
「ナレッジの落とし込みが難しい…」「社内にないノウハウを新しくナレッジとして取り入れたい」
このようにお考えのご担当者は、この機会にぜひ「HiPro Biz」までご相談ください。
「HiPro Biz」は経営課題に取り組む企業向けに、経営層・CxO・エキスパートクラス等、高度な課題を解決できるプロ人材と共に、課題解決に導く経営支援サービスです。営業や新規事業開発、人材育成など、さまざまな分野に特化したプロ人材が多数登録しており、ナレッジシェアリングの分野においても言語化が難しい、いわゆる「暗黙知」のモデル化など、お悩みごとに最適なプロ人材をマッチングいたします。
課題にマッチした最適なプロ人材と連携し、自社にこれまでなかったノウハウの蓄積にお役立ていただくといった活用も可能です。
ナレッジシェアリングを適切に行えば、組織の成長を目指せる
今回は、ナレッジシェアリングのメリットをお伝えするとともに、ナレッジシェアリングを成功させるために押さえておきたいポイントなどについても解説いたしました。自社でナレッジシェアリングを実施するイメージは浮かんだでしょうか。
ナレッジシェアリングを適切に行うことで、属人化の防止のみならず、組織の成長まで見込めます。
本記事でお伝えした内容を参考にして、実施フローや仕組みなど現場に即した形でナレッジシェアリングを構築してみましょう。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)




