企業価値を高める「知的財産戦略」とは?立案の流れ、課題や改善策を解説
2025年07月22日(火)掲載
グローバル化の進展によって市場競争が激化している昨今、高性能で高品質な製品やサービスを提供するのみでは、企業が生き残ることは困難といえるでしょう。そのような状況下で、注目を集めている経営戦略が「知的財産戦略(知財戦略)」です。
本記事では、知的財産戦略の概要を、立案の流れや想定される課題とその改善策とともに解説します。企業の競争力を高めるための足がかりとして、ぜひ参考にしてください。
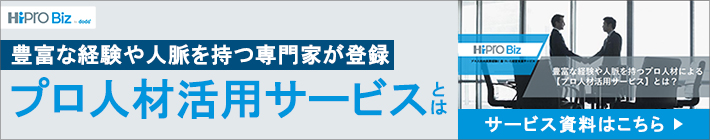
■知的財産戦略とは
■最新トレンドから見る知的財産戦略の進化
■知的財産戦略を立案する流れとポイント
■大企業で見られる知的財産戦略の課題と改善策
■知的財産戦略は企業の競争力を向上させ、事業を成長させるために重要
知的財産戦略とは
知的財産戦略とは、自社が生み出した発明やデザインなどの無形の財産、すなわち「知的財産」を保護、または活用する経営手法のことです。
以下で実行の目的や重要性、そして経営戦略との関係性から、知的財産戦略について理解を深めていきましょう。
知的財産戦略を実行する目的
知的財産戦略を実行する目的は、企業の知的財産、あるいは知的財産権に関する知識を駆使して事業を成功に導くことにあります。
戦略を推し進めることで期待できる具体的な成果を、以下にまとめました。
- 市場優位性の確保:知的財産の取得によって他社の参入を阻止する
- ブランド価値の向上:独自性が担保されることで企業のブランド価値が向上し、顧客からの信頼や市場シェアの拡大につながる
- 収益の増大:他社とのライセンス契約や権利譲渡により収益が得られる
- 投資やM&Aに対するアピール:企業の独自性が可視化され、企業全体の価値の向上につながる
- リスク管理:他社の知的財産権を正確に把握することで、トラブルを回避して円滑に事業を進行できる
これらの成果を得るために、多くの企業で知的財産戦略の立案が進められています。知的財産戦略を有効活用すれば、事業環境が絶えず変化する現在でも、自社に有利な市場を安定して確保できるようになるのです。
デジタル変革時代における知財戦略の重要性
知的財産戦略は、このデジタル変革時代で企業が存続していくために重要な役割を担っています。
近年のインターネットの目覚ましい普及に伴い、誰もが多くの情報にアクセスできるようになりました。これにより、多くの業界で発展が促された一方で、企業の知的財産が脅かされています。公開した自社独自の発明やノウハウの情報は瞬く間に拡散され、誰もが簡単に参考にできてしまうためです。
このような状況で対抗策を何も用意していないようであれば、自社の競争力を維持することは困難といえるでしょう。
そこで企業に求められる防衛策こそが、知的財産戦略なのです。
知的財産戦略によって、自社の知的財産を保護、あるいは活用することで競争力を保ち、持続的な企業成長を推進できます。
経営戦略と知財戦略の統合アプローチ
ここで、経営戦略と知的財産戦略の関係性を把握しておきましょう。
知的財産戦略は、単体で考えるものではありません。マーケティング戦略や研究開発戦略といった、経営戦略を実行していくための手段として検討されるものです。
知的財産戦略は経営戦略の一部、ともいえます。
例えば、マーケティング戦略を推し進めるために、知的財産戦略としてブランド要素の獲得を目指し商標権を取得することが挙げられます。また、研究開発戦略として、技術領域の特定と保護のために、特許出願を進めることもあるでしょう。
経営戦略と知的財産戦略は不可分のものであり、経営戦略を立てていく上で知的財産戦略が重要な役割を果たすことがわかります。
最新トレンドから見る知的財産戦略の進化
知的財産戦略のトレンドは、日々目まぐるしく変わる社会情勢に伴い、定期的にアップデートされます。ここで最新のトレンドを以下の3つの観点から確認し、知的財産戦略の現状への理解を深めていきましょう。
- AIやデジタル時代の知的財産戦略の再構築
- オープンイノベーションと知財の役割
- 標準化戦略とデファクトスタンダードの獲得
AIやデジタル時代の知的財産戦略の再構築
2025年現在、AIの活用やデジタル化が進む中で、知的財産に関連する制度の変革が急がれており、それに付随して知的財産戦略の柔軟な再構築が求められています。
AIの進展に伴い、生成AIによって作られた画像や文章などのコンテンツを活用する動きが広まりつつあります。しかし現行法上では、AIが作成したコンテンツの著作権の帰属先が明確に決まっていません。コンテンツの権利保護の問題に対応するために、新しいルールや枠組みが必要とされています。
また、AIによって生成されたものを含むデジタルコンテンツの権利保護は、もはや一国の問題にとどまりません。各国で知的財産権に関する法制度が異なるため、国際的な調整が必要なのです。
このように、知的財産に関する制度は今、まさに変革の最中にあるといえます。企業が知的財産戦略を有効に実施するためには、制度の動向を的確に察知し、柔軟に対応を決めていくことが求められます。
オープンイノベーションと知財の役割
オープンイノベーションの考えに基づいて、知的財産を活用することも最新のトレンドです。
オープンイノベーションとは、自社のイノベーションを推進していく上で、組織の内外を問わずあらゆるリソースを駆使し、新たな価値を創出することです。市場競争の加速や消費者ニーズの複雑化が進む昨今、自社にはないスキルや視点を得て対抗するための手法として活用する動きが広まっています。
従来の知的財産戦略では、自社の市場優位性を高める、あるいはブランドとしての価値を維持することを重要な目的としていました。しかし現在では、オープンイノベーションの考えによって、ライセンスの権利共有など、社内の知見を社外に循環させることも重要視されているのです。
ただし、知的財産を共有する目的はあくまでビジネス強化にあります。単なる無償または定額でのライセンス提供を推奨するものではないことには注意が必要です。
関連記事:オープンイノベーションとは?要素やメリット、ビジネスにおける重要性を解説
標準化戦略とデファクトスタンダードの獲得
標準化戦略を立ててデファクトスタンダードの獲得を目指すこと、そして知的財産戦略を実行することを並行して進める動きもあります。
標準化戦略とは、ある製品やサービスで一定の規格を決め、市場に普及させる戦略のことです。これが社会的に標準化した状態を、デファクトスタンダードといいます。
身近な代表例としては、PCのキーボード配列である「QWERTY配列」が挙げられるでしょう。QWERTY配列は、公的に定められている規格ではないものの、多くの企業が製造するキーボードで採用されています。キーボードの利用者としても、この配列に慣れ親しんでいるため「ほかの配列のキーボードを使おう」と考える人は少ないはずです。
こうしたデファクトスタンダードの獲得は、知的財産戦略と併せることで大きな利益の創出が期待できます。標準化した製品やサービスを知的財産権で保護することで、市場優位性の確保、またライセンス使用料の獲得などをより効果的に進められるのです。
関連記事:デファクトスタンダードとは?業界標準になるまでの流れと企業戦略を解説
知的財産戦略を立案する流れとポイント
ここからは、知的財産戦略を立案する流れとそのポイントを解説します。知的財産戦略は大まかに以下の手順で進められます。
- 自社の経営環境と知財ポートフォリオの現状分析と評価
- 事業戦略と連動した知財戦略の立案
- 知的財産戦略を実行するための管理体制の整備や構築
- 知的財産権に関する手続きなどの確認
- 知財意識を向上させるための社内教育や仕組みづくり
自社の経営環境と知財ポートフォリオの現状分析と評価
知的財産戦略を立てるにあたり、まずは自社の経営環境と知的財産ポートフォリオの現状分析と評価を進めていきます。
その際は、以下の項目に基づいて検討していきましょう。
自社の市場におけるポジションや課題を把握する
知的財産戦略の立案のためには、自社の置かれている市場内でのポジションや課題を洗い出すことが大切です。知的財産戦略の方向性を決める足がかりとなります。
この際にお勧めしたい手法が、「SWOT分析」です。SWOT分析は、自社の事業の状況を、強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の4つの項目で整理して、分析する方法です。こうしたフレームワークを用いることで、自社の市場でのポジションや課題を、体系的かつ明確な根拠を持って把握できます。
競合企業の知財動向を分析する
自社が現在保有している知的財産について、相対的な評価を行うことも欠かせません。競合企業がどのような知的財産を保有しているのか調査し、自社との差異を確認していきます。
調査で得た競合企業の情報は、複数の知的財産を一つの観点に基づいて集合体にまとめる「知的財産ポートフォリオ」によって管理しましょう。続けてポートフォリオを参考に、自社を含む全企業の状態をグラフや表に記す「パテントマップ」を作成してまとめていきます。
これにより各社の知的財産の情報が視覚的に整理されることで、自社の市場での立ち位置や業界内での動向を客観的に分析できるようになります。
事業戦略と連動した知財戦略の立案
現状分析によって洗い出された自社の事業課題、また事業成功につながるヒントから、知的財産戦略を決定します。経営資源には限りがあるため、メリハリを付けた知的財産戦略の立案が求められます。
なお、知的財産戦略を立案する際の考え方として、基本となるものが以下で紹介する「オープン&クローズ戦略」です。
オープン戦略とクローズ戦略の活用
オープン&クローズ戦略とは、自社の知的財産を広く公開するか、または独占して権利化するかを使い分ける知的財産戦略の手法です。自社保有の知的財産について、市場拡大のための「オープン戦略」、利益確保のための「クローズ戦略」のどちらで活用するのかを一つずつ決めていきます。
より具体的に説明すると、オープン戦略は、先ほどの標準化戦略と同様に自社の知的財産の標準化を目指すために、競合企業での使用を積極的に促していくものです。
一方、クローズ戦略は、発明を特許出願して権利化し、他社がその技術を無断で実施(利用)できないように独占する手法といえます。
経営の戦略や環境によっては、独占して使用料を取るよりも、広く公開して普及を目指したほうがかえって利益につながることもあるため、この2つの使い分けが重要なのです。
分析した内容を基に、しっかりと吟味した上でいずれの方針で知的財産戦略を進めていくのかを決めていきましょう。
関連記事:新規製品開発・新規事業⽴上げ時に強化すべき知財戦略
知的財産戦略を実行するための管理体制の整備や構築
知的財産戦略の立案が完了したら、それを効果的に実行していくための部門を立ち上げます。そして、部門を中心として社内全体で知的財産の重要性を意識できる管理体制の整備、構築を進めていきます。
具体的には、以下の2つの視点から体制を整えていくことが成功のポイントです。
知的財産の出願や弁理士と連携できる体制
知的財産権を取得するために、弁理士との連携を図り出願体制を整えておくことが求められます。
特許出願といった知的財産を権利化する手続きは、特許事務所に所属する弁理士を通して行われます。自社の知的財産権を的確に主張するために、信頼できる特許事務所を見つけることが大切です。
依頼先の特許事務所を選定する際は、自社の分野に精通している弁理士が在籍しているかどうかを確認することがポイントです。事務所のホームページやパンフレットからこれまでの実績を調べてみましょう。
競合企業の知財動向の分析やチェック体制
自社の知的財産戦略立案後も、競合企業の知的財産に関する動向を引き続き分析する体制を整えておく必要もあります。これは、自社内で新たな戦略を立て続けることはもちろん、他社からの権利侵害に迅速に対応するためです。
権利侵害が発見された場合には、速やかに経営層や関係部署に共有することで、早い段階での対応を進められます。
知的財産権に関する手続きなどの確認
知的財産戦略の管理体制の構築と並行して、知的財産権取得に関する手続きについても確認しておきたいところです。
知的財産権を取得するためには、その権利の種類によっても異なりますが、一定の期間がかかります。例えば、特許権を取得するためには、手続きが順調に進んだとしても1年半から2年半程度を要するといわれています。
こうした中で、知的財産戦略をスムーズに進めていくためには、あらかじめ手続きについて把握し、途中で滞らせないことが重要です。
以下で特許権の場合を参考に、権利を取得するための手続きを確認しておきましょう。
| 手順 | タイミング | 手続き |
|---|---|---|
| 出願 | 出願日 |
・特許庁に出願書類を提出する ・出願手数料を納付する ・出願番号を取得する |
| 出願から1年間の管理 | 出願日から1年 |
・国内での優先権出願を検討する(改良発明がある場合) ・海外出願を検討する |
| 公開前の管理 | 出願日から1年半 |
・改良発明の出願を検討する ・出願取り下げの判断を行う |
| 公開 | 出願日から1年半後 |
・出願内容が公開公報として公表される ・補償金請求権が発生する |
| 審査請求期間中の管理 | 出願日から3年 |
・審査請求を実施するか判断する ・審査請求のタイミングを検討する ・早期審査制度を活用するか決める |
| 審査請求 | 出願日から3年以内 |
・審査請求手続きを実施する ・審査請求料を納付する |
| 審査対応 | 審査請求後数カ月~数年 |
・拒絶理由通知への対応をする ・意見書と補正書を提出する ・面接審査の活用を検討する |
| 特許査定や登録 | 審査後 |
・特許査定を確認する ・3年分の特許料を納付する ・特許原簿への登録を済ませる |
特許権を得るためには、多くの手順がある中でさまざまな手続きへの対応が求められます。手続きについて、さらに詳しい内容を知りたい場合には、以下の特許庁の資料で説明されていますので、こちらを参考にしてください。
(参照:特許庁『出願の手続き(令和7年度版)』)
知財意識を向上させるための社内教育や仕組みづくり
知的財産戦略を推進していくには、自社全体で知的財産の重要性を理解することが大切です。そのために、知的財産に関する社内教育や意識向上を促せる仕組みづくりに取り組むことが求められます。
例えば、知的財産の社内教育の方法には、教育プログラムや発明提案書の書き方を学ぶワークショップ、知的財産に関するe-ラーニングなどの実施が挙げられます。また、意識向上の仕組みづくりとしては、発明に関する補償制度や褒賞制度を充実させるといった、社員のモチベーションにはたらきかける策を講じると良いでしょう。
こうした取り組みが、自社内の知的財産に対する意識を醸成し、知的財産戦略を成功させる可能性を高めていくのです。
大企業で見られる知的財産戦略の課題と改善策
最後に、大企業での知的財産戦略で発生し得る3つの課題と、その改善策を解説します。
- 知財部門と事業部門の連携強化
- 投資対効果の明確化と経営層への説明
- 国内外での知財係争リスクへの対応
知財部門と事業部門の連携強化
知的財産戦略を進めていく上では、知的財産部門と事業部門の密接な連携が不可欠であり、それなくして成功は見込めないでしょう。
先に説明した通り、知的財産戦略は、単体で考えるものではありません。マーケティング戦略や研究開発戦略といった、経営戦略を踏まえた上で進めていかなければ、実効性のある戦略の策定や改善にはつながらないのです。
従って、知的財産部門には、マーケティング部門や研究開発部門など事業部門との連携体制を構築しておくことが求められます。事業部門との定期的なミーティングの場を設けるなど、日ごろからコミュニケーションが取れる体制を整えておきましょう。
投資対効果の明確化と経営層への説明
知的財産戦略をうまく活用できない理由として「知的財産権は既存の事業や研究成果などを保護し、管理するための防御的手段である」という認識が、経営層にあるケースも少なくありません。この状況では、市場優位性の確保やブランド価値の向上などは見込めず、知的財産戦略の効果を最大限発揮できないでしょう。
そこで知的財産部門には、知的財産戦略の役割について経営層に説明し、重要性をきちんと理解してもらうために行動することが求められます。その際には、権利を取得しない場合と権利を取得した場合の利益を算出し、投資対効果の観点から説明することがポイントです。
知的財産戦略によって期待できる利益を数値として視覚化することで、経営層からの理解も得やすくなります。
国内外での知財係争リスクへの対応
知的財産戦略を進めていくには、知財係争に対応するための万全な準備も必要です。
前述の通り、インターネットが普及したことにより、企業の発明やノウハウといった情報に対して外部からのアクセスが容易になっています。これにより、知的財産権侵害が国内外で起きやすくなっており、知財係争に巻き込まれるリスクも高まりを見せているわけです。
もしトラブル対処のために裁判へと発展すれば、時間も費用も膨大にかかり、大きな損失が生じてしまいます。
そこで企業には、知的財産権侵害を未然に防ぐためのリスク対応が求められます。知的財産権の取得と適切な管理に取り組むことはもちろん、秘密保持契約やライセンス契約などの契約によって権利が保護できるように準備しておくことが重要です。
また、市場の監視も実施し、権利侵害の可能性があった場合に早急に対応できる体制を整えておきましょう。
監修
弁護士法人ブライト 和氣良浩 弁護士
知的財産戦略は企業の競争力を向上させ、事業を成長させるために重要
本記事では、知的財産戦略について詳しく解説しました。
知的財産戦略とは、知的財産を保護、または活用する経営手法です。推進していくことで、市場優位性の確保やブランド価値の向上、また収益の増大といった利益が期待できます。
国内外で市場競争が激化している中で、自社の競争力を保ち、事業を成長させていくために、知的財産戦略を進める体制を整えましょう。
なお、知的財産戦略に関する課題を抱えている場合には、経営支援サービスの「HiPro Biz」に相談ください。知的財産に対する経験と知識の豊富なプロ人材が、戦略の立案から課題の洗い出しまで幅広くサポートします。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)




