理念を自分ごと化する仕組みづくり。「インナーブランディング」を採用成功や離職防止につなげる具体策とは
2025年09月26日(金)掲載
- キーワード:
採用難が続き、多くの企業がコーポレートサイトの刷新やSNS活用など外部に向けた発信を強化しています。しかし、伝えるべき価値やメッセージが曖昧なままでは、かえって空回りしてしまうケースも少なくありません。こうした中で注目されているのが、自社の理念や魅力を明確に言語化し、社員一人ひとりに浸透させる「インナーブランディング」の考え方です。
インナーブランディングは単なる社内向けスローガンにとどまらず、エンゲージメント向上や離職防止、さらには企業の持続的成長を支える基盤ともなります。インナーブランディングを進め、社内に浸透させていくには、どのようなステップが必要なのでしょうか。編集者、プランナーとして数多くの企業を支援するプロ人材、宮崎 慎也氏に、その要諦を聞きました。
■取り組みに悩む企業、「そもそもインナーブランディングとは?」から始まる支援
■「Whyの整理」から始まる4ステップに社内横断で取り組む
■内定承諾率向上や離職減少——インナーブランディングによって生まれる成果
■まとめ
取り組みに悩む企業、「そもそもインナーブランディングとは?」から始まる支援

——人材不足が深刻化する中にあって、「インナーブランディング」の重要性に着目する企業が増えているようです。
宮崎氏:ここ4〜5年、インナーブランディングの必要性が叫ばれるようになってきましたね。私のもとへも「自社のスタイルを言語化したい」「ミッション・ビジョン・バリューを根付かせたい」といった相談が多く寄せられています。
採用は売り手市場が続き、個人が会社を選択できる立場になりました。給与面などのメリットだけでなく、企業姿勢や社会的な価値にも共感できなければ、従業員ははたらき続けられません。
そのため企業側では、自社の魅力や強みを言語化し、従業員が自分ごと化できるようにしなければならないという機運が盛り上がっているのです。最近では人的資本経営の観点で外部発信する際にも、人がいきいきと活躍できる環境づくりが重視されるようになってきました。
——宮崎さんは、企業のどのような悩みを聞くことが多いですか。
宮崎氏:目的としては採用成功や離職防止など、はっきりとしていますが、「そのために何をすればよいのかわからない」という企業が多いです。エンゲージメントなどの流行ワードもあって取り組もうとしていますが、「そもそもインナーブランディングとは何か?」という状態から始まることが少なくありません。
——インナーブランディングが必要な企業の特徴とは?
宮崎氏:自社のミッション・ビジョン・バリューや価値観があっても、それをうまく語れず、自分たちの仕事に結びついていないケースが見受けられます。極端な場合は「自社のビジョンは何だったかを答えられない」ということもありますね。
とはいえ、自分ごと化は簡単ではありません。ミッション・ビジョン・バリューは抽象的な言葉で作られていることも多く、日々の仕事で意識することは少ない。部門やチームごと、あるいは個人ごとに落とし込んでいく必要があるのです。
「Whyの整理」から始まる4ステップに社内横断で取り組む
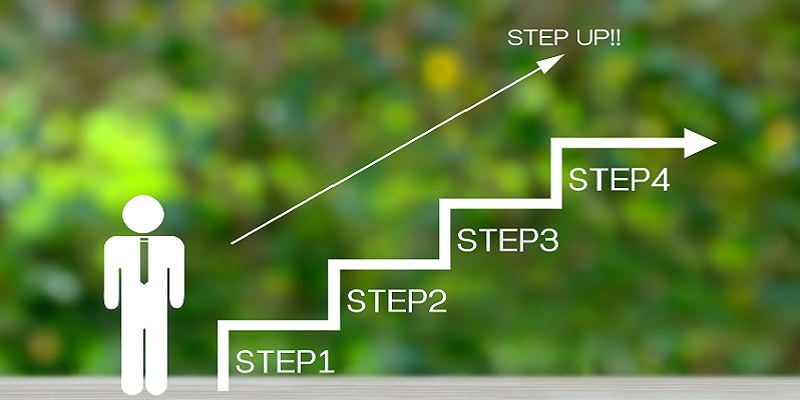
——インナーブランディングを構築するためのステップについて教えてください。
宮崎氏:何をやったらいいかわからない。これが最初の問題なので、支援の際は状況整理から始めることが多いです。
まず取り組むのは「Why」の整理です。採用を増やしたい、エンゲージメントを高めたいなど、なぜインナーブランディングが必要なのか目的を整理し、望ましい状態をイメージします。これは人事だけのスコープではありません。目的の背景には人事の課題はもちろんのこと、社内広報の課題もあれば、経営企画観点からビジョンを浸透させて新規事業につなげたいというケースもあります。部署横断で取り組むことで、全社一丸となったインナーブランディングが可能になります。
次に「What」です。企業として従業員に何を伝えたいのか、何を大事にしたいのか、何を世の中に発信したいのか、何を自分ごと化してほしいのかなど、インナーブランディングのコアとなる言葉を整理します。たとえば、「幸せを届けたい」というメッセージでも、自社にとって、その“幸せ”とはどういうものなのかを深堀りして、より精緻な言語化を進めます。
続いて「Who」です。従業員の中でも、特に誰に伝えたいのかを整理します。「若手社員に誇りを持ってほしい」「工場・店舗など現場の従業員にも届けたい」など、これもさまざまなケースがあります。Whoが曖昧なままで、漠然と全社員をターゲットにしてしまうと、メッセージや手法も中途半端なものになってしまいます。
最後に「How」です。どうやって伝えるかを考えます。ウェブサイトや社内報から、社員食堂のテレビまで、企業によって受け入れられやすい手法は異なります。対外的にはコーポレートサイトやSNS、外部メディアもあります。ここは企業のカルチャーや先に設定した「What」「Who」に合わせて手段を明確化し、制作を進める必要があります。
こうしたステップを経て考えないと、How(手法)の部分ばかりに気を取られて時間をかけてしまい、結果的には何もメッセージが伝わらないこともよくあります。
——こうしたステップの中で、企業がつまずきやすいポイントはありますか?
宮崎氏:社内でゴールの共有がうまくいかず、施策を進めるための説得材料を持てずに頓挫してしまうこともあります。インナーブランディングは売上などの数字に短期的につながるものではないので、経営層には中長期的な視点でWhyを理解してもらい、従業員にはその意義を伝えて主体的に動いてもらうことが不可欠です。
担当者にとっても、目的を一朝一夕で達成できる取り組みではありません。その意味では担当者の熱意も非常に大切です。担当者自身が「誰に届けたいか」などの思いを強く持ち、他部署のメンバーや上層部にまで、その思いと目的を強く共有できるようにすることが重要です。
そういう意味では、数字を追いかけたり、作業をこなしたりするだけで単純に進められるものではなく、熱意や機運や社内の雰囲気などを盛り上げていくこともインナーブランディングにとってはとても大切な要素です。
——経営層の理解を得るために取り組みをどのように進めていくのでしょうか。
宮崎氏:私は「Whyの整理」の段階で経営層を巻き込むこともあります。ミッション・ビジョン・バリューを一から作ることもありますし、すでにできあがっている場合でも、経営陣にインタビューして思いを聞き整理します。ボトムアップで進める場合は20〜30代の若手を集めてワークショップなどを開催し、一緒にWhyを整理することもあります。
注意すべきは「人と組織のことだから人事が頑張らなきゃ」と狭い視点になりすぎないこと。経営層はもちろん、広報や経営企画、事業部のメンバーなども巻き込み、プロジェクト化して横断的に取り組んでいくべきでしょう。
内定承諾率向上や離職減少——インナーブランディングによって生まれる成果

——インナーブランディングで自社らしさや魅力を言語化できたとしても、社内に浸透させるには大きな壁があるのではないでしょうか。
宮崎氏:ここに課題を感じている企業はたしかに多いですね。ポイントは「認知、理解、共感、行動」の4段階で取り組むことです。
「認知」は従業員が「こんなビジョンがあるんだ」と知る状態。そのビジョンの中身を「理解」し、「共感」して自分に置き換えて考えられるようにし、自分の仕事のあり方を変えて「行動」へつながるよう支援していきます。
この4段階のそれぞれにおいても、誰に届けたいかを設計することが重要です。「まずは役員の理解を深めよう」「新入社員に認知してもらおう」など、ターゲット×4段階のマトリクスで施策を細分化すると全体像がつかみやすくなります。対外的な発信ではターゲットを精緻に考えるのに、社内では従業員を一括りにしてメール1本で済ませてしまうような企業も少なくありませんが、これではメッセージが届きません。
たとえば、認知フェーズであればポスターやメールだけでもいいかもしれませんが、理解や共感のためにはより深いコミュニケーションが必要になります。さらに、行動の段階では、評価制度や社内アワード、新規事業コンテストなど具体的な仕組みを設けて従業員を後押しすべきでしょう。社内で一気通貫することも重要で、現場が意識して動いているのに上層部が意識していないと、一気に全体の士気が下がってしまいます。そのため、役員など上層部からの発信も重要です。
——インナーブランディングの取り組みによって、どのような成果が生まれるのでしょうか。
宮崎氏:ある大手企業では、新卒採用でリクルーターとなる社員が、学生の相談に乗る仕組みを設けています。入社2〜3年目の社員がリクルーターを担い、求職者を入社までサポートしています。これができるのはインナーブランディングの取り組みがあってこそ。人事が動いて社内からリクルーターを集め、研修やワークショップを通じ、自社を自分ごと化して語れるようにしたことで、リクルーターとなる社員が自分ごと化した言葉で学生と向き合うことができています。その結果、内定承諾率が向上しました。
別の企業では、離職者を減らすためにエンゲージメント調査やアンケートで退職理由を明らかにし、会社への不安に対処しています。退職理由の中で多かったのが「会社がどこに向かっているかわからない」という不安です。これを解消するため、企業の方針を明確に言語化し、離職が多いゾーンに対して適切な手段ではたらきかけをし、キャリアのイメージを描けるようにしました。
離職理由がはたらき方や労働条件などの問題であれば個別で改善できますが、「会社の将来への不安」など抽象的な問題には、インナーブランディングを通じて中長期的に取り組む必要があります。成果が現れるまでには数年を要することもあるため、取り組みを進める部門担当者にも経営層にも、未来を見据えた持続的な取り組みが求められます。
——インナーブランディングの取り組みを強化したいと考えている企業は、外部プロ人材の力をどのように活用すべきでしょうか。
宮崎氏:最も苦労するのは「Whyの整理」でしょう。ここがうまく進まないと、社内を混乱させてしまうかもしれません。外部のプロを頼る際には、方向性が見えなくても形が整っていなくても構わないので、入り口の段階で相談していただきたいですね。
また、最終的な「How」につながるアウトプットのイメージを持てないと、取り組みはなかなか進みません。クリエイティブな要素も含めてアウトプットの具体像を描く意味でも、知見を持つ外部のプロの力を活用すべきだと思います。こうした材料を持つことができれば社内での理解が得られやすくなり、取り組みが加速度的に進んでいくはずです。
【プロフィール】
株式会社イランコッペ 代表取締役 宮崎慎也(みやざき・しんや)
編集者・プランナー。大学卒業後、2011年に編集工学研究所に入社し、情報編集技術やクリエイティブワークを学ぶ。2018年にメディアカンパニーCINRAでプランナーを経て、2023年に独立。企業や大学、地域のインナー/アウターブランディングを手がけ、情報企業やIT企業、化粧品会社などのミッション、ビジョン、バリューの策定を行う。1987年生まれ、上智大学経済学部卒業。ワシントン大学IBPプログラム修了。宣伝会議コーポレートブランディングカンファレンス登壇。
まとめ
採用市場が変化し、人的資本経営が求められるようになった今、インナーブランディングは企業の成長に重要な要素となりました。インナーブランディングは短期的な成果が見えにくい一方で、採用成果の改善やエンゲージメント向上、離職防止など、中長期的には大きな成果を期待できます。経営層や現場を横断して社内の理解を深め、効果的に取り組みを進めていけるよう、「HiPro Biz」でプロ人材を活用してみてはいかがでしょうか。
▼HiPro Biz 人事関連資料
・OJTを問い直す ~現場任せから「戦略的OJT」への転換に向けて~/パーソル総合研究所 上席主任研究員 佐々木 聡氏
・採用難時代の人事責任者が読むべきプロ人材活用術
・ジョブ型等の輸入型マネジメントを考察する研究/パーソル総合研究所 上席主任研究員 佐々木聡 氏
・【パーソルグループ事例】 人的資本レポートの作成フロー
・「反DEI」の潮流とこれから/パーソル総合研究所 上席主任研究員 佐々木聡 氏
・導入事例のご紹介~人事編~
・【“課題ありき”だから、分かりやすい!】HiPro Biz 活用ポイントガイド(人事編)
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)




