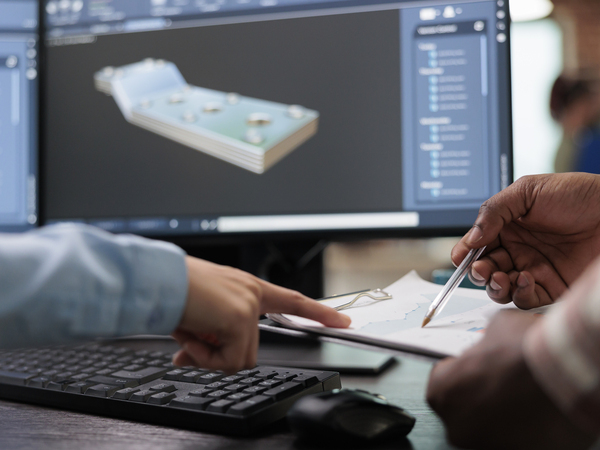「なぜ海外工場の品質は安定しない?」その“もどかしさ”を解消する品質管理の4要素
2025年09月18日(木)掲載
海外に生産拠点を持つ製造業にとって、海外工場の品質保証は大きな課題です。文化や言語の違い、人材不足、データに基づくマネジメントの弱さ——。現場で起こる小さなズレの積み重ねは、不良率に直結します。では、この課題を乗り越えるには何が必要なのでしょうか。
お話を聞いたのは本多 正信氏です。大手メーカーで海外工場の品質改革を担当した本多氏が行ったのは特別な手法ではなく、「品質管理の基本」の徹底と現地社員との協働、そして、IoTやAIといったテクノロジーを柔軟に取り入れることでした。
ここでは本多氏に「海外工場の品質保証が難しい理由」と「改善のために必要なこと」を伺いました。現場視点と最新技術をどう組み合わせるか、その実践知は海外拠点を構える日本企業にとって大きな示唆となるはずです。
海外工場で品質保証が難しい理由

——海外拠点での製品の品質保証に課題を抱える製造業は多いです。品質保証が難しい原因はどこにあるのでしょうか?
本多氏:大前提として、品質管理には以下の4要素が必要です。
・設計品質の確保(設計の完成度)
・部品品質の確保(サプライヤー品質のコントロール)
・製造工程品質の確保
・出荷品質の確保
品質に課題があるということは、この4要素が十分に機能していない可能性が考えられます。この原則は日本でも海外でも同じですが、海外工場で実践する難易度は日本より高いと思います。
——難易度が高くなる理由について教えてください。
本多氏:海外工場での品質管理が難しい原因は大きく2つあります。
まずは日本人のマネジメントの特性です。日本人は精神面を重視する傾向にあり、データやファクトに基づくマネジメントが弱い傾向があります。
それに関連して、日本人特有のコミュニケーションにも課題があると思います。技術的で論理的な説明が苦手で、日本人にとっての当たり前を明確にしないまま進めた結果、現地社員とのコミュニケーション不全が起きてしまうケースは多いです。もちろん言語の壁はありますが、それ以前のやりとりを見直す必要があるでしょう。
——2つ目は何でしょうか?
本多氏:製造業の人気の低下です。日本の製造業はかつてほどの人気がなく、今は人材が集まりにくくなっています。
その原因として、給与水準の低さと技術開発への消極性が挙げられます。今の時代ならAIをはじめとするIT分野に進んだ方が収入は高いですし、ものづくりをするにしても海外企業の方が新しい技術開発に積極的な傾向があります。結果として、日本の製造業はエンジニアにとって魅力を失いつつあるのだと思います。
海外工場で品質を安定させるために必要なこと

——海外工場の品質管理を向上させるために、何をすればいいでしょうか?
本多氏:基本は、最初に申し上げた4要素を着実に実行することです。今はAIやIoTを活用し、効率的にデータを収集したり分析できるようになりました。まずは数値を基に課題を特定し、事実を明確化することが重要です。
ただ、やり方を変えて運用していくのは簡単なことではありません。また、駐在員は多忙で、新しい取り組みに十分な時間を割けないのも理解できます。だからこそ、現地社員と課題を共有し、一緒に改善に取り組むこと、そのための人材育成を並行して進めることが重要です。その過程で、勤勉という日本人の強みも発揮しやすいと思います。
その際、外部人材を頼るのも一つのアイデアです。データドリブンでものづくりの品質を保証するには、ロードマップをつくり、計画を立てる必要があります。その部分だけでも外部の力を借りられると、駐在員の負荷は大きく下がるはずです。
——現地社員とコミュニケーションを取る上で、気をつけることはありますか?
本多氏:基準を示すのが重要です。具体的には「きちんと」「ちゃんと」といった曖昧な表現を使わず、その定義を明文化し、口頭やチャットだけで済ませず文書に残して、規定基準を共有するとよいでしょう。日本の工場であればある程度共通認識があり、何かあれば周囲がカバーしてくれることもありますが、海外工場で同じようにはいかないでしょう。日本人は基準を曖昧にしがちですが、明確な基準がなければ品質が不安定になります。
その上で、品質管理の4要素のうち、製品ごとに何に注力すればよいかを見定め、日々愚直に品質確認を繰り返すことが極めて重要になります。これは品質保証の基本として一般的な教材にも書いてあることですから、現地社員との合意も取りやすいと思います。
——海外工場の品質改善例を教えてください。
本多氏:ヨーロッパとアジアの工場で品質傾向管理(※)を導入し、品質改善を行った経験があります。その結果、不良率を3分の1まで低減することができました。
とはいえ、特別なことはしていません。重大な品質問題をきっかけに、原因を徹底的に突きつめ、どの工程をコントロールすれば改善できるかをデータで可視化し、優先順位を決めて取り組んだのです。そうやって原因を一つずつ、現地社員と一緒につぶしていきました。
その上で、重要品質項目ごとの品質変動を毎日確認し、異常な方向にデータが動いたら即対処する。これの繰り返しです。
※重要品質項目のデータを収集・分析してパターンを把握し、品質異常の兆候を早期に検知して対策を講じること
必要なのは「品質管理の基本の見直し」と「テクノロジー活用」

——あくまで基本となる4要素を徹底する。実施することはシンプルですね。
本多氏:品質管理の方法論は確立されています。前述した品質傾向管理についても、ISO9001やIATF16949で標準化されている手法です。
ただ、こういった基本的な方法論をそもそも知らない人が増えているように思います。現在私が支援している企業の規模は数百億〜数兆円までさまざまですが、品質管理の根底にある問題点は共通しています。
たとえば、ある品質項目の規格を満たしているかどうかだけでその品質の良否を判断し、出荷保証をしてしまうケースが見られます。「昨日も今日も規格に収まっている」ではなく、本来は「昨日と今日で品質がどう変化しているか」を確認しなければいけません。ギリギリでの合格であれば改善が必要ですが、そこまで踏み込めていない。
こういった基本が抜けていることが多いように感じます。今一度基本を学び直し、品質管理をただの作業にしないことが重要です。
——海外工場に駐在する社員の育成が必要ということでしょうか。
本多氏:そうですね。駐在員が品質管理の方法論を身につけるのはもちろん、IoTやAIなど最新技術を習得することが重要です。古いやり方を踏襲していてはうまくいきませんので、個人の努力に任せるだけでなく、会社として教育の機会を与えるような仕組みの整備が求められます。
また、経営層が海外工場の品質管理の方針を明確に示すことも大事です。「IoTの積極活用を会社としてサポートする」と宣言するだけで、現場は動きやすくなるのではないでしょうか。
日本の製造技術が世界トップクラスだった1980〜1990年代は、品質を人と時間で支えていましたが、今ははたらき方が変わり、当時と同じようには時間をかけられなくなっています。本来であればその不足分をAIやIoTで補うべきですが、対応が遅れていることに大きな問題があると思います。
今やIoT化はセンサーと小型コンピュータがあれば実現できます。たとえばカードサイズの超小型コンピュータでもデータ取得はでき、従来のように多大なコストをかけずともデータドリブンな品質管理が可能になるのです。
さらにいえば、品質管理の完全自動化も現実的な選択肢となりつつあります。IoTでセンサリングし、データを取得し、それを基にAIに判定させ、異常があればAIに製造工程を自動制御して正常値に戻す。こうしたテクノロジーの力を用いれば、「不良を出さない工場」を実現することも可能でしょう。
——最後に、海外工場の品質向上や安定化に取り組む大手製造業の担当者や、海外拠点を持つ製造業の経営者にメッセージをお願いします。
本多氏:品質に関わる全てのことは机上ではなく、製造の現場で起きています。だからこそ現場を丁寧に見つめる姿勢が重要です。それは昔から言われてきたことで、私も何度も教わり、常に意識してきました。品質管理に携わる皆さんには、その姿勢を忘れないでいただきたいと思います。
一方で、品質はあくまで守りです。それだけでは日本のものづくりはシュリンクしますから、日本企業には積極的な技術開発に挑み、新しい製品を生み出すという攻めの姿勢も不可欠です。守りと攻めの両輪を意識することが、これからのものづくりに不可欠だと考えています。
【プロフィール】
本多 正信(ほんだ・まさのぶ)
電気電子および、情報工学系に係る基礎技術教育修了後、電機メーカーにて三次元電磁場解析プログラム開発、映像デバイスの開発、設計業務に従事し、米国大手コンピューターメーカーへの製品納入に貢献。その間、TQMにおける技術管理(デザインレビューを含む)とナレッジマネジメントの方法論を習得した。また、技術論文投稿と特許申請にも力点をおき、1997年に映像デバイスに係る国際学会SIDより最優秀論文賞を受賞。その後、日本国内工場および海外(ドイツ、中国)工場において、シックスシグマブラックベルトとしてDMAIC手法を用いた品質保証や品質管理業務を実践する一方、品質責任者としても海外工場品質を統括する品質マネジメントシステム改善に努めた。さらに、電子部材メーカーにて、IATF16949品質マネジメントシステムを立ち上げるとともに、電子材料の微細欠点を自動検出するAI検査システムを導入して、検査精度向上と省人化を実現。同時に、機械学習プログラムとビッグデータを活用した多変量解析技術の業務適用にも尽力した。現在は、ものづくりにおける品質課題を常にトリガーとしながら、実践的真因分析手法とデータドリブンの論理的改善手法、およびIoT技術とを組み合わせた製品品質改善支援活動と、ものづくりの現場に真に役立つQMS構築支援活動を、「HiPro Biz」の登録プロ人材として行っている。
まとめ
海外工場の品質保証に必要なのは特別なノウハウではなく、基本の徹底です。品質管理の4要素をデータドリブンで管理し、現地社員と共に改善を進めることが第一歩です。そのためには、明確な基準づくりと、IoT/AIを活用した効率的な品質管理体制の構築が重要な要素となります。
「HiPro Biz」には、海外工場の品質改善や仕組みづくりに豊富な実績を持つプロ人材が登録しています。自社の課題に合わせて品質管理の基盤を整えたいとお考えの方は、ぜひ一度「HiPro Biz」へのご相談をご検討ください。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)