CO2を「コスト」から「価値」へ。CO2回収ビジネスが拓く、企業の新たな可能性
2025年10月31日(金)掲載
- キーワード:
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、CO2回収ビジネスに活路を見出す企業が増えています。工場などから排出される二酸化炭素を回収し、製品などに利活用するこの取り組みは、脱炭素社会の実現に向けて期待の集まる新たなモデルです。
しかし、事業化にはさまざまな課題が立ちはだかっているのも事実です。企業がCO2回収ビジネスに挑むために必要な取り組みとは何か。カリフォルニア大学バークレー校化学Ph.D.(※1)を取得し、同分野のプロ人材でもある隅田 健治氏に伺いました。
※1 Ph.D.とは、Doctor of Philosophyの略称で、日本でいう博士号に相当
日本のCO2回収ビジネスは「投資フェーズ」
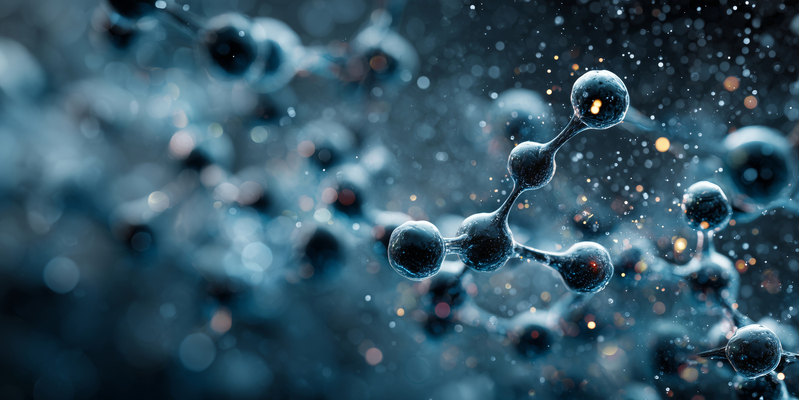
——昨今、CO2回収ビジネスが注目を集める理由や社会的背景を教えてください。
隅田氏:最大の理由は、近年ますます過酷さを増している気候変動問題です。CO2をはじめとした温室効果ガスの排出による気温上昇は、最近では肌で感じられる程度にまで顕著になりました。このまま気温上昇が続けば、日本の社会や産業にも致命的な影響が及びかねません。
こうしたなかで、日本は2050年までにCO2の排出を実質ゼロにする、カーボンニュートラル実現を目指していますが、企業に課せられた役割は決して小さくありません。むしろ、企業にCO2削減を義務付ける法律が施行されるなど、主要なプレイヤーに位置付けられています。その点、CO2回収ビジネスは、自社のCO2排出削減に貢献するのはもちろん、脱炭素社会における新たな事業の柱にもなることから、多くの企業が期待を寄せています。
——日本におけるCO2回収ビジネスの現状を教えてください。
隅田氏:特に注目度が高いのがCCS(Carbon dioxide Capture and Storage)事業です。CCSとは分離・回収した CO2を地中などに貯留する技術で、日本国内では苫小牧沖の海底層への貯留などの実証試験を中心に実装に向けた動きが加速しています。将来的には、回収した CO2を化学品や燃料などに変換する利活用も期待されています。
世界では2000年代後半からCCSの事業化が進んでおり、2023年時点で計画中や整備中も含めれば約3.5億トンのCO2を回収できる見込みでした。(※2)
日本でも2023年に経済産業省が「CCS長期ロードマップ」を策定し、国内企業によるCCSのバリューチェーン構築などを支援しています。しかし、諸外国に比べると実装・事業化において遅れを取っているのが実情です。政府は“Advanced CCS Projects”を選定し、2030年までに600〜1200万トン /年、2050年に1.2〜2.4億トン /年の貯留を目標としていますが、このターゲットを達成するには産業基盤の整備を急ぐ必要があります。(※3)
CCSの事業化には、CO2の分離回収技術はもちろん、液化貯蔵や輸送など、さまざまな技術や設備、ロジスティクスの構築などが必要で、実現に向けての課題は少なくありません。日本におけるCO2回収ビジネスの現状は、そうした壁を一つひとつ乗り越え、実現に向けての環境整備を進めている「投資フェーズ」と言えます。
※2 出典:「資料8 世界のCCSの情勢について 年度レポートの解説(Global CCS Institute)」(経済産業省)
※3 出典:「CCS長期ロードマップ検討会 最終とりまとめ」(経済産業省)
まずはCO2の分離回収の取り組みに期待
——現状、日本企業がCO2回収ビジネスに取り組むメリットはなんでしょうか。
隅田氏:国内では商業規模での事業化には至っていないものの、実証試験や制度整備が着実に進められています。これを背景に、自社でどのような設備投資を行い、新しいレギュレーションへの対応を早い段階から企業戦略に組み込むことは十分な価値があると思います。とりわけ、政府のGX-ETS(排出量取引制度)は2026年4月から義務化され、過去3年平均で年間10万トン以上のCO2排出企業が対象となる見込みです。(※4)今やCO2排出削減は経営に直結する要素になりつつあると言ってよいでしょう。体制づくりの第一歩として、自社の排出をどのように抑制し、脱炭素社会への移行リスクを低減していくかを戦略的に検討することが重要です。
——CO2の分離回収にはどのような方法があるのでしょうか。
隅田氏:代表的なのがアミン水溶液を吸収液として用いた分離回収法です。工場などで排出されるガスを吸収液に導入し、CO2を選択的に吸収させたのち、吸収液を加熱してCO2を放出します。原理としては古典的ですが、現在も数多くの分離回収設備で用いられています。
ただし、課題も存在します。まず、アミンは腐食性であるため、製造設備で用いる際には水溶液のアミン濃度を抑えなければならず、それに比例してCO2の吸収量も減少します。アミンは酸化することにより劣化してしまうので、定期的に水溶液を交換することも必要になってきます。さらには、吸収させたCO2を回収するには水溶液を加熱することが必要なため、「CO2の回収のためにCO2を排出してしまう」という問題もあります。こうした課題を踏まえ、近年ではアミン水溶液以外の分離回収法にも注目が集まっています。
その一つが、MOF(金属有機構造体)と呼ばれる固体吸着剤です。MOFは金属イオンと有機配位子が結合した多孔性材料で、CO2の吸着、分離、変換などを可能にします。固体であることから比熱が低く、運用条件によっては再生に要するエネルギーを大幅に低減できる可能性があります。運用コストも抑えられることから、昨今、MOFによる分離回収法を採用する企業も増えており、海外ではパイロットスケールで、燃焼排ガスからの分離や、空気中からのCO2を直接回収するDAC(Direct Air Capture)技術にMOFを活用する例も増えてきています。
とはいえ、MOFによる分離回収法にも、長期利用における耐久性やコストなどの課題が存在し、幅広く利用されるにはもう少し時間を要するのが現状です。工場施設の構造や製造プロセスなどによって分離回収設備の設計も変わることから、専門的な知見を交えた十分な検討が必要になります。その点では、MOFは構造や化学特性を自由に設計できるため、こうした課題の解決に向けて極めて有望な材料といえます。
※4 出典:「資料3 事務局資料」(経済産業省)
CO2回収ビジネスの第一歩は知的基盤と人的基盤の強化
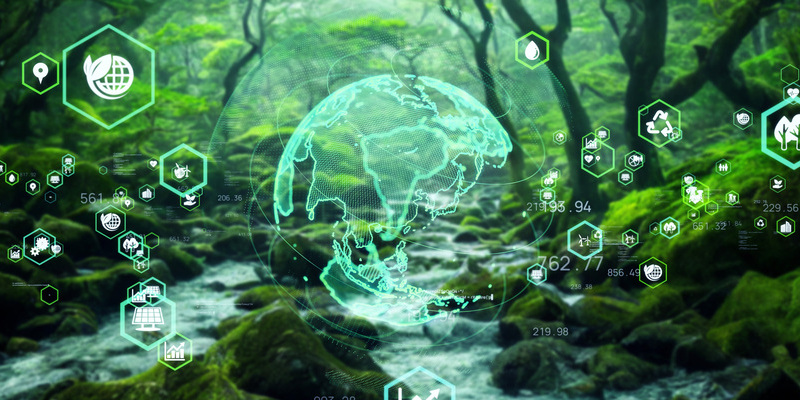
——将来的なCO2回収ビジネスの展開を見据え、今、企業が取り組んでおくべきことは何でしょうか。
隅田氏:先ほども述べた通り、CCS事業をはじめ、日本におけるCO2回収ビジネスは初期段階にあります。貯留したCO2の利活用先も明確には定まっておらず、市場動向にも注視が必要です。こうしたなかで企業に求められる行動は、将来に向けた知的、人的な基盤づくりではないでしょうか。
例えば、経済性に対する評価です。CO2回収ビジネスで得られるコストメリットやCO2削減効果、節電効果などをモデリングして緻密に評価しておく。海外の動向においても参考にできるデータやビジネスモデルも増えてきていることから、このようなモデリングの実施も容易になりつつあります。これにより、どの程度の人員や予算を投入するのが適切かどうか明確になり、体制構築の具体化にもつながるでしょう。
また、CO2回収ビジネスのインパクトを評価するためにも、市場環境の調査や政府、行政の動向を継続的にモニタリングすることが欠かせません。2025年1月に米国がパリ協定からの再離脱手続きを開始し、今後の政策動向に不確実性が生じていることからも分かる通り、CO2回収ビジネスの市場は政府や行政の方針に大きな影響を受けます。したがって、日々の報道のチェックはもちろん、政策決定プロセスに詳しい人材の力を借りるなどして、迅速に情報を収集し、事業戦略に反映できる体制を整えることが重要です。
——人材育成についてはいかがでしょうか。
隅田氏:人材育成は特に重要な課題の一つであり、迅速な対応が求められます。製造業では、環境対策やサステナビリティ推進を担う部署が設けられていて、化学や工学の知識を持つ人材も多く在籍しています。とはいえ、CO2回収ビジネスは環境対策や生産管理といった技術分野にとどまらず、AIやファイナンス、政策など幅広い領域を包含しており、既存の人材だけでは対応しきれないのが現状です。
特に重要なのは、専門性を持った人材採用の強化です。大学や大学院でCO2回収技術の研究を経験してきた人材はもちろん、ビジネス運用に必要なスキルを備えた人材を積極的に採用し、将来の事業展開を見据えた人材ポートフォリオを構築することが望まれます。
一方で、社内にすぐに大規模な専門チームを立ち上げるのは容易ではありません。そのため、外部人材の活用も有効な選択肢です。海外に比べればまだ数は少ないものの、技術とビジネスの両面に精通した人材は確実に存在します。そうした人材を招聘し、長期的な戦略策定や将来に向けたロードマップづくりに参画してもらうことも有効です。
いずれにせよ、今後、CO2回収ビジネスの市場が拡大し、ビジネスとしてのインフラも整備されていくでしょう。確実に訪れる未来に向けて動き出すのであれば、その時期は早ければ早いほど望ましい。言い換えれば、先行して取り組むことで、将来的な企業競争力の向上につながる可能性が高いということです。ぜひ多くの企業にCO2回収ビジネスへの第一歩を踏み出してほしいと願っています。
【プロフィール】
隅田 健治(すみだ・けんじ)
ニュージーランド出身。米国・カリフォルニア大学バークレー校にて、MOF(多孔性配位高分子)分野の権威の一人であるJeffrey R. Long教授に師事し、化学Ph.D.を取得。京都大学iCeMS北川研究室(北川進教授:2025年ノーベル化学賞受賞)にて博士研究員、豪州アデレード大学で独立研究フェローとしてMOFの構造化・機能化を研究。その後、京大発スタートアップ株式会社AtomisでCSOとしてR&Dと技術戦略を主導。現在は独立コンサルタントとして、MOFを中心とした分離・吸着・回収技術の技術評価、経済性分析(TEA)、事業化支援を国内外の企業向けに提供している。カリフォルニア大学バークレー校化学 Ph.D.、アデレード大学MBA(経営学修士)。
まとめ
日本におけるCCS事業をはじめとしたCO2回収ビジネスは黎明期にあります。事業の実現に向けた技術的、制度的な壁も存在しています。しかし、そうした状況だからこそ、先行者利益が期待できる側面もあります。将来的な市場の成熟を見据えて、今のうちにCO2分離回収などを進めることを検討してみてはいかがでしょうか。「HiPro Biz」には、国内外のCO2回収ビジネスの動向やCO2回収技術に精通したプロ人材が多数登録しています。プロ人材の力を借りて、来るべき脱炭素社会に向けた確かな一歩を踏み出してみませんか。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)
