生産性向上を実現する「業務プロセス最適化」とは。具体的な進め方や打ち手を解説
2025年07月28日(月)掲載
労働人口の減少が問題となっている今日では、いかにして生産性を向上させられるかが経営での重要なポイントとなっています。そのような潮流の中で注目を集めている取り組みが、「業務プロセス最適化」です。
本記事では、業務プロセス最適化の概要を説明した上で、その進め方や具体的な打ち手も解説します。自社の生産性を向上させるための手立てにお悩みの方は、ぜひご一読ください。
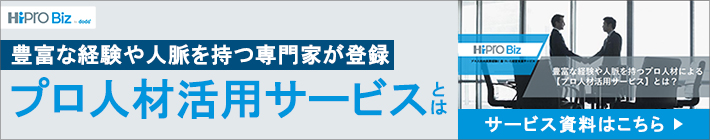
■業務プロセス最適化とは
■業務プロセス最適化の進め方
■業務プロセス最適化の具体的な打ち手
■業務プロセス最適化を成功させるポイント
■業務プロセス最適化で生産性を向上させることが、これからの時代では重要となる
業務プロセス最適化とは
「業務プロセス最適化」は、特定の業務が開始されてから終了するまでの一連のステップ、つまり「業務プロセス」を改善し、会社全体の利益を高めていく取り組みです。
業務プロセスを全く持たない企業は、ほとんど存在しないと言えるでしょう。
明文化されているか否かの違いはあるかもしれませんが、どの企業も基本的には何らかのプロセスに従って業務を進めることとなります。ゆえに業務プロセスの最適化は、業種や職種、あるいは規模の違いに関係なく、全ての企業に共通の取り組みとなり得ます。
業務プロセス最適化の目的と求められる理由
業務プロセス最適化を行う目的は、企業の生産性を改善し、より効率的に利益を生み出せる構造をつくることにあります。
業務を進めるにあたっての無駄な工程を取り除けば、企業の生産性は自然と向上し、コスト削減による利益率の改善が図れます。また業務の進め方が見直されれば、従業員のワークライフバランス、さらにはエンゲージメントも向上し、社内の動きがさらに活発になるでしょう。
近年はしばらく採用での売り手市場が続いており、十分な数の人材を確保できていない企業が少なくありません。このような状況下では、限られた人数で少しでも効率的に利益を生み出せるように、業務プロセスの最適化が求められます。
業務プロセス最適化と業務改善の違い
業務プロセス最適化と似た概念として、「業務改善」が存在します。両者は定義として明確に差別化されているわけではありませんが、一般的には以下の違いがあるとされています。
| 項目 | 業務プロセス最適化 | 業務改善 |
|---|---|---|
| 改善の範囲 | 業務のプロセス全体 | 課題のある一部分のみ |
| プロセス全体の変更(ステップの追加や入れ替えなど) | あり | なし |
| 取り組む主体 | 複数の部署あるいは全社 | 課題に関連する部署のみ |
業務プロセス全体を見直すか、あるいは業務の中の一部分にフォーカスするか、という点が両者の大きな違いです。またそれに付随して、プロセスそのものの改修の有無や取り組む主体も変わります。 全社的に何らかの支障が出ている状態であれば業務プロセス最適化を、局所的な課題に対しては業務改善を、と使い分けられると理想的です。
業務プロセス最適化の進め方
業務プロセス最適化を実践する際の基本的な流れは、以下の通りです。
- 業務プロセスの細分化と課題の洗い出し
- プロセスごとの数値の把握と具体的な目標設定
- 改善方法の選定と実行
- 成果状況の確認と改善作業
業務プロセスの細分化と課題の洗い出し
自社にどのような課題があるのかを把握しなくては、業務プロセスを最適化するのは困難になります。そのため、まずは業務プロセスを一つひとつのステップに細分化した上で、非効率的になっている箇所を洗い出していきます。
業務プロセスを細分化する際は、以下の3点を意識しましょう。
- 作業手順を書き出す
- 作業の内容を詳細に書き出す
- 担当者ごとの作業パターンを書き出す
順番に作業を洗い出しそれぞれの内容を具体的に整理していけば、現場で課題となっている部分が浮き彫りになってくるでしょう。この際、実際に作業を担当している従業員やその関係者にもヒアリングすれば、現場の目線により近い意見を吸い上げられます。
プロセスごとの数値の把握と具体的な目標設定
最適化の対象となった業務プロセスごとに課題を洗い出したら、それが具体的にどのような影響を与えているのかを把握しましょう。
この際、「資料作成時のデータ検索で合計○時間かかっている」といったふうに、数値的に影響を可視化することが重要となります。課題の現状を定量的に把握できないと、改善策の方向感が定まらないためです。
プロセスごとの課題を数値化したあとは、その値をベースにKGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)を設定します。例えば、「バックオフィスの生産性を15%向上させる」というKGIを設定したら、それを達成するために「1作業当たりの所要時間を20分短縮する」というKPIを定めます。
KGIとKPIを詳細に設定できるか否かが業務プロセス最適化の成否を左右するので、設定する数値は慎重に決定したいところです。
改善方法の選定と実行
次に、設定したKGIとKPIを達成するための具体的な改善方法を選定します。
業務プロセス最適化を効果的に実行する上では、ビジネスシーンで頻繁に用いられるさまざまなフレームワークが活用できます。
中でも有用なフレームワークが、「ECRS(イクルス)」です。これは、業務を最適化する際の優先度を決めるフレームワークであり、活用することで効率良く改善活動を進められます。
改善方法を決める際に役立つフレームワーク「ECRS」
ECRSの詳細をさらに深掘りしていきましょう。 ECRSの各アルファベットは、前から順に「Eliminate(排除)」「Combine(結合)」「Rearrange(再配置や交換)」「Simplify(簡素化)」の頭文字となっています。この4つの単語が指す内容は、それぞれ以下の通りです。
- Eliminate:排除しても何も問題がない業務はないか
- Combine:内容が類似しておりまとめられる業務はないか
- Rearrange:業務の順番をより効率的な流れに入れ替えられないか
- Simplify:業務の内容をより簡単にできないか
この4つの観点で既存の業務プロセスの無駄を洗い出すことが、効率的な最適化につながります。
成果状況の確認と改善作業
フレームワークを活用して改善活動を実行したら、その後の成果状況を確認した上でPDCAを回して活動を継続します。
実際のところ、業務プロセス最適化が一度の取り組みでうまくいくケースはほとんどありません。長期的に改善活動を繰り返す中で内容を都度見直していき、徐々に確度を上げていくことが重要となります。
業務プロセス最適化の具体的な打ち手
業務プロセスの最適化に取り組む際の具体的な施策として、日本企業ではこれまでRPAやAI-OCRなどが用いられてきました。しかしそういった従来の施策では、単一のタスクや部分的な最適化しかかなわず、業務プロセスのエンドツーエンドでの最適化は難しい、という現状があります。
こうした状況を打破できるとして近年注目を集めている施策が、「ハイパーオートメーション」をはじめとする以下の3つの打ち手です。
- ハイパーオートメーションの推進
- AIエージェントの活用
- 従業員体験(EX)向上のための従業員エンゲージメント測定ツールの活用
ハイパーオートメーションの推進
ハイパーオートメーションは、さまざまなツールを組み合わせて業務プロセスの自動化を目指す概念です。多種多様なツールを併用して、自動化によるプロセス全体の最適化を実現します。
一つの業務プロセス内のステップが非常に多く、関連する部署やシステムも多数になるケースでは、ハイパーオートメーションによる総合的なアプローチが特に有用です。
一点、ハイパーオートメーションは、単にツールを組み合わせて作業を効率化するものではないことに注意しましょう。ハイパーオートメーションの目的は、業務プロセス全体を根底から改善することであり、そのためには、時に組織風土の改革や人材の育成なども必要となる場合があります。
関連記事:RPAを活用した業務の効率化 ~導入プロセスとよくある課題を事例で紹介~
ハイパーオートメーションの課題
ハイパーオートメーションを推進するにあたって課題となる点の一つが、コスト面です。業務プロセスを大きく変えることによるコストはもちろん、各種ツールを導入し、構築する際のコストも発生します。
また、ハイパーオートメーションの導入直後には、従業員が新しい業務プロセスに慣れず、イレギュラーが多発することも予想されます。そのため、ハイパーオートメーションの導入と並行して、トラブルに対するサポート体制の整備も進めなくてはなりません。
AIエージェントの活用
近年急速に普及が進んだAIエージェントも、業務プロセス最適化の具体策として適しています。
AIエージェントは、設定された目標に向けて計画の立案や手段の選択を主体的に行い、ユーザーを支援するシステムです。従来のチャットボットなどと異なり、ただ質問に答える、あるいは情報を提供するだけではなく、推論によって最適なアイデアを提供してくれる点が大きな強みです。
このような特性上、AIエージェントは主にコールセンター業務やオペレーター業務のプロセス最適化で活用されています。また、コードの自動生成機能を追加したAIエージェントで、プログラマー人材の育成や非プログラマーによるコーディングの促進などを実施しているケースもあります。
関連記事:AIエージェントとは?生成AIとの違いや種類、活用例を解説
AIエージェント実用化における課題
AIエージェントを実用化する際の課題としては、まず「行動の信頼性を確保することが難しい」点が挙げられます。つまり、場合によってはAIエージェントがユーザーの意図しない挙動を取るケースがあるのです。 この事態を事前に防ぐためには、AIエージェントを常に監視し、任意のタイミングで動作を制御できる機能を実装しなくてはなりません。
従業員体験(EX)向上のための従業員エンゲージメント測定ツールの活用
従業員体験、いわゆるEX(Employee Experience)の向上によっても、業務プロセスの最適化はかないます。そこで必要となるツールが、従業員エンゲージメント測定ツールです。
測定ツールを用いて従業員の声を継続的に集めることで、業務プロセスに存在する問題を現場目線で明らかにできます。その上で業務プロセスの最適化を実施すれば、全社的に生産性が増加し、さらには従業員の定着率向上にもつながります。
業務プロセス最適化を成功させるポイント
最後に、業務プロセス最適化を成功させるために意識したいポイントを解説します。
- 業務プロセスを可視化しボトルネックを特定する
- 目的や意図を社内に浸透させる
- データドリブンによる意思決定につなげる
業務プロセスを可視化しボトルネックを特定する
業務プロセスの全体を可視化し、ボトルネックとなっている部分を全体的な観点から洗い出すことが、最適化を実行する上では重要です。
繰り返しになりますが、個別の課題の改善が業務プロセス最適化の目的ではありません。
業務の全体的な流れを一から見直し、根本的な部分から効率化を目指していくことが、業務プロセス最適化のゴールとなります。そしてそのためには、業務プロセスの開始から終了までの全てのステップを可視化し、効率化の妨げとなっている部分を把握しなくてはならないのです。
よって最適化に取り組む際は、フローチャートなどを活用した業務プロセス全体の可視化から始めましょう。
目的や意図を社内に浸透させる
業務プロセスを最適化する目的や経営陣の意図を、現場の従業員に浸透させることも非常に大切です。
業務プロセス最適化による変化が、全ての従業員に受け入れてもらえるとは限りません。「既存の方法に慣れ親しんでおり、新しい進め方が馴染まない」などの事情から、最適化の取り組みに抵抗感を示される場合もあるでしょう。そうした意見を無視して施策を実施すると、従業員のエンゲージメントが下がり、結果として業務の非効率化を招いてしまう恐れがあります。
業務プロセスの最適化が必要な理由や、従業員が得られる恩恵を丁寧に説明すれば、上記のような反発の発生も防げます。変化に伴うデメリット以上のメリットがあると、具体的な事例とともに示すことが重要です。
データドリブンによる意思決定につなげる
データドリブンとは、集積したデータの分析結果を基に、その後の意思決定や行動の指針を決定することです。業務プロセス最適化は、このデータドリブンの考え方に基づき、客観的な数値やデータを用いて実施する必要があります。
直感や経験則が重要になる場面もありますが、全社的な取り組みとなる以上、客観性を重視するほうが有用性を高められるためです。
特に業務プロセスの最適化では、データやコンテンツを一元的に管理する「データハブ」や「コンテンツハブ」の構築が効果を発揮します。参照先を一元化することで、各プロセスやステップが効率良くデータやコンテンツにアクセスできるようになり、スムーズに最適化を進められます。
業務プロセス最適化で生産性を向上させることが、これからの時代では重要となる
今回は、業務プロセス最適化の進め方や具体的な施策、また成功させるためのポイントを解説しました。
労働人口の減少が続く現代では、業務プロセス最適化により従業員一人ひとりの生産性を向上させることが非常に重要です。ハイパーオートメーションやAIエージェントなどを有効活用し、業務プロセスの最適化を効率良く進めましょう。
もし自社だけで業務プロセス最適化を実施することが難しいのであれば、ぜひ一度「HiPro Biz」にご相談ください。さまざまな経営課題を解決してきたプロ人材と共に業務プロセス最適化の取り組みを支援します。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)




