顧問とは?活用のメリットや報酬、ほかの役職との違いや事例を解説
2024年01月22日(月)掲載
- キーワード:
顧問とは、ビジネスで使用される場合、一般的に事業成長や停滞感の解消を目的として企業にアドバイスなどを行う人材を指します。これまで顧問は、取締役や役員などが引退後にそのまま就任することが一般的でした。しかし、近年の人手不足や事業サイクルの加速に伴い、プロ人材を顧問とした活用ケースが増えてきています。
それでは、企業にとって顧問とはどのような活用メリットや活用事例があるのでしょうか。こちらの記事では「顧問とはどういった人材、ポジションなのか」といった疑問を持つ方を対象に、顧問の概要や活用するメリット、企業が顧問を活用した事例などについても紹介します。自社で顧問を活用した際の具体的なイメージをつかむための参考材料としてご活用ください。
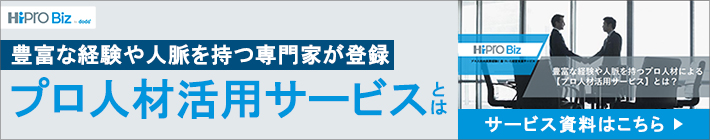
■企業での顧問の意味は?報酬の考え方や内部顧問・外部顧問の違い
■顧問とほかの役職の違い
■外部顧問を活用するメリット
■企業が顧問を活用するメリット
■顧問活用の懸念点
■顧問の報酬・待遇の体系
■顧問の勤務形態
■顧問の契約形態
■法人で外部顧問を活用した事例
■外部顧問を活用する際のポイント
■顧問・専門家のプロ人材紹介サービス『HiPro Biz』
■顧問の意味や全体像を理解し、社内での活用イメージをつかむ
企業での顧問の意味は?報酬の考え方や内部顧問・外部顧問の違い
ビジネス上での顧問とは、課題の解決や事業の成長のための有益なアドバイスや指導を行う人材・役職を指し、「ブレーン」や「アドバイザー」と呼ばれるケースもあります。一般的に経営での意思決定権や議決権を持たず、設置の有無は企業の自由です。加えて、日本特有のポジションであるため、英語などの外国語で表現するのが難しいと言われています。
また、顧問の中でもその契約形態やどのような専門分野の業務を依頼するかで報酬額が大きく変わります。したがって、顧問を活用する場合は依頼する業務内容の範囲や専門度を鑑み、それに見合った報酬額を検討しましょう。
内部顧問と外部顧問の違い
顧問は「内部顧問」と「外部顧問」の2種類に分けられます。それぞれの違いは以下の通りです。
| 内部顧問 | 外部顧問 | |
|---|---|---|
| 定義 | 社内の人材が務める | 社外の人材が務める |
| 務める人材の例 |
・元取締役 ・会長 ・オーナー株主 |
・弁護士 ・税理士 ・公認会計士 |
| 強み | 社内事情に詳しいため、実務に即したアドバイスが強み | 専門的な知識を活かした、第三者目線でのアドバイスが強み |
社内の重役がその会社で顧問を担う場合、その人材を内部顧問といいます。取締役を担っていた人材が退任後に顧問になるケースや、会長などの役員を務めている人材が顧問を兼任するケースがよくみられます。自社内での業務経験があり、内部事情にも精通しているため、それらを踏まえて具体的にアドバイスできる点が特徴です。
一方、社外の人材が務める顧問のことを外部顧問とよびます。大手企業での経営実績がある人材、または弁護士や税理士といった専門的な知識を有するプロ人材が務めるケースが一般的です。第三者ならではの、多角的なアドバイスやコネクションの活用が期待できます。
顧問とほかの役職の違い
顧問と混同しやすい役職に「相談役」「参与」「役員」があります。それぞれの違いについて、概要や特徴を踏まえながら確認していきましょう。
相談役と顧問の違い
相談役とは、企業を経営していくことで生じる課題や問題に対し、臨時的にアドバイスなどを求められる役職です。情報漏えいや著作権侵害など、会社で重大な問題が発生した際に、問題を解決するためのアドバイスを行います。相談役は社内の重役が退任後に就任するケースが一般的で、名誉職の意味合いが強い傾向にあります。
参与と顧問の違い
参与とは、社内の専門分野で管理職と同程度の知識を有すると認められた人材に与えられる職能資格です。資格制度の定義やポジションは各企業によって異なりますが、経営や業務を行うための実質的な権限を与えられているケースが一般的です。
役員と顧問の違い
役員とは、「取締役」や「会計参与」、「監査役」などを指す役職です。役員は会社法で定義されており、会社全体の方針を決める権限を持ちます。企業によっては、取締役などの役員の地位を保ちながら顧問や相談役などの役職を兼任することもあり、その場合会社法上は役員であるものの、事実上の立場・役職としては顧問や相談役として業務を行うことになります。
外部顧問を活用するメリット
外部顧問を活用することで、企業は多くのメリットを得られる可能性があります。 ここでは4つの代表的なメリットを紹介しますので、外部顧問の依頼を検討する際にお役立てください。
意思決定のスピード向上
意思決定を円滑に進められるようになる点は、外部顧問を活用する大きなメリットです。
現代のビジネスシーンでは、競合他社に後れを取らないよう、迅速な意思決定が求められます。豊富な経験と知識を有する外部顧問からのアドバイスを受けることで、経営判断の材料が揃いやすくなるため、結果として意思決定のスピード向上が図れます。
企業課題に応じた柔軟な契約形態
自社の課題に応じて契約形態を自由に選べることも、外部顧問を活用するメリットとして挙げられます。
外部顧問の契約形態は、「業務委託」「顧問契約」「雇用契約」などさまざまです。必要なときにのみ依頼できる外部顧問であれば、費用を抑えてアドバイスを受けられるでしょう。
機能戦略の明確化
外部顧問を活用することで、機能戦略も明確にできます。
機能戦略とは、事業の拡大に向けて各部門が策定する施策のことです。経営上の行動指針のような役割を担っているため、あいまいなままでは事業を進められませんが、その立案には相応の時間と専門的な知識が求められます。従って、自社の力のみで進めることは容易ではありません。
その点、外部顧問を活用すれば専門的な知見に基づくアドバイスによって、機能戦略を円滑に立案できるようになります。
企業ブランドの向上
自社のブランド価値を高められる点も、外部顧問を活用するメリットの一つです。
外部顧問の中には、業界内で高い評価を得ている人材も存在します。こうした人材を外部顧問として迎え入れることで、取引先の新規開拓や商談の際に、自社の信頼度や専門性をアピールできるでしょう。
また、著名で実績のある外部顧問の存在は、社内の従業員にとって刺激になるため、組織全体の成長にもつながるかもしれません。
企業が顧問を活用するメリット
近年、上場企業を中心に顧問を設置する企業が増えつつあります。企業が顧問を活用するのは、確かなメリットがあるからです。企業が顧問を活用する代表的な3つのメリットを見ていきましょう。
経営などに関する専門的・客観的なアドバイスを素早く受けられる
企業が専門的な知識を有する人材を顧問に配置することで、専門的なアドバイスを受けやすくなります。例えば、社内で経営上の課題を解決し得る豊富な知見を持つ人材がいない場合、課題を解決するための人材を内部で育成するとなると相当な時間がかかるでしょう。そのような場合に、経営に精通した人材を顧問として活用することで、新たな人材を育成するよりも早く、かつ高い精度で知識を取り入れて課題解決に取り組める可能性があります。また、社外の人材を顧問として活用する場合より、客観的な目線からアドバイスを受けられる点もメリットです。
トラブルの未然防止などを期待できる
顧問を活用することで、トラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。専門的な知識を有する顧問に日ごろから会社の状況を共有し、前もって予防策を提案してもらえるような体制を構築しておけば、トラブルの未然防止にもつながるでしょう。加えて、万が一顧問の専門外のトラブルが発生した場合でも、顧問の豊富な人脈を活用してもらうことで、新たな対処法を得ることができるかもしれません。
取締役・役員などの役職者が自分の仕事に集中できる
顧問を活用することで、取締役や役員などを含めた役職者が自分の仕事に集中できるようになります。特に、人手が不足している企業にとっては大きなメリットといえます。企業によってはヒューマンリソースが限られ、例えば役員を筆頭とした役職者が法務・税務関係など本来は担当外の業務を行わざるを得ないケースもあるでしょう。そのような場合に、法務や税務関連に精通した顧問を外部から受け入れることで、これまで担当してきた業務を顧問に依頼し、取締役や役員が自分自身の担当業務に専念できるようになるでしょう。
顧問活用の懸念点
顧問を活用することで多くのメリットが得られる一方、懸念点もいくつか存在します。ここでは2つの懸念点をお伝えしますので、顧問を活用する際の参考にしてください。
登用が難しい
自社にとって最適な顧問を見つけて登用することは、容易ではありません。特に外部顧問の活用を検討している場合、実績のある人材は多くの企業が登用したがるため、競争率が高く、登用が難航しがちです。
また、顧問の実力や自社との相性を面接のみで見極めることは非常に困難です。従って「外部顧問を登用したものの、期待していたような成果は出なかった…」ということもよくあります。
契約の調整が難しい
顧問活用の懸念点として、契約期間の調整が難しいことも挙げられます。
一般的に、顧問契約はある程度長期間の契約を前提としていることが多いため、短期間の契約は受け入れてもらえないケースもあります。さらに内部顧問の場合は、もともと同じ会社ではたらいていた人に依頼するという都合上、関係性を配慮して解約の提案に踏み切れないこともあるでしょう。
顧問の報酬・待遇の体系
顧問の報酬形態は、「固定報酬額」「時間単価制」「成果報酬型」の3種類に大きく分けられます。
最も一般的な「固定報酬型」は、一定の月額報酬を支払う形式です。長期間にわたって継続的なサポートを受ける場合に多く採用されます。業務内容や顧問の専門性に応じて、報酬額は異なりますが、専門性が高い業務を依頼する場合は、より高額になることも珍しくありません。
「時間単価制」の場合は、顧問が実際に稼働した時間に基づいて報酬が支払われる形式です。顧問の業務にかかる時間を算出し、その時間に応じて報酬額が決まります。また、もう一つ代表的な報酬形態として挙げられる「成果報酬型」では、達成した成果次第で報酬額が変動します。
なお、顧問には役員待遇を与えることが一般的ですが、後述する勤務形態によっては無報酬での契約も可能です。余計な出費や契約上のトラブルを避けるためにも、顧問契約を結ぶ前に、報酬や待遇についてきちんと確認しておきましょう。(2025年5月時点情報)
顧問の勤務形態
ここでは、顧問がどのようにして企業と関わるのかを示す、代表的な3つの勤務形態を紹介します。
常勤顧問
常勤顧問は、毎日出社してフルタイムで業務にあたる勤務形態です。主に、内部顧問を登用する際に採用されます。常勤顧問は社内に常駐するため、企業の内情を把握しやすく、それに即したアドバイスを行える点が特徴です。
また、常勤顧問は必要なタイミングですぐに相談できることから、初めて顧問を登用する企業にとっても適しています。コミュニケーションが取りやすく、自社に寄り添ってくれる人材を登用できれば、より効果的なアドバイスが期待できます。
非常勤顧問
非常勤顧問とは、企業に常駐せず、決められた時間のみ特定の業務に携わる勤務形態のことを指します。外部顧問の活用時によく採用される勤務形態で、社外での経験や視点を活かした、柔軟で客観的なアドバイスを受けられるでしょう。
なお、非常勤顧問は「必要なときだけ出社」「月に所定の回数だけ出社」など、出社の頻度を柔軟に調整できるため、その分費用を抑えられる点が魅力です。常駐してのアドバイスは不要なものの、経営判断にプロ人材の知見を取り入れたい場合には、非常勤顧問の登用を検討することも一案です。
リモート顧問
近年では、リモート顧問を登用する企業も増加しています。
リモート顧問は、ビデオ会議やメッセージアプリを活用し、非対面で経営課題の解決に向けたアドバイスを行う勤務形態です。この形態の最大のメリットは、地理的な制約を受けることなく、自社が求める人材を全国から登用できる点にあります。さらに、移動の手間をかけずに打ち合わせが可能なため、日程調整やタスク管理も容易です。
顧問の契約形態
ここでは、顧問を雇う際の代表的な契約形態を紹介します。業務内容や目的を鑑みて、自社に適したものがあるかどうかを確認ください。
業務委託契約
業務委託契約は、特定の業務でのみアドバイスを依頼する契約形態です。内部顧問や外部顧問に関係なく結ばれる契約で、登用された顧問は独立した事業者という扱いになります。雇用ではないため、契約期間をある程度柔軟に定められる点が特徴です。
顧問に支払う費用を抑えつつ、ピンポイントで成果を上げたい場合に適した契約形態といえるでしょう。
顧問契約
長期間のアドバイスを希望する場合には、顧問契約が適しています。厳密には、顧問契約も業務委託契約の一種ですが、必要な場面で専門家の知見を求めるために継続的な関係を前提とした契約が交わされる場合、一般的な業務委託契約とは区別されます。顧問契約を結ぶことで幅広い業務に対するアドバイスを依頼できます。
雇用契約
雇用契約とは、企業が顧問を自社の従業員として雇用する契約形態のことです。業務の範囲や勤務条件、報酬といった項目で双方が合意すれば、所定の時間内でさまざまな業務を任せられます。
この契約が結ばれる具体例としては、経営やコンプライアンスの責任者を顧問に任せるケースなどが挙げられます。一従業員として社内に常駐してもらうことで、複数の部署との連携が欠かせない業務も円滑に進められるでしょう。
法人で外部顧問を活用した事例
次に、実際に顧問の役職にプロ人材を活用し、法人である企業が抱える課題を解決できた例を紹介します。自社で顧問を活用した際の具体的なイメージをつかむ参考にしてみてはいかがでしょうか。
設備関連の事業を展開しているA社は、市場の拡大や製造部門の新規設立を目指していましたが、業務の効率化に課題を抱えていました。現場の従業員は既存業務で忙しく、また効率化を目的として導入されたデバイス・システムを適切に活用できていなかったことなどが大きな要因でした。そこでA社は、DX化を推進し業務効率の改善を図るために、専門的な知識を有するプロ人材を顧問として迎え入れることにします。担当者は自社の課題をクリアにするにあたり、これまでの経験を活かしながら業務改善を推進できそうな人材を選びました。
外部顧問は、組織体制や中長期計画の確認、課題の整理・優先順位付けなどの業務を行います。またそれらとあわせて、システムベンダーと協議を重ね、社内システム構築にかかる費用を抑えつつ最大限改善できる範囲を模索しました。現状を正確に把握しながら、最適な業務フローについて議論を重ねることで、課題の抽出から新規システムの導入までの全ての工程を主導したのです。紙ベースで処理していたものをシステムに移行するなど関連業務の自動化や平準化を行ったことで、従業員の工数削減・業務全体の効率化などを実現しました。
外部顧問を活用する際のポイント
続いて、顧問とより良い関係を築き確かな効果を実感するために、顧問を活用する際のポイントを押さえておきましょう。
業務内容・費用・契約期間を明確にする
プロ人材と顧問契約を結ぶ前に、業務内容や費用、期間を明確にしましょう。これらが不明瞭な状態で顧問契約を結んでしまうと、後々トラブルが起きる可能性があるからです。例えば、企業が税理士を顧問として活用する場合、顧問料とは別に記帳代行や年末調整などの業務が別費用として設定されることが一般的です。上記のように業務内容によった費用を詳細に把握できていなければ、想定していた金額と実際の顧問からの請求額が異なり、トラブルに発展する可能性があります。
顧問・専門家のプロ人材紹介サービス『HiPro Biz』
「外部のプロ人材の力を借りて、自社の課題を解決したい」とお考えであれば、経営支援サービス「HiPro Biz」のご利用をおすすめします。「HiPro Biz」には、特定分野に深い知見や人脈のある3万名(2024年12月現在)を超えるプロ人材が登録しており、ご相談の内容に応じて、最適なプロ人材を提案し、事業のさらなる成長を支援いたします。各業界や領域で顧問として活躍してきたプロ人材も多数登録しているため、さまざまな課題への対応が可能です。
また、「HiPro Biz」では、社外取締役や社外監査役も紹介できます。本サービスを活用することで、新たな人脈と出会えるだけでなく、企業のブランド価値の向上にもつながるでしょう。
目的に応じて最適なパートナーを紹介しますので、まずはお気軽にご相談ください。
【関連ページ】
経営支援サービス「HiPro Biz」
顧問の意味や全体像を理解し、社内での活用イメージをつかむ
前述したように顧問とは事業を成長させるためのアドバイスを行う日本特有の人材・役職であり、相談役や参与、役員とは異なるポジションです。
会社が顧問を活用するメリットは多岐にわたります。例えば、顧問に社内の情報を共有しておくことでトラブルを未然に防げるかもしれません。また、企業事例などからもわかる通り、顧問は企業が抱える課題を把握した上で、社内にいてはなかなか気づきにくいことにも、客観的な立場で適切なアドバイスを行ってくれます。プロジェクトのキーパーソンとして、数々の課題解決をけん引してくれるはずです。貴社でも専門知識を有した顧問を活用することで、事業を成長させるために尽力してもらえるでしょう。
当サイトでは企業での顧問の活用方法や導入事例をはじめ、プロ人材活用にまつわる豊富なコンテンツを発信しています。あわせてご覧いただき、顧問やプロ人材活用のイメージを膨らませてみてはいかがでしょうか。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)




