松浦 年宏
- 得意分野:
- ロボティクス、
- 生産・品質
お客様のニーズに応えて状況を見極め、
仕事が完結するまで支援を続ける

PROFILE
1975年に株式会社小松製作所の入社し、特殊車両や大型ダンプトラックの設計及び生産技術に従事。1985年松下FAエンジニアリング株式会社に移り、自動化設備の外販に従事。2002年株式会社エヌエスティーに転職し、電子技術を応用した設備の開発に携わる。2008年アイエンジニアリング株式会社を設立、現在に至る。
好きな仕事で生涯現役を目指す
失敗を経てコンサルティングの道へ
私は55歳で独立しましたが、それまでに3社経験しています。同年代でこれだけ転職をしている人はごく希だと思います。この経験の中で、設計・生産技術・サービス・営業技術・社内コンサルティングという職種の面や、機械と電気という業種の面に加え、数多くの商品を経験したことが私の技術の源となっています。飽きっぽい私にとって、新しい機械を作ることはぴったりの仕事です。55歳で独立したのは、こんな素晴らしい仕事を続けたいと思ったからです。軌道に乗せるには10年くらいかかるので、再雇用定年の65歳からの逆算ですね。今でこそ転職をする人が増えてきて当たり前になりましたが、よくよく考えてみれば、65歳になって新しい仕事を始めるのは難しく、退職金をもらった人が新しい挑戦に向かえるかというと、それは無理だと思います。あと、経営者という立場を経験する必要があると考えていたこともあります。自分ではそれなりにやっているのに、サラリーマンの考え方だと当時のある社長に言われて、どうしたらわかるのかと考えていましたので。
独立を始めた最初は商社と組んで機械設備の受注活動を始めました。受注直前まで行きましたが、リーマンショックによってすべて中止になってしまいました。起業して3ヶ月目です。景気が回復し始めた時、景気の影響を大きく受ける仕事では継続することは困難と考え、自分の力でコントロールできない部分は排除して、自分が働いて自分の範囲内でできるコンサルティングに特化しようと思いました。その理由としては、会社勤めの間に、営業の努力もしましたし、機械設計もしっかりやりました。自分が指示して作った機械は他の人が作ったものより成果が出ていたので、自分の仕事に自信を持てていたことも大きかったですし、どこでも通用すると考えていたからです。
そこから自分のことを知ってもらうことが重要だと考え、ホームページを作りました。その中に自動機の技術解説をしました。今でこそ誰でもホームページは簡単に作れますが、当時は結構大変でした。そのホームページによって1件の成約があり、事業を継続できました。自分はラッキーだったと思います。

コンサルティングをして思うこと
日本の製造業に元気になってほしい
私が得意としている分野は、FA(ファクトリーオートメーション)と言われている工場の自動化です。その中でも組立や検査の自動化に関して多くの経験があります。自動化・ロボット化は人手不足の日本にとって重要なテーマなので、何とかしたいと思っている会社は多いと思います。ただ、私は営業ではなくコンサルタントなので、基本に戻って考えるようにしています。自動化は経営の手段の1つです。ほかの方法と比べ、自動化が一番良い方法ならば推進します。他の方法(例えば治具の工夫や流し方の変更)の方が費用対効果が良いのならば、自動化はしない方が良いとアドバイスします。また、保全の技術を持たない会社では高度な自動化はしない方がいいとアドバイスします。ちょっとしたトラブルで生産できなくなることがあるからです。効果が見込める自動化に対してはできるだけコストを抑える工夫をします。
そして私のコンサルティングの仕事において、一番のポイントだと思っているのは完結するもしくは結論が出るまで支援するということです。私のコンサルティングでは構想案を提示したり、設計指導をしたり、場合によっては図面を書いたりもします。アドバイザーとして、実務者として、双方の対応が可能だというところが強みだと考えています。作るところがないと言われれば作るところを紹介することも行います。お客様が何を求めているのか、お客様によって違うニーズに最後まで応えていくのが自分の仕事だと思っています。
いま日本の製造業のレベルが下がっているという危機感があります。そのための強化対策が必要ですし、世代間の引き継ぎに私も貢献できればと思っています。昔の方法を繰り返しているだけの技術者が多くて、特に大企業のサラリーマン技術者は会社がなんとかしてくれると考えているように思えます。技術者のあるべき本来の姿は、例えば技術の進歩に伴ってもっと新しい方法でもっと業務を良くしたい、と考えるのが普通です。日本企業の技術者は待遇の面で恵まれていない人が多いのも問題ですが、もっと製造業が活発な企業活動を取り戻すためには、価値を生み出す技術者に対してもっと対価を支払うという仕組みになってほしいと思います。
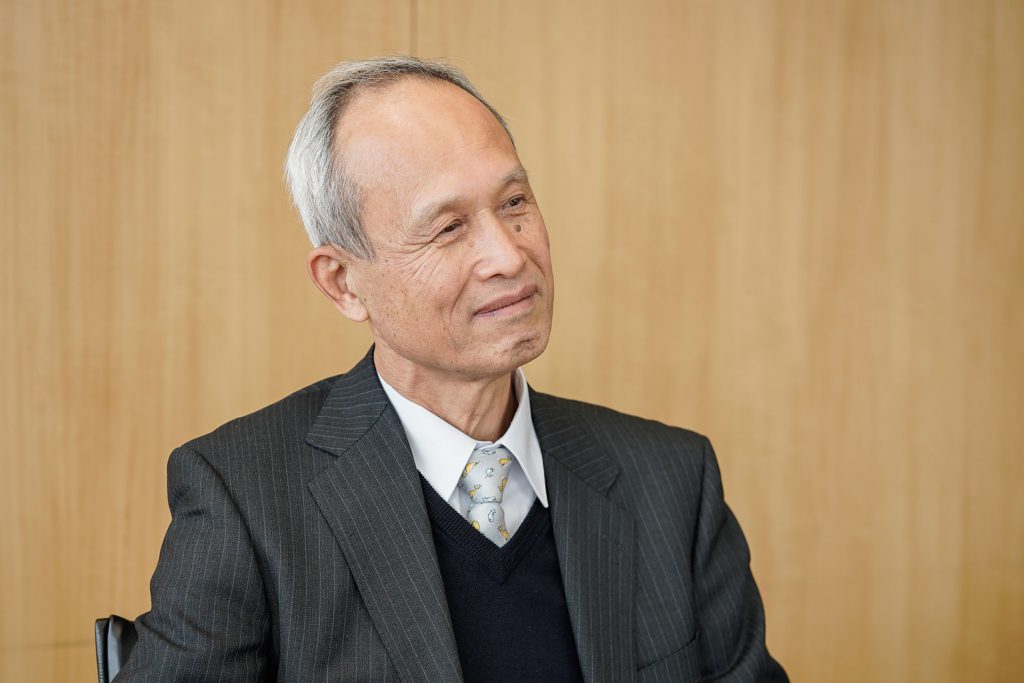
いつまでもチャレンジ
後の世代に何かを残したい
私がHiPro Bizに登録している理由は、営業の手間がかからないからです。営業活動を自分で行うとそれだけ実働時間が減るので、その分をサポートしてもらえるのは大きなメリットだと思っています。契約などの細かい話もお客様との間でやり取りしてもらえるので、それだけの価値があると考えています。HiPro Bizでは、これまで鉄鋼、化学等の大手製造業、建設業など様々な企業様の支援をさせていただきました。
コンサルティングも含めて、私は新しいもの好きなので、新しいものが出るとすぐに試してみたくなります。3Dプリンターは自分で設計してオリジナルのものを作ってみました。試作品の製作や子供向けのイベントに活用しています。技術は自分でやってみないと分からないものです。コンサルティングに関しても同じです。同じように見えても、会社によって、工場によって、担当者によって違があります。いつも新しい課題にチャレンジできるコンサルティングという職業はとても楽しいです。
そして将来的に関わってみたいのは、プログラミング教育です。2020年に小中学校で必修科目になると聞いています。今の時代には必要な知識ということもありますが、私が期待しているのはその学び方です。私の経験から言うと、プログラミングは従来の学校の勉強とは学び方が全く違います。やりたいことを決めて、そのための知識を収集することで学んでいくのです。これは社会に出て課題を解決する方法と同じです。プログラミングを学ぶことによって、小さいころから社会に出るときの準備ができるのです。しかし、学校教育のスタイルで教えられると、嫌いになる生徒が出てきそうで恐ろしく感じています。英語教育と同じで先生が教えるとなると先生を超えられないですよね。プログラミングを理解する生徒が増えて裾野が広くなれば、スティーブジョブズやイーロンマスクのような人が日本にも現れるかもしれない。こんな夢物語が実現したらいいなと思っています。
![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)

